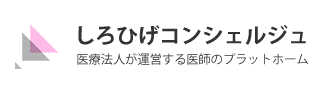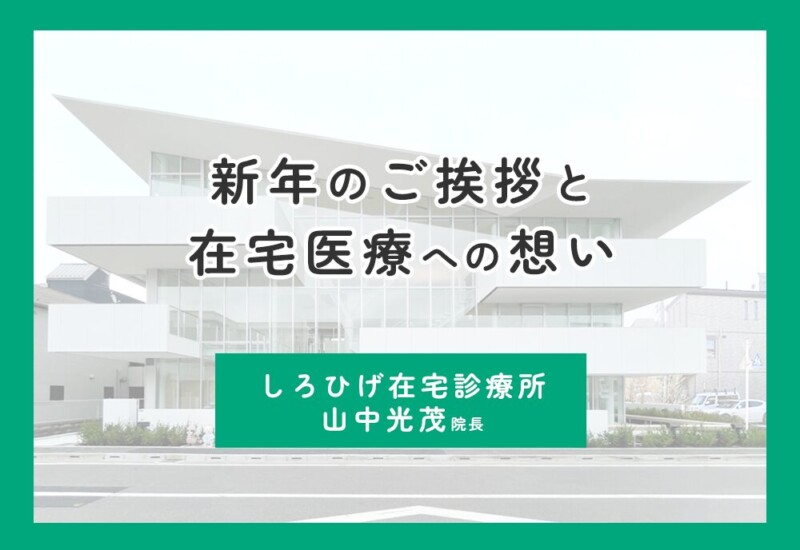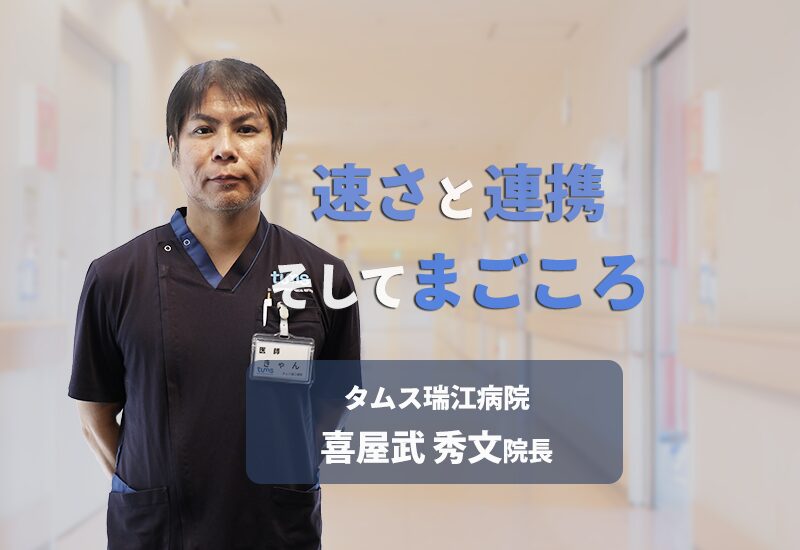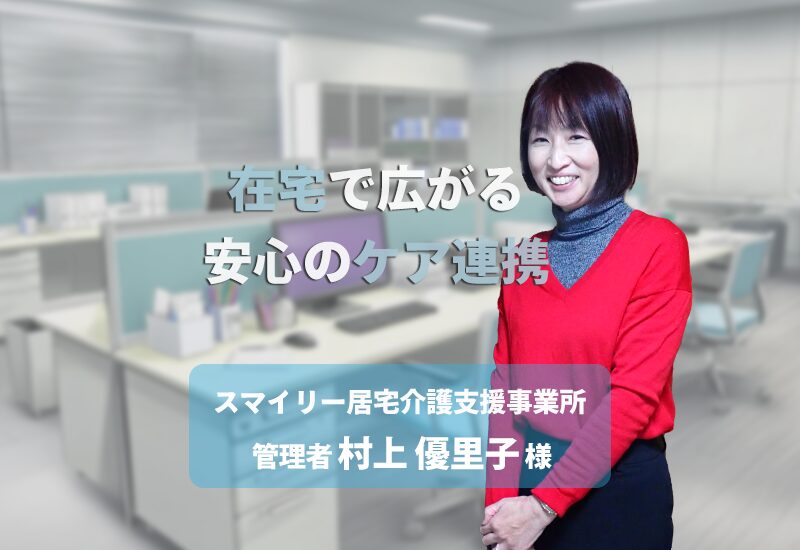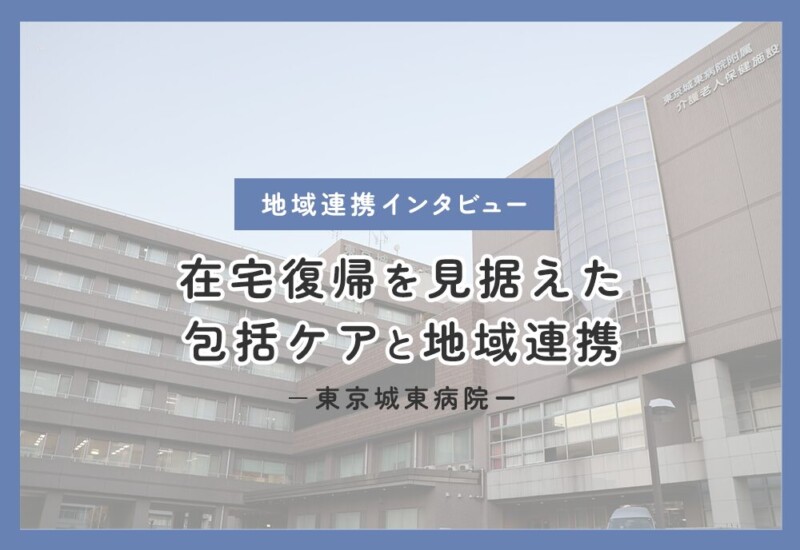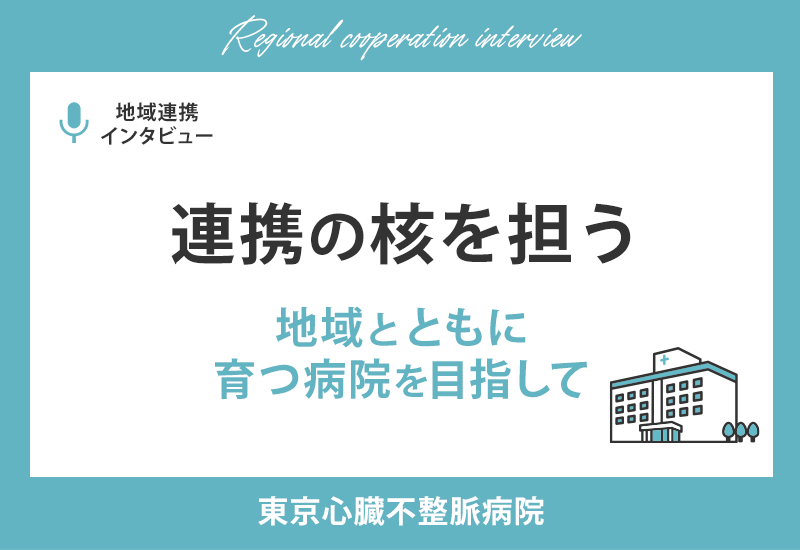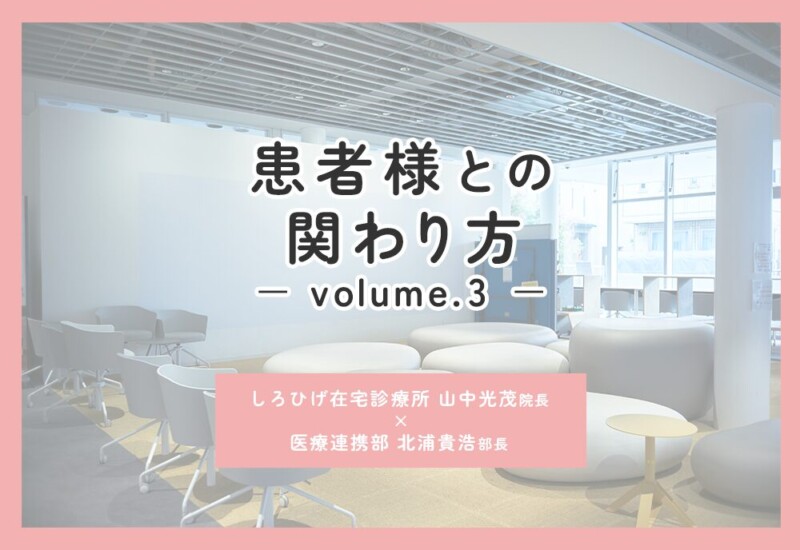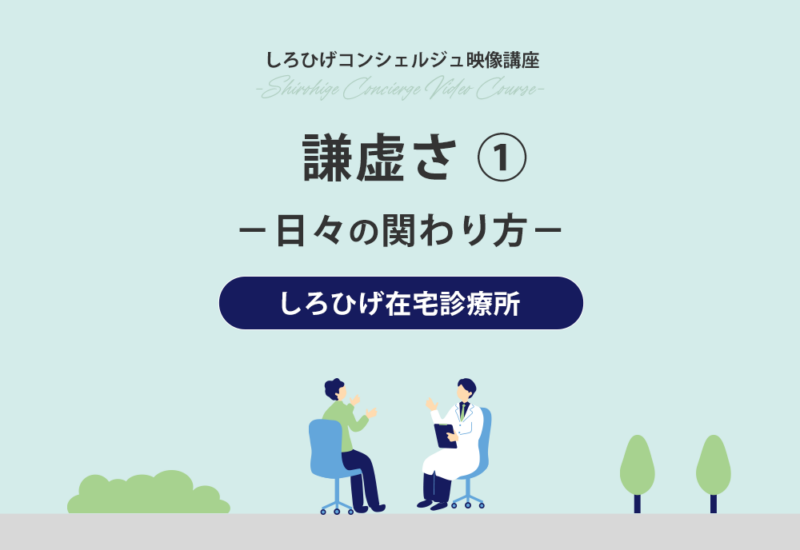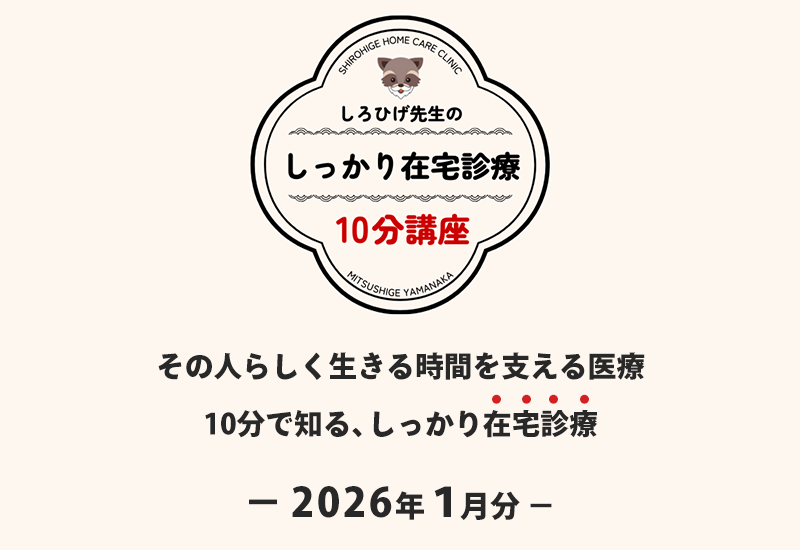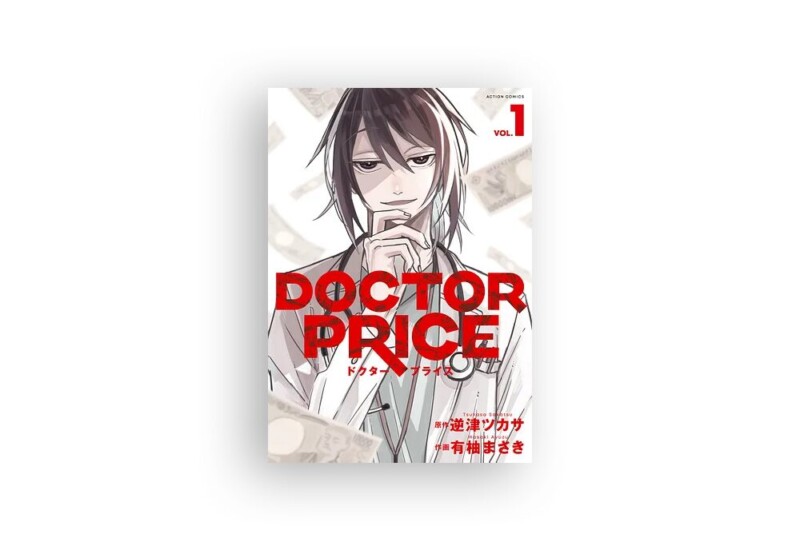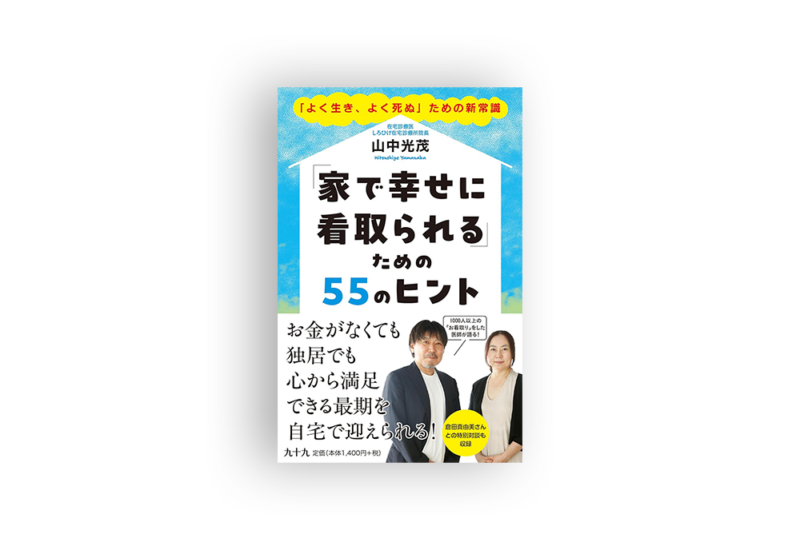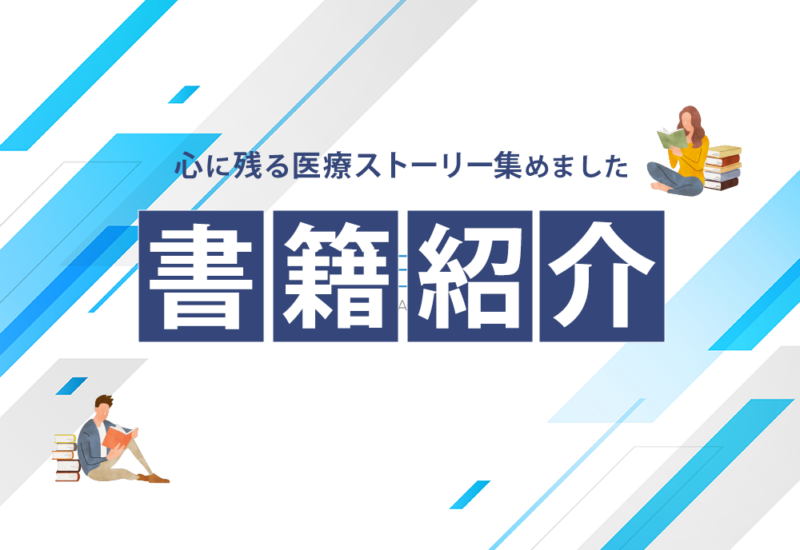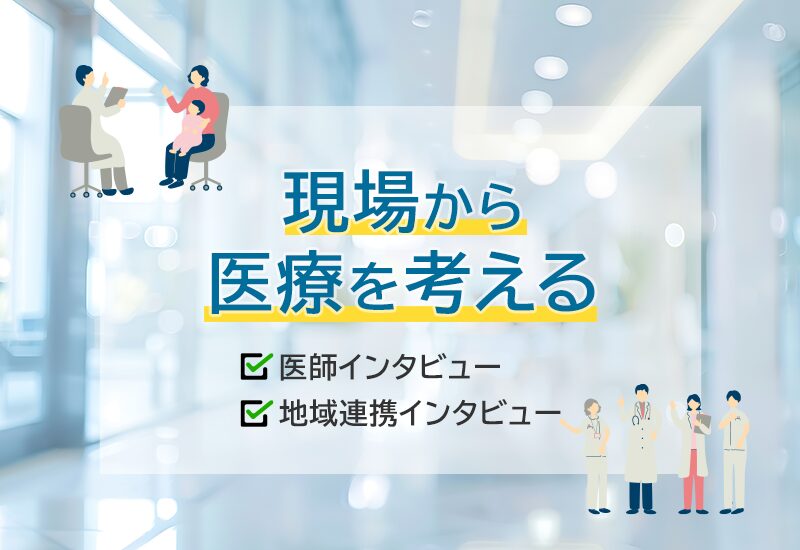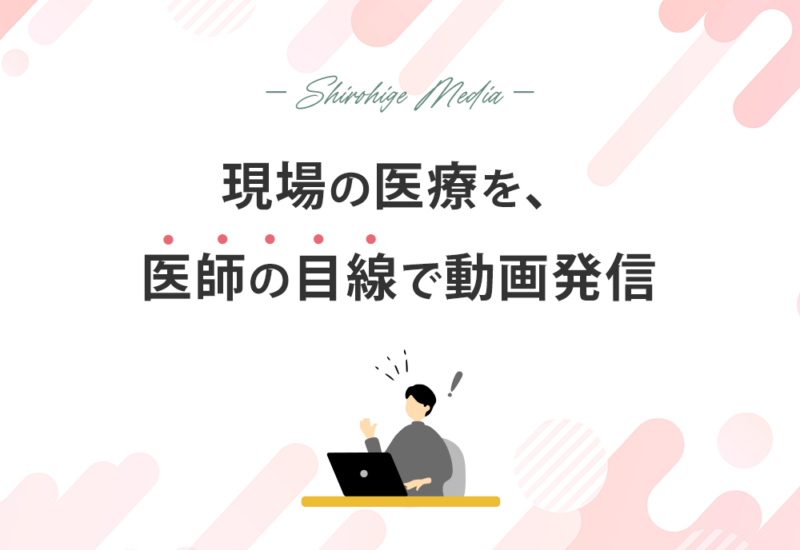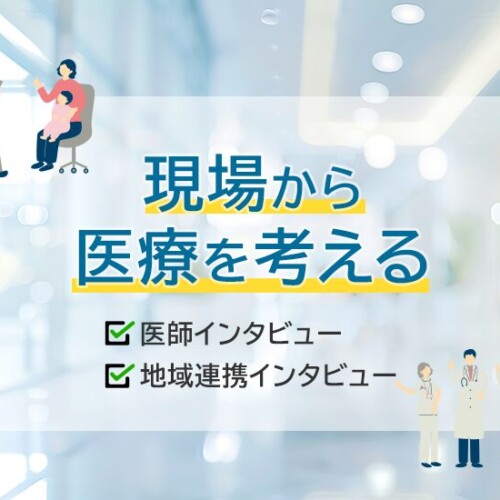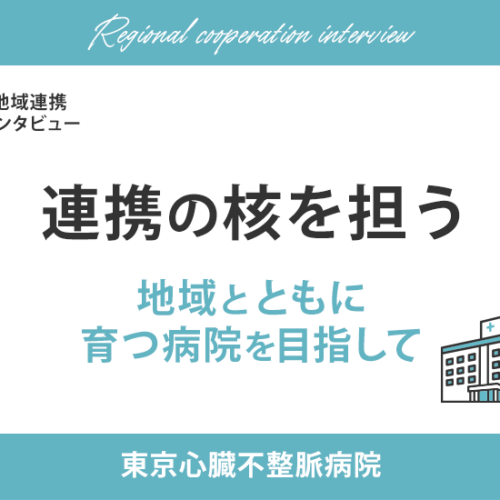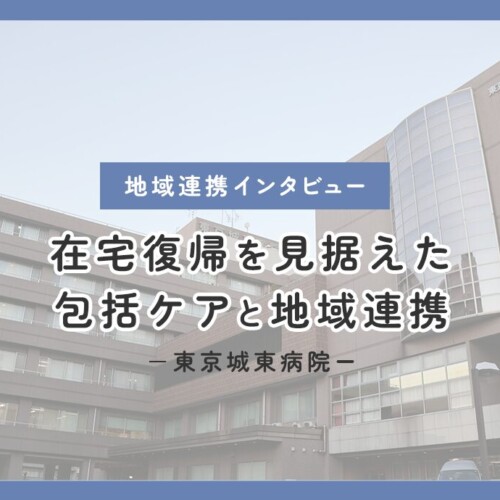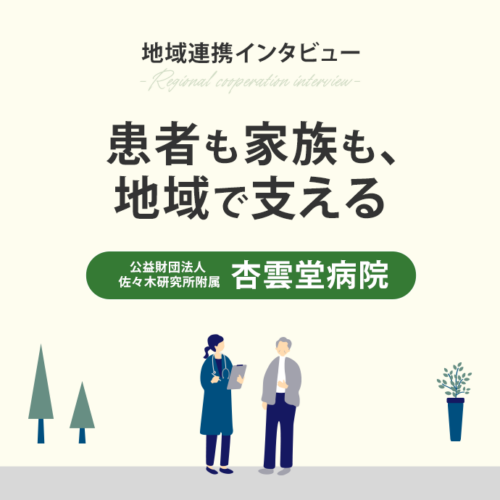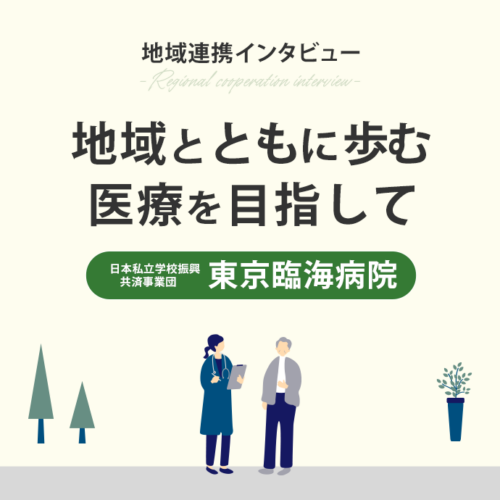治療から生活まで、地域を支える架け橋
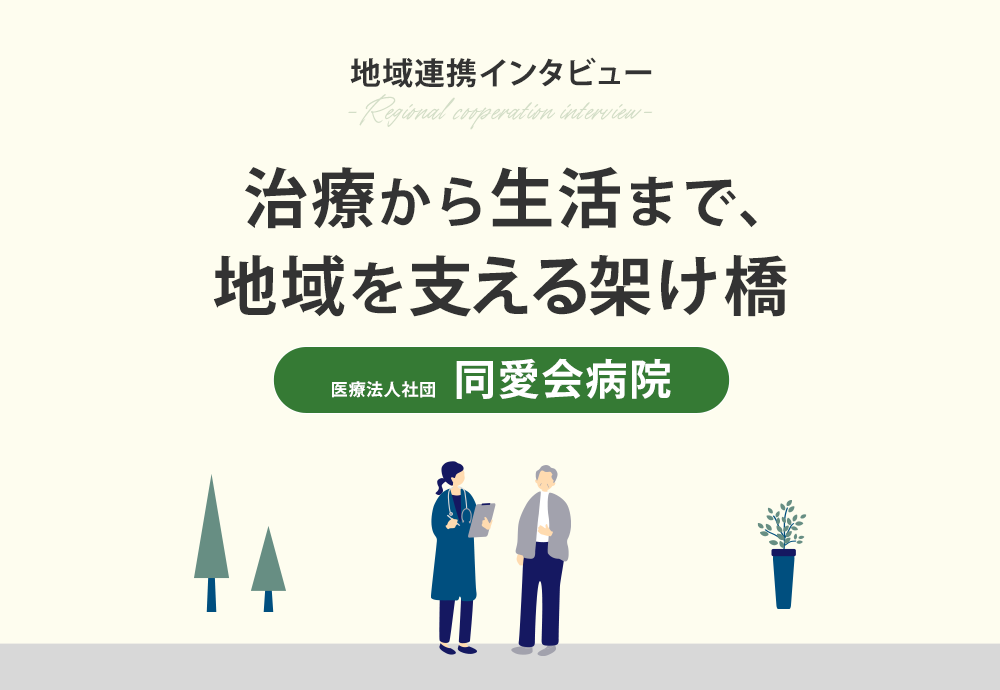
今回のインタビューでは、同愛会病院 地域連携室 室長 志村 直人 様に、地域連携の取り組みについてお話を伺いました。
-同愛会病院の歴史や概要についてお聞かせください。
1957年に開設された同愛会病院は、長年にわたり江戸川区の地域医療を支えてきました。現在は149床を備える中規模病院として、地域住民にとって身近で頼れる存在となっています。2021年4月に新病院が完成し、ハード面での整備を進めることで、安全性と快適性の両立を実現しました。
診療面では、日本大学、順天堂大学にルーツを持つ医師陣が多く在籍しており、とりわけ消化器疾患・整形外科疾患に強みを発揮しています。高齢化が進む地域特性を踏まえ、高齢者医療や生活習慣病への対応に注力している点も特徴です。地域の方々にとって、安心して通院・入院できる環境を提供し続けていることが、当院の歩みを支える大きな柱となっています。
-地域連携室の主な役割について教えてください。
地域連携室の役割は大きく二つに分かれます。一つは「前方連携」、もう一つは「後方連携」です。
前方連携では、地域のクリニックや診療所に当院の機能や強みを知っていただき、紹介患者さんをスムーズに受け入れる体制を整えています。単に患者さんを受け入れるだけでなく、紹介医との関係性を築きながら、安心してご紹介いただけるような信頼関係を大切にしています。
一方で後方連携は、入院治療を終えた患者さんが自宅や施設で安心して生活を続けられるように支援する役割です。在宅医療や介護施設への橋渡しを行い、治療から生活への移行を切れ目なくつなげていくことを重視しています。この二つの側面をバランスよく担うことで、地域における医療の循環が成り立つよう支えています。
地域連携室の日常業務は多岐にわたります。入院患者さんの情報確認や、紹介状・返書といった文書管理はもちろん、薬剤情報や治療経過を把握し、関係機関に適切に伝達する役割も担います。さらに、患者さんの中には未収金や保険未加入、独居といった社会的な課題を抱えている方も少なくありません。そうした場合には、医師・看護師・ソーシャルワーカーなどと密に連携しながら解決策を探ります。

- 日常業務ではどのようなことを行っているのでしょうか。
単に医療情報をつなぐだけではなく、社会的背景までを含めて包括的にサポートするのが、地域連携室の重要なミッションの一つです。患者さんやご家族にとって「安心して次のステップへ進める」ように下支えする存在であり続けたいと考えています。
-地域連携において工夫されている点はありますか。
当院が特に意識しているのは、地域の医療機関から「安心して紹介できる病院」と思っていただけることです。そのために救急対応や専門外診療における紹介ルートを明確化し、地域内での役割を見える化する取り組みを行っています。必要な情報はマニュアル化して共有し、連携がスムーズに進むよう工夫しています。
また、訪問診療を行うクリニックや介護施設との関係性も重視しています。入院から退院、その後の生活支援まで切れ目のない医療を提供できるよう、定期的な情報交換や相談体制を構築しています。こうした取り組みによって、患者さんが「治療後も安心できる医療環境」を感じられることを目指しています。
-地域連携においてどのような特徴がありますか。
当院では、医師と職員の距離が近く、日常的なコミュニケーションが活発であるため、院内での意思決定や情報共有がスムーズに行われ、患者さんへの対応も迅速です。また、老人施設をはじめ地域の医療・福祉施設へ積極的に挨拶や訪問を行い、信頼関係を築くことで、施設や在宅への移行も含めた連携が円滑に進められる体制を整えています。さらに、専門領域外の医療が必要な場合でも、地域の病院や専門施設との連携を迅速に行い、患者さんに最適な医療を提供できるよう努めています。

-今後の展望についてお聞かせください。
同愛会病院が目指すのは「地域の中核病院」としての拡大路線ではなく、あくまで地域に根差した存在であり続けることです。特に在宅復帰支援を重視し、訪問診療クリニックや介護施設との連携をこれまで以上に強化していきたいと考えています。
また、医療の質だけでなく「接遇」や「サービス向上」にも力を注ぎます。患者さんやご家族から寄せられるアンケートを分析し、改善につなげる取り組みを継続的に実施しています。
地域住民の方々に「同愛会病院なら安心」と思っていただけるよう、これからも誠実に歩みを進めてまいります。