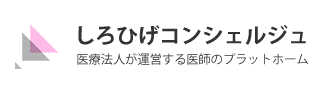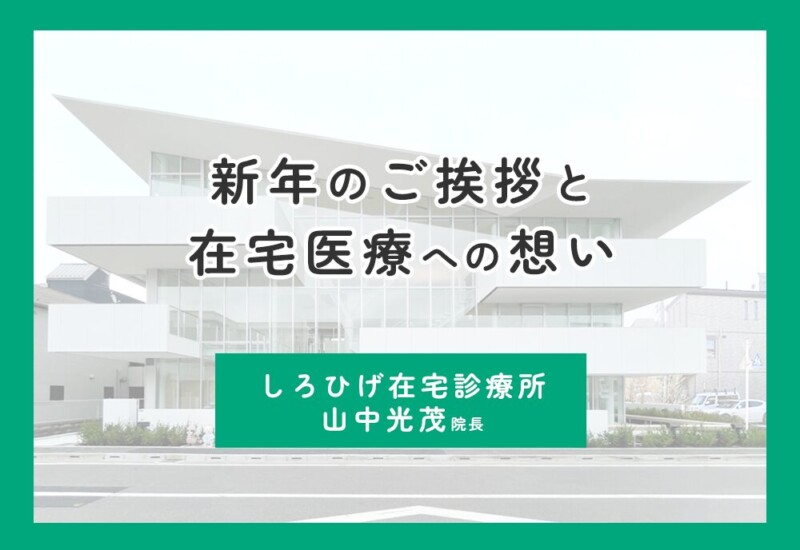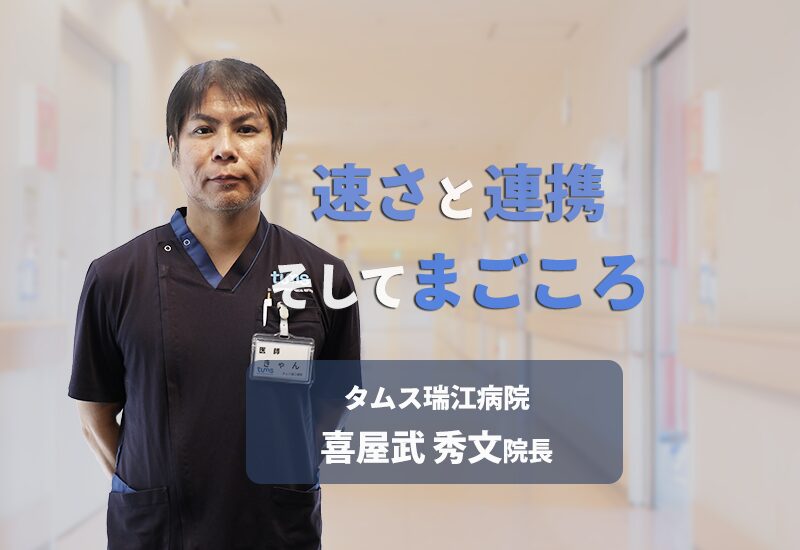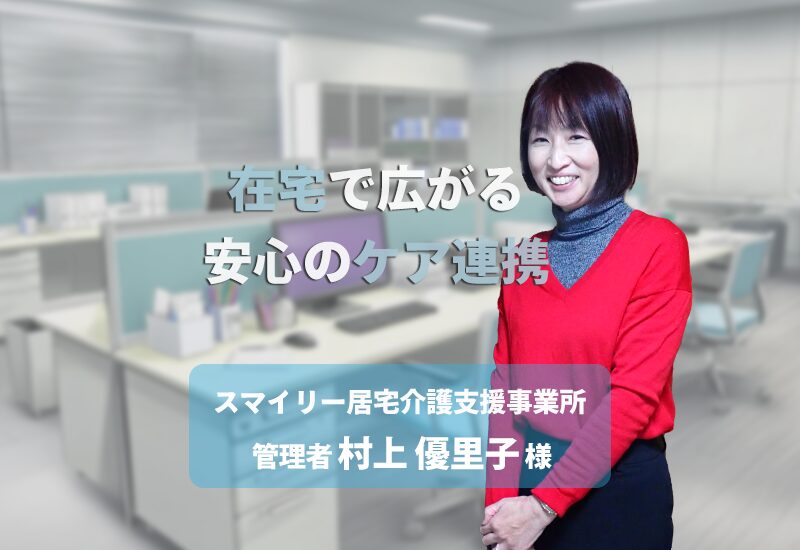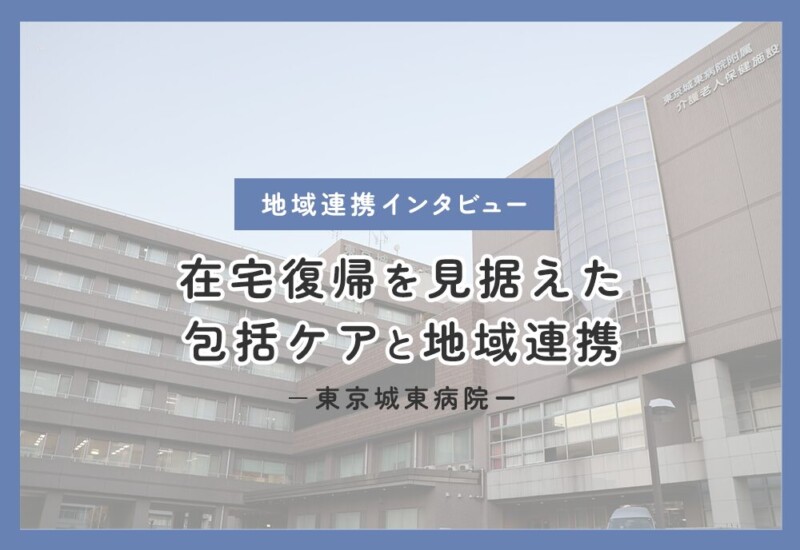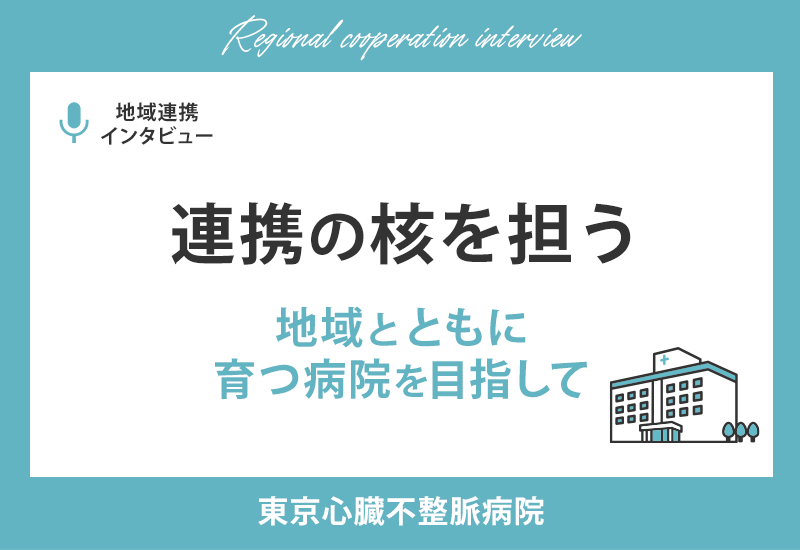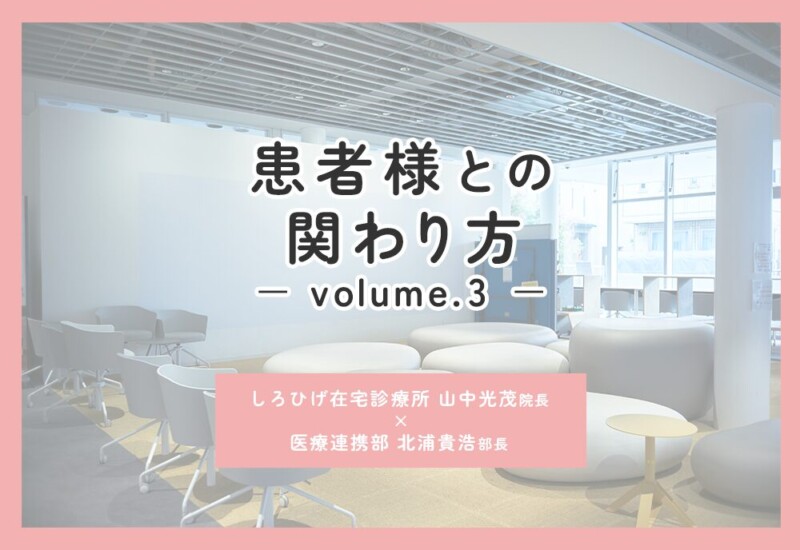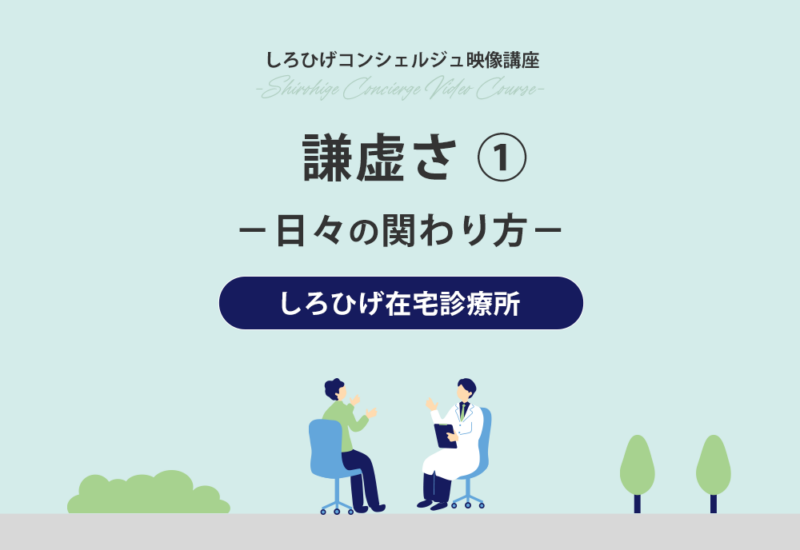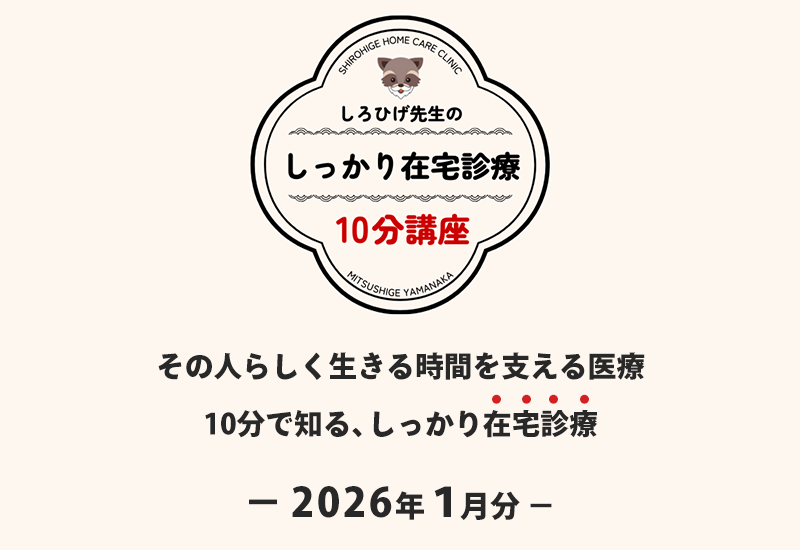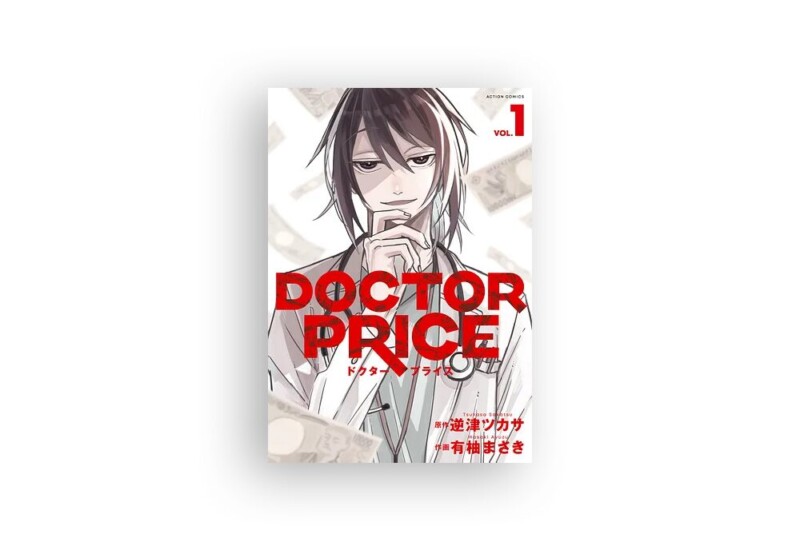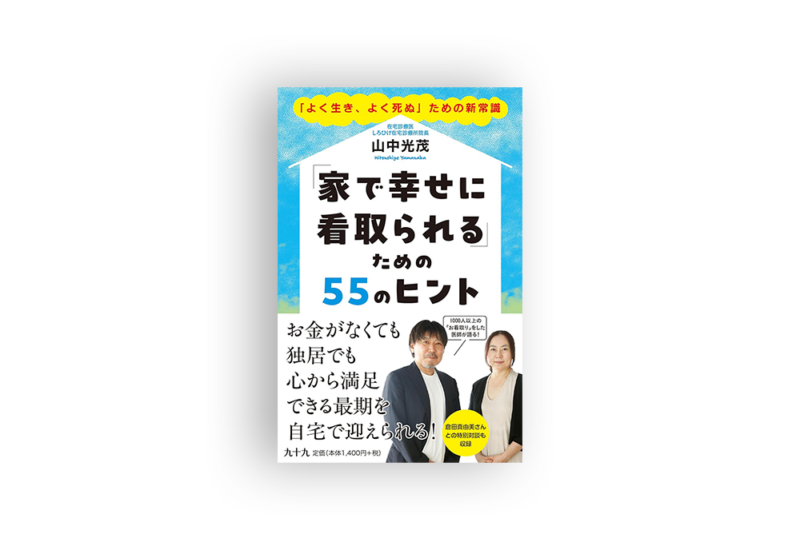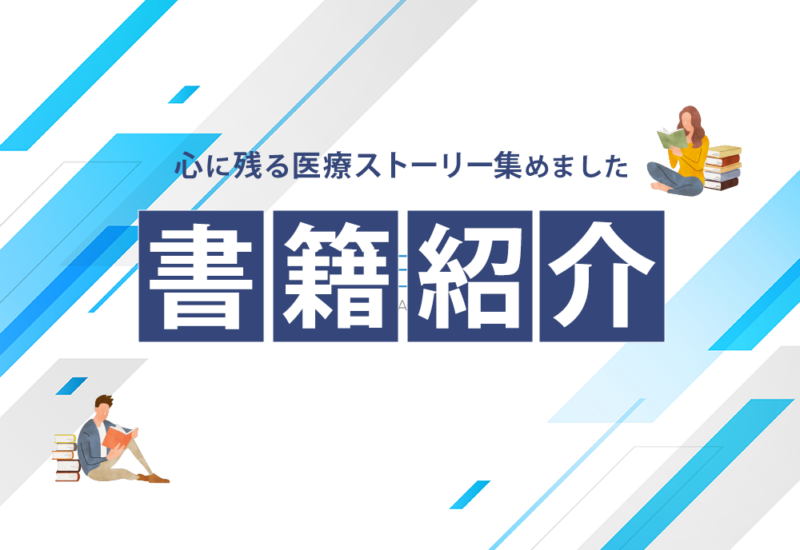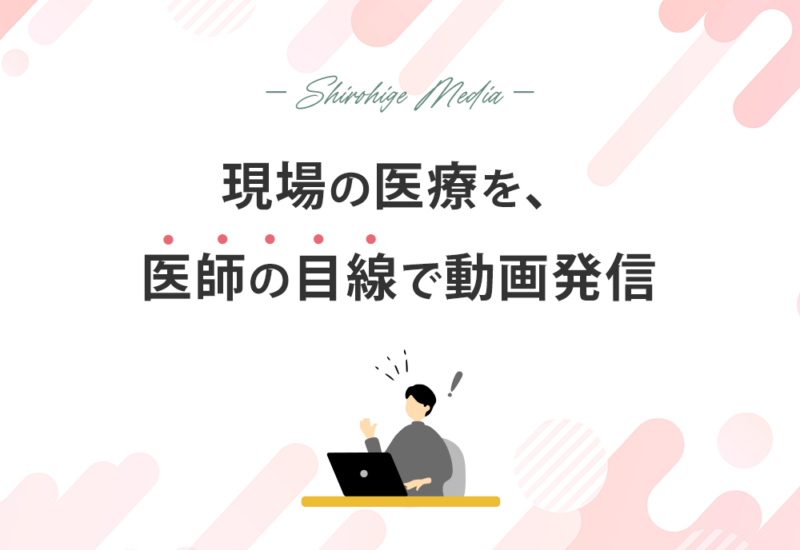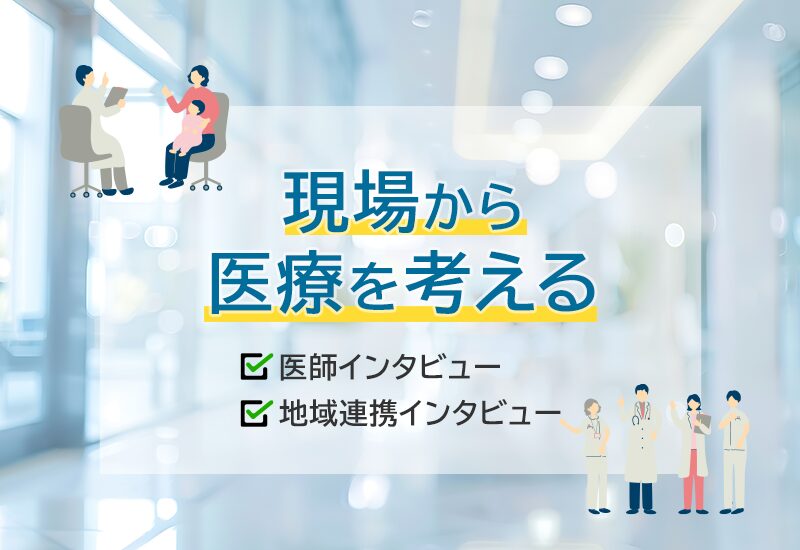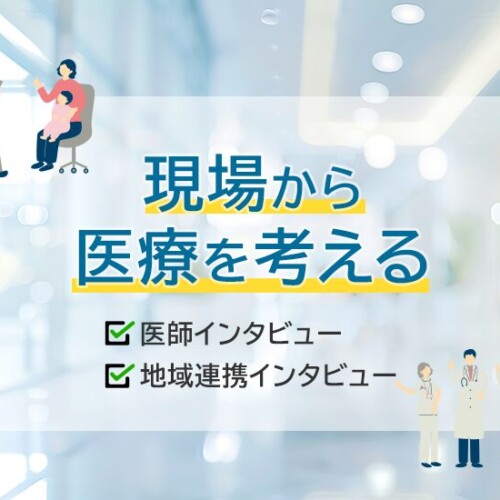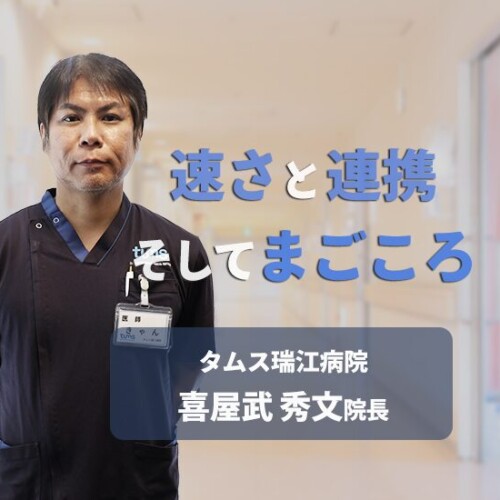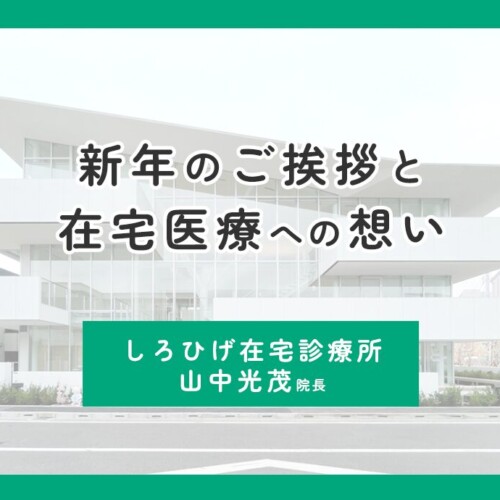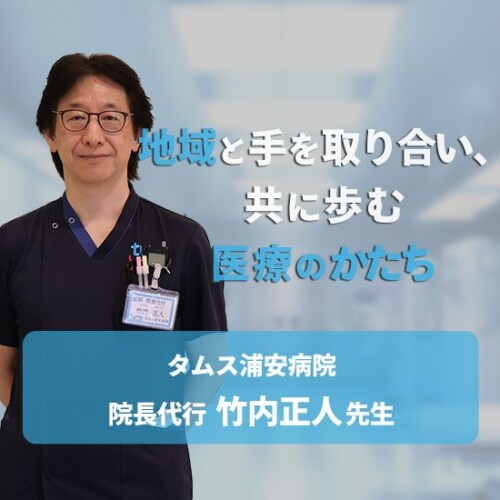救急も地域も、チームで支える脳外科の現場から
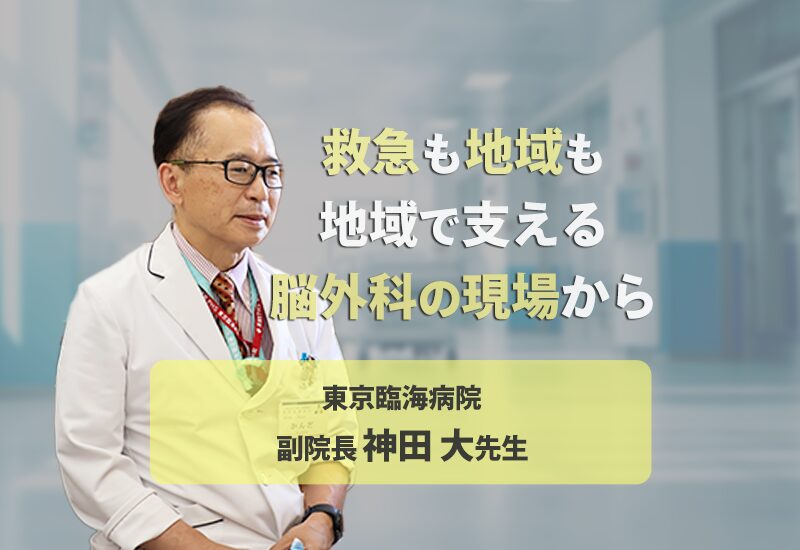
今回、東京臨海病院 副院長でいらっしゃる神田 大先生にご登場いただき、貴重なお話を伺いました。
-東京臨海病院に来られる前のキャリアについて教えてください。
私は自治医科大学を卒業後、出身地の神奈川県で僻地の診療所に住み込みで勤務し、地域医療の最前線を経験しました。
この時期には、脳外科の診療に携わりつつ、地域の患者さんの生活背景や社会状況を理解しながら医療を提供する大切さを学びました。その後、学位取得のため母校に戻り、引き続き脳外科領域で研究と臨床に従事しました。
学位取得後は、東京都で勤務することとなり、これまで培った脳外科の技術と知識を活かして診療を行っています。これまでのキャリア全体を通じて、急性期医療の技術面だけでなく、患者さんや家族の生活全体を支える医療の重要性を学び、地域医療の視点を大切にしてきました。
- 現在、東京臨海病院での脳外科医としての業務内容について教えてください。
現在は脳外科部長は藤井医師におねがいし、自分は救急対応を中心に業務を行っています。
難易度の高い手術は同僚の藤井医師に任せていますが、私はジェネラルニューロサージャンとして、幅広い症例に対応し、急性期患者の救急医療を担っています。診療対象は脳腫瘍、脳卒中、血管障害など多岐にわたり、血管障害に関しては脳卒中センターの藤井医師が中心で対応しています。
私の役割は、救急受診患者の初期評価や治療方針の決定、入院患者の療養・退院までのマネジメント、診療科間での調整など、多岐にわたる業務を包括的に行うことです。チーム全体の調整を大事にしております。

-経営企画室長としての役割や取り組みについて教えてください。
経営企画室長として、病院全体の運営改善や戦略的意思決定に関わる業務を担当することになりました。
具体的には、現場スタッフと対話を重ね、病院運営上の課題を抽出し、改善策を図っております。医療現場のニーズを経営に反映させ、医療の質と経営効率の両立を目指すことが求められます。
また、地域医療との連携や患者受け入れ体制の整備も重要な業務で、地域支援病院としての責任を果たすため、今後在宅医療や訪問診療との協力体制の構築、紹介患者数の分析、地域医療従事者との情報共有などを行ってまいります。
-地域連携入退院支援室における役割や業務内容は?
地域連携入退院支援室では、入院前から退院後までの患者のケアをサポートしています。私は主に救急患者の受け入れ調整や、診療科間での治療方針の調整を担当しています。
高齢者や複雑な病態を持つ患者の場合、どの診療科で対応するのが最適かを検討し、当該科で決定します。また、ベッドコントロールや退院調整も重要な業務で、医師、看護師、ソーシャルワーカーと密に連携し、患者が適切なタイミングで安全に退院できる体制を整えています。こうやって、地域医療機関との信頼関係を構築しています。
-若手医師の育成方針や取り組みはどのようなものですか?
若手医師の育成は、病院の医療水準を維持・向上させるための最も重要な課題ですが、彼らを指導する中堅層が不足しており、マンパワー不足ではありますが若手医師が実践的に学ぶ環境の整備に努めています。
手技や知識だけでなく、臨床判断力、チーム医療における意思決定能力、救急対応力なども身につけられるよう、実際の手術や救急対応の場で教育しています。

-副院長としての今後の展望や地域貢献について教えてください。
副院長としての今後の目標は、病院の存在意義を地域に広く示し、地域医療の質向上に寄与することです。具体的には、地域医療従事者、自治体、企業、地域住民など多様な関係者との接点を増やし、病院の取り組みや地域医療の重要性を発信していきます。
また、地域に根差した医療の提供を進めることで、患者や家族が安心して暮らせる環境を整えることを重視しています。院内では多職種連携の強化を進め、医師、看護師、ソーシャルワーカーが一体となって地域の課題に対応できる体制を整えています。
さらに、地域住民や企業、自治会などと直接交流し、地域の実情を把握して病院運営に反映させることも意識しています。