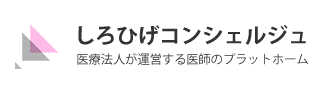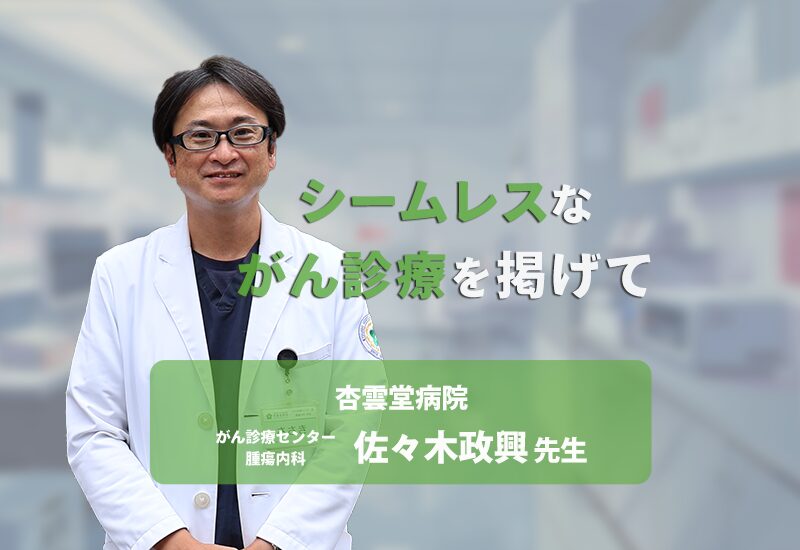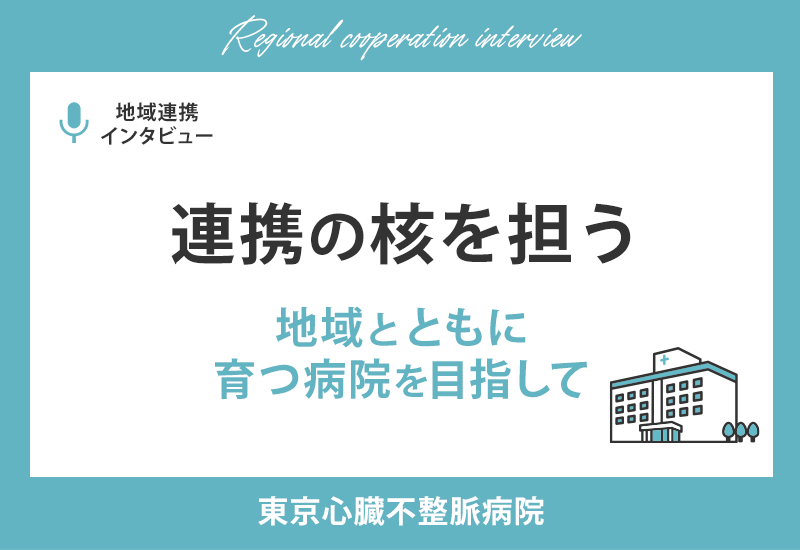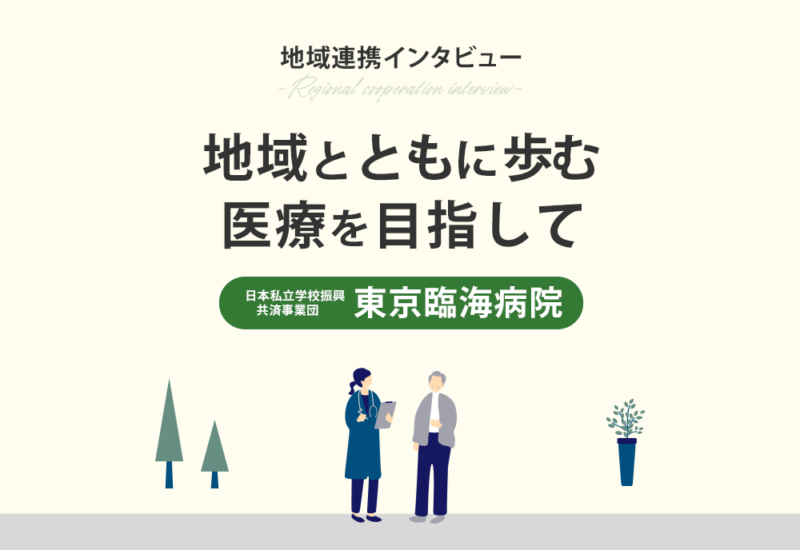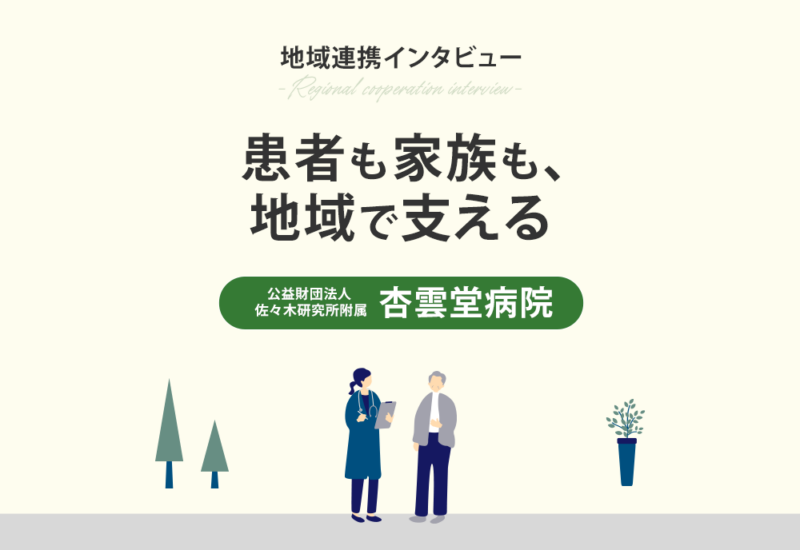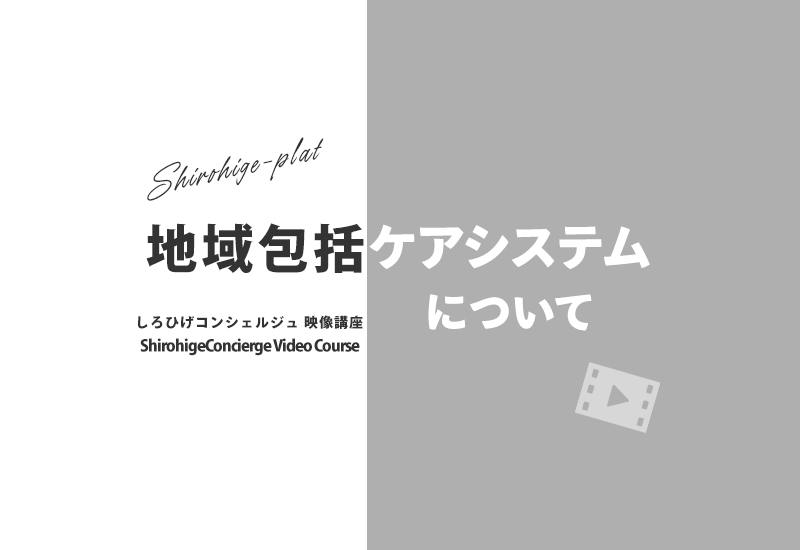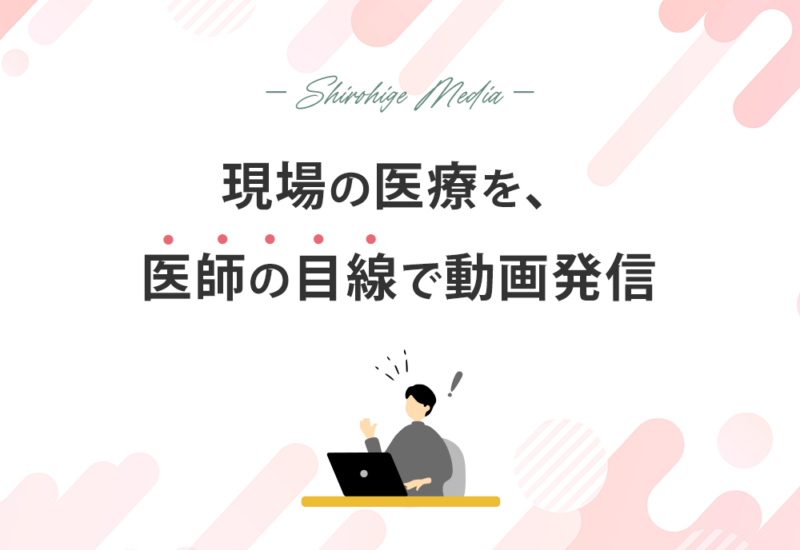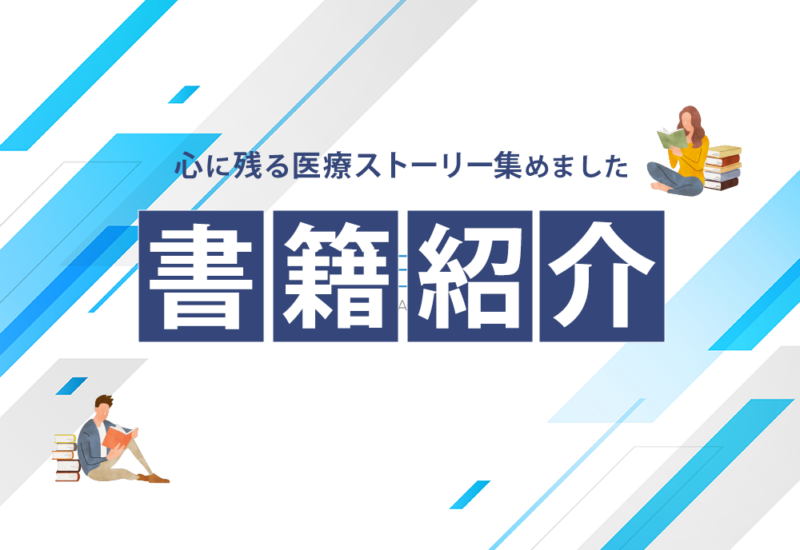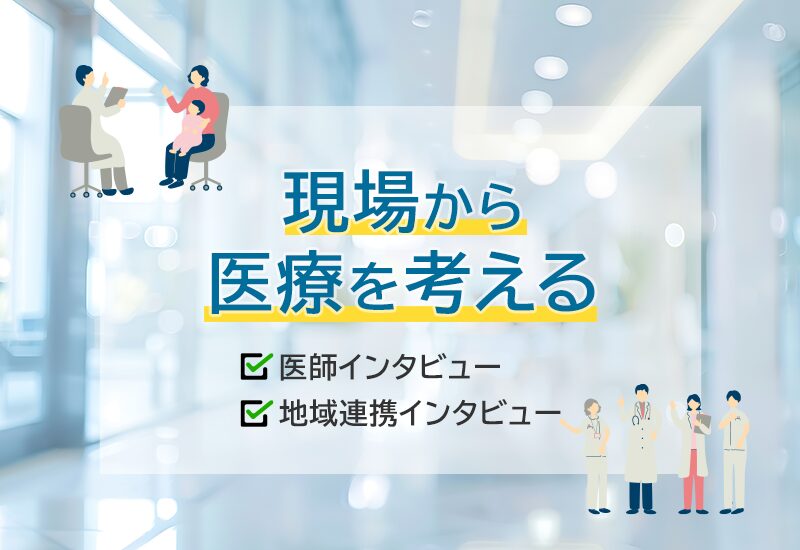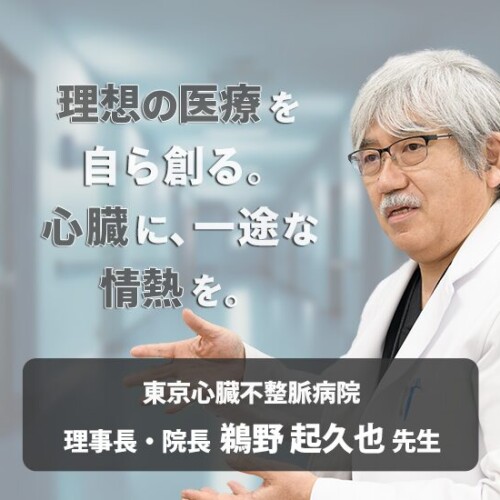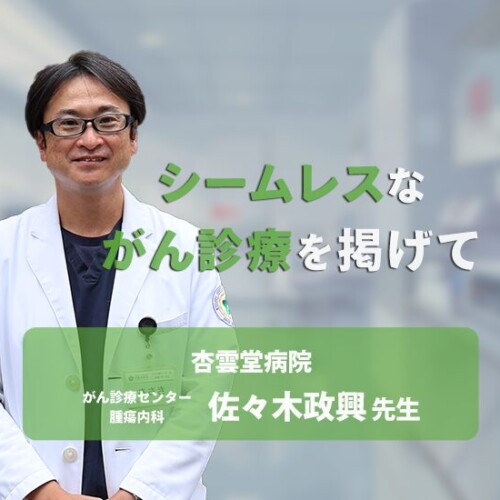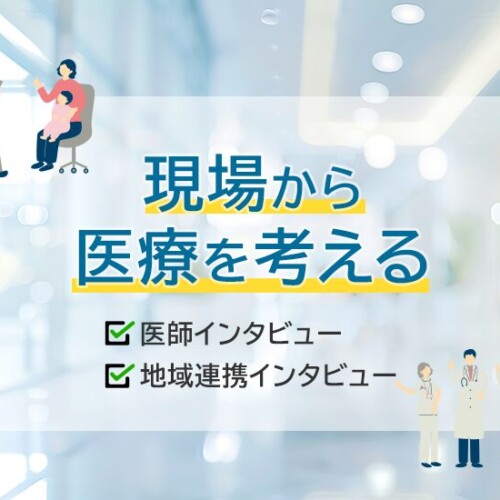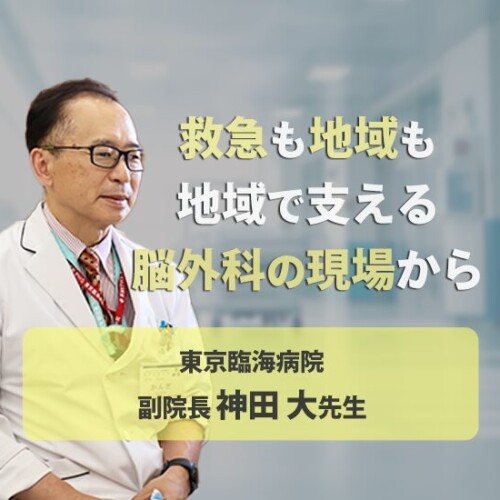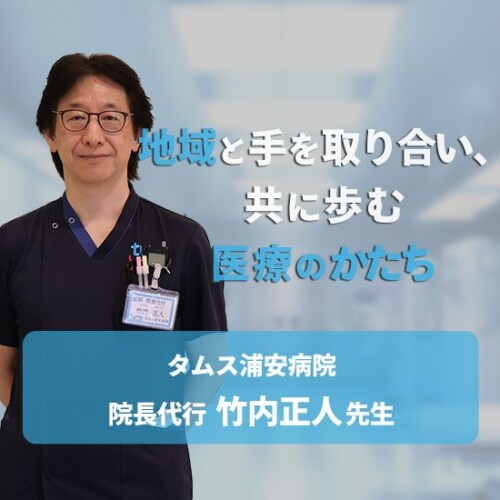現場で学び、地域に届ける。院長が語る在宅医療のかたち
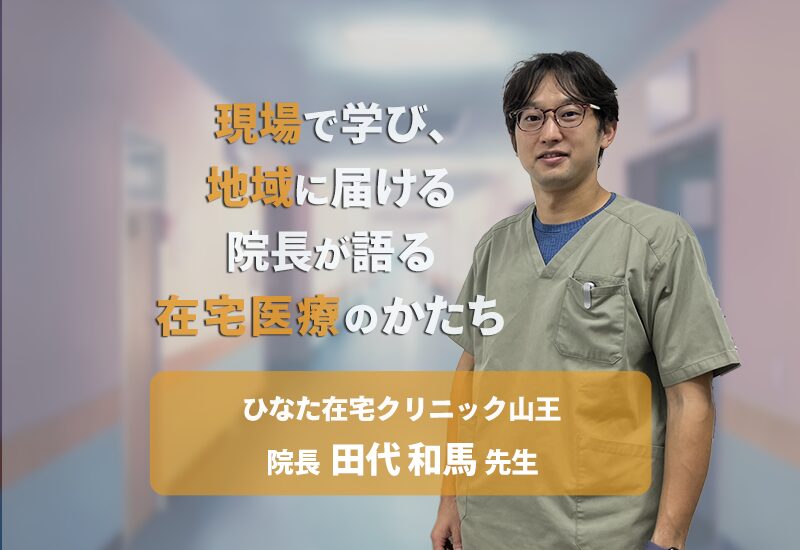
今回、ひなた在宅クリニック 院長 田代 和馬先生にご登場いただき、貴重なお話を伺いました。
-先生のこれまでのキャリアについて教えてください。
私の医師としての歩みは、学業面だけでなく、人間性やリーダーシップの形成にも大きな影響を受けてきました。中高時代は、多様な価値観や背景を持つ仲間たちと過ごすことで、物事を多角的に見る力や協調性を培いました。その後、現役で医学部に進学しましたが、大学に入ると同じような環境や背景の学生が多く、当初は刺激が少ないと感じました。
しかし、清山理事長の講義に出会ったことで、医師としてだけでなく、社会課題の解決や組織運営における考え方に触れ、強い興味を持つようになりました。清山理事長は、東大卒業後に沖縄で医療教育に携わり、地域医療や離島医療の課題解決に取り組まれた方です。こうした経験談を伺い、私も同じような環境で成長したいと考え、沖縄の研修病院に進むことを決めました。沖縄では研修医としてだけでなく、将来的な院長候補として、離島や中山間地域での診療経験を積むことが求められました。
この明確な目標設定があったことで、日々の業務や患者対応が単なる作業ではなく、成長や学びに直結していると実感できました。救急医療や在宅医療の現場で、多くの困難な症例や社会課題に直面する中で、医師としての基礎力だけでなく、判断力や柔軟性、チームマネジメント力も磨かれる非常に濃密な経験となりました。
-沖縄での経験を経て、東京で開業しようと思った背景は何ですか。
沖縄での研修を通して、医療現場では単に病気を治すだけでなく、社会的課題や患者の生活環境に寄り添うことが重要であると痛感しました。特に、生活保護世帯や認知症の患者さん、高齢で支援が必要な方々が急性期病院のベッドを圧迫している現状は、大きな社会的課題でした。
沖縄では先輩医師たちが既存の医療システムで対応を試みていましたが、十分に解決できず、東京という大都市で新たな挑戦をする必要性を感じました。東京・大田区は高齢化が進み、病院依存が強い地域ですが、沖縄で得た経験や理念を応用することで、より多くの患者さんに責任ある在宅医療を届けることができると考えました。
2018年に開業を決意し、ゼロから患者さんや地域の医療関係者との信頼関係を築き上げ、少しずつ地域に必要とされるクリニックとして認知されるようになりました。困難な症例や複雑な社会背景を持つ患者さんに対しても、「まず受け入れる」という姿勢を貫くことで、地域全体の医療の質向上に寄与できる環境を作り上げてきました。

-「断らない医療」を実現するための取り組みについて教えてください。
私が沖縄で研修した病院では、患者さんを断らないことが理念として徹底されていました。この経験から、困難なケースであってもまず受け入れ、考えながら対応する姿勢が自然と身につきました。東京でのクリニック開業後も、この理念はそのまま引き継がれています。
看護師や医師、事務スタッフ全員が「断らずに対応する」という共通の価値観を持ち、複雑な症例や社会的に課題のある患者さんにも柔軟に対応できる体制を整えています。例えば、精神疾患や複数の慢性疾患を抱える患者さんで、通常の在宅医療では対応が難しいケースでも、内科医が中心となって多職種と連携し、最適なケアプランを組むことで、患者さんと家族が安心できる医療を提供しています。
地域のケアマネージャーや病院からも、こうした姿勢が評価され、紹介患者が増えてきました。このように、「断らない医療」を理念として徹底することで、社会的に困難な状況にある方々に寄り添い、地域全体の医療資源の有効活用にもつなげています。
-経営者として、またプレイヤーとして重要視していることは何ですか。
経営者として最も重視しているのは、職員が安心して働きながら自己成長を実感できる環境を整えることです。医療現場は日々困難な判断を迫られますが、スタッフが理念に基づき正しい行動を選択できるよう、明確な方針やサポート体制を提供しています。
また、給与やボーナスなど待遇面の公正さも重視し、職員のモチベーションや組織への信頼感を維持しています。一方で、プレイヤーとしては「属人化しない医療体制」を意識しており、特定の患者が院長に依存することなく、チーム全員で医療を提供できる仕組みを作っています。
私自身も現場に入ることで、初期対応や判断が難しいケースのサポートを行い、職員や患者さんに安心感を提供しています。経営者としての統括力と現場でのプレイヤーとしての即応力を両立させることで、理念に沿った質の高い医療サービスを安定して提供することを心がけています。
- ドクターや看護師の育成について、どのような取り組みをされていますか。
ドクターの育成では、まず現場での密着研修を通して、病院に頼らず患者さんを主体的に診る姿勢を体感してもらいます。初期対応から判断のプロセスまで、日々の業務で生じた疑問や課題に対してフィードバックを行い、理念に沿った行動が自然とできるよう指導します。
看護師については、経験豊富なコアメンバーが中心となり、過去の事例や理念に基づいた対応方法を伝え、実践を通じて学んでもらいます。医療事務やドライバーなども、個々の適性やリーダーシップを見極めつつ権限を委譲し、チーム全体が自律的に動ける体制を作っています。これにより、組織全体として理念が浸透しつつ、専門性を維持した医療サービスの提供が可能になっています。
教育は単なる知識伝達ではなく、現場での実践力と理念理解を重視することで、スタッフ一人ひとりが自信を持って働ける環境を整えています。

-今後の展望をお聞かせください。
私が目指すのは、単にクリニックの規模を拡大することではなく、提供する医療の質をより多くの地域住民に届けることです。具体的には、自分が受けたいと思えるような責任ある在宅医療を、地域全体に広めることが目標です。
そのためには、理念を共有する志の高い医師や医療従事者を巻き込み、同じ価値観で医療を提供するネットワークを形成することが重要です。また、診療だけでなく、教育や地域への啓蒙活動、行政や他医療機関との連携も強化し、在宅医療のモデルを地域全体に広く伝えていくことを意識しています。
将来的には、困難な症例や多職種連携が必要なケースにも対応できる体制をさらに整え、地域住民が安心して生活できる医療環境の構築に貢献していきたいと考えています。理念に基づいた医療提供を軸に、質の高い在宅医療を持続可能な形で広げていくことが、私の長期的な展望です。