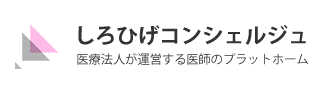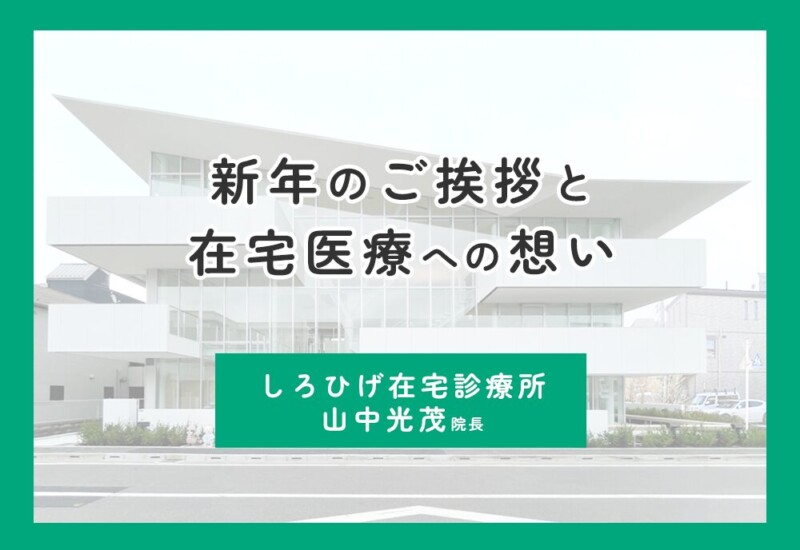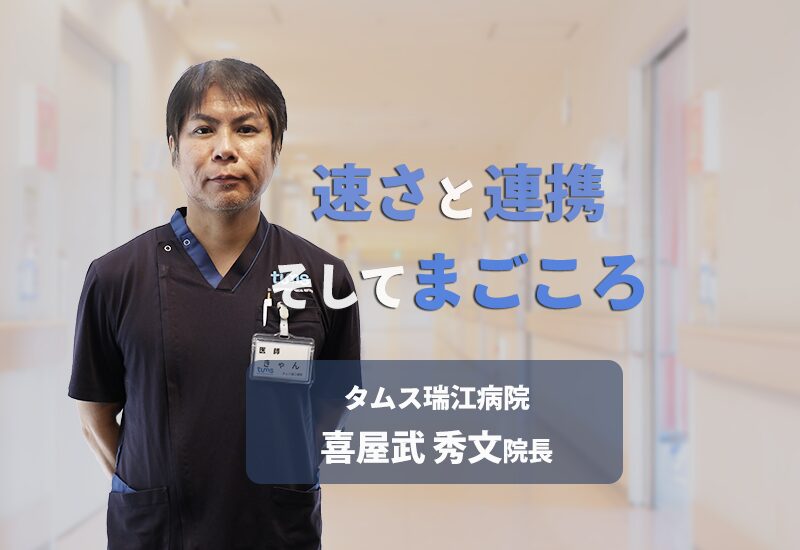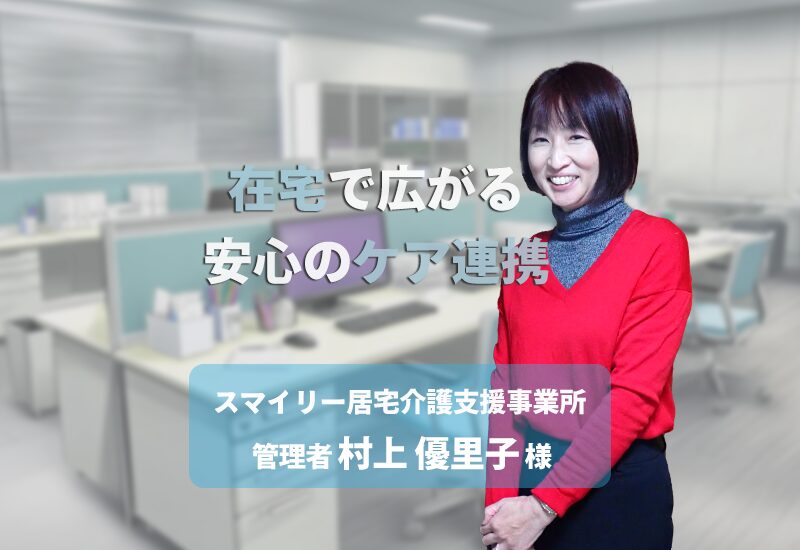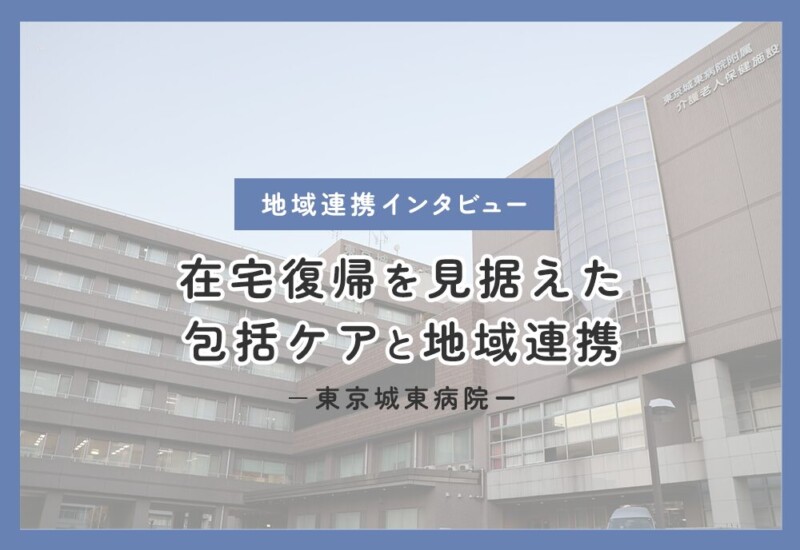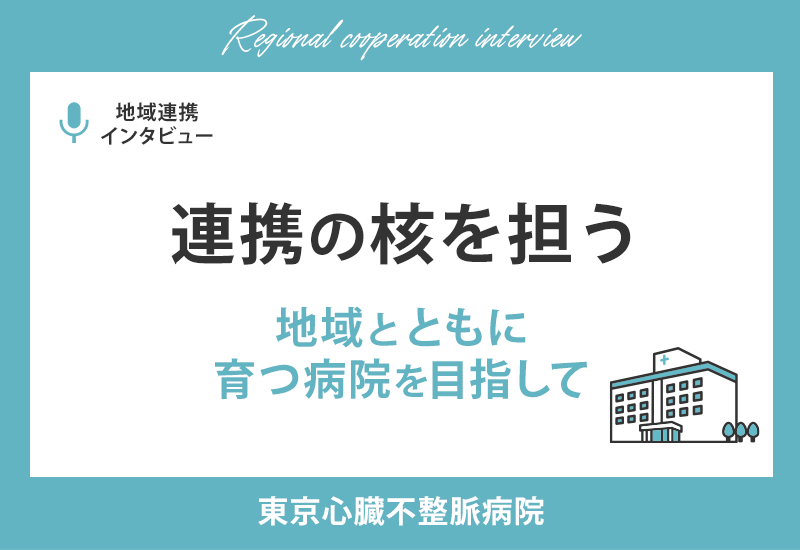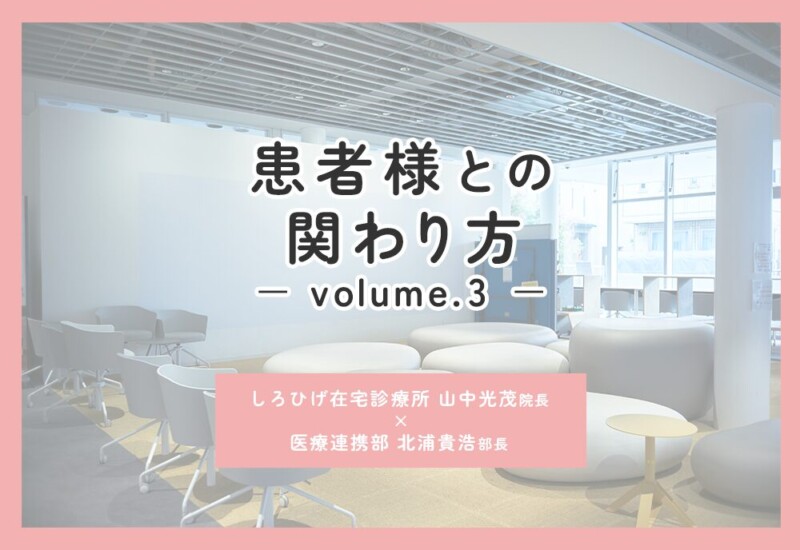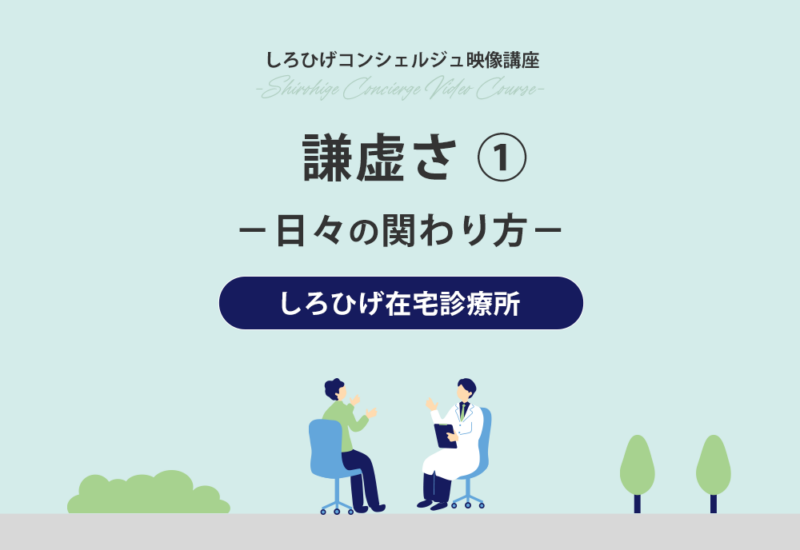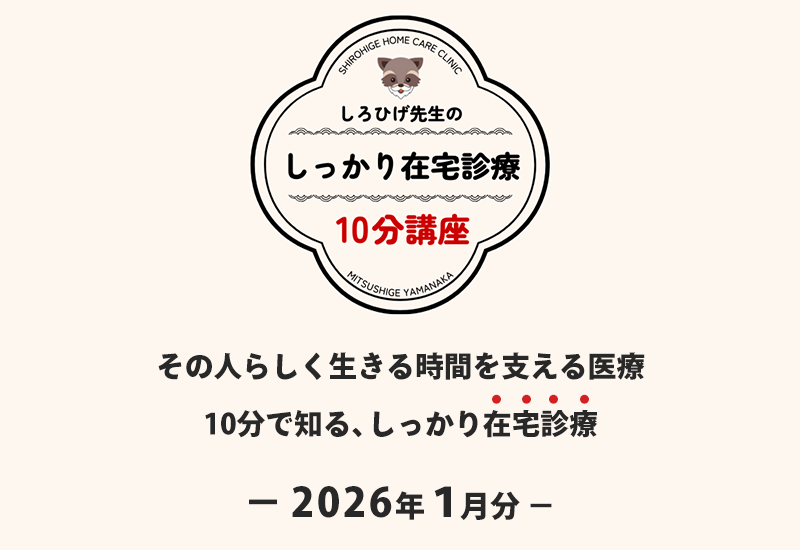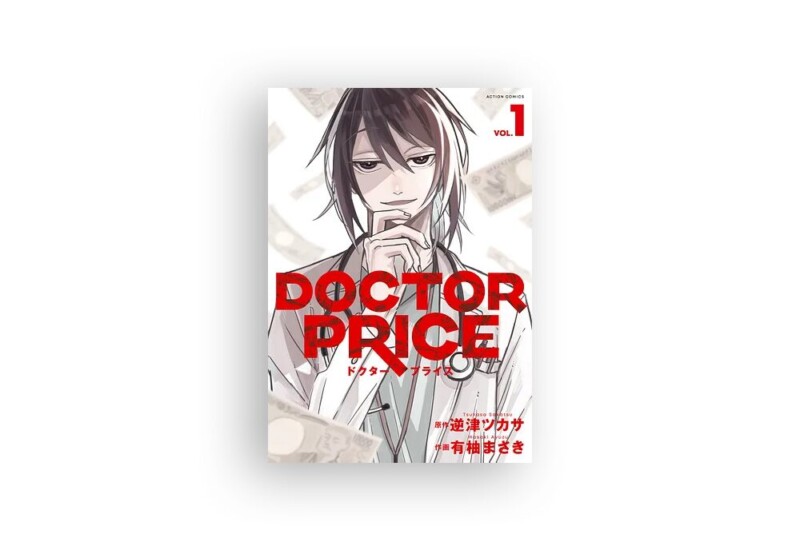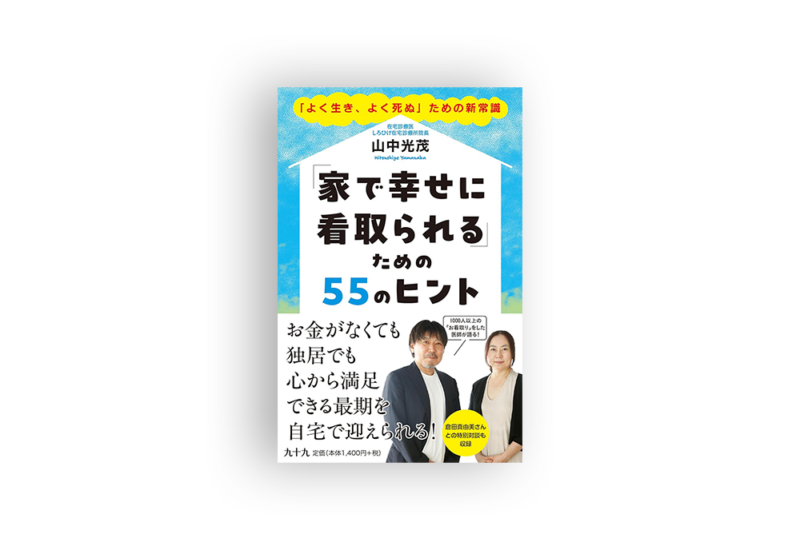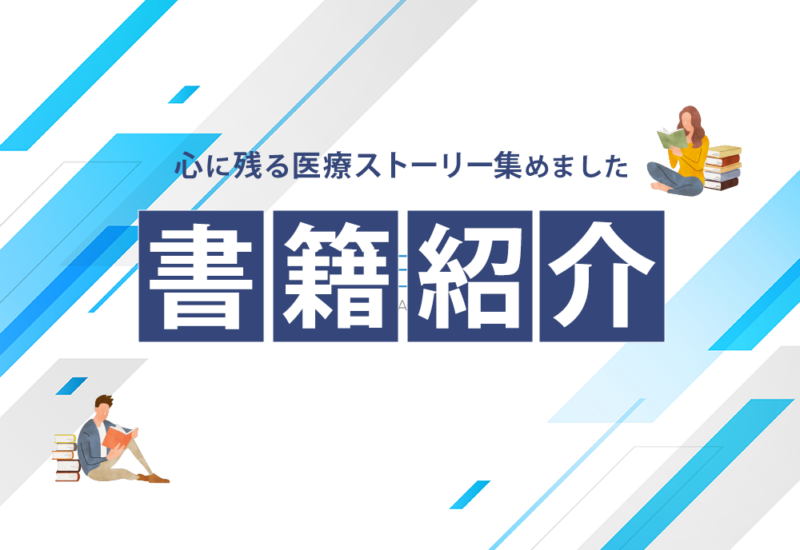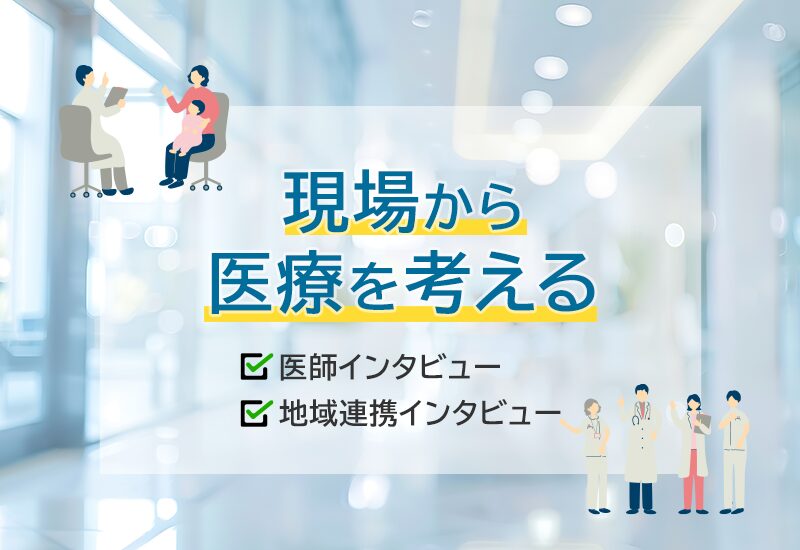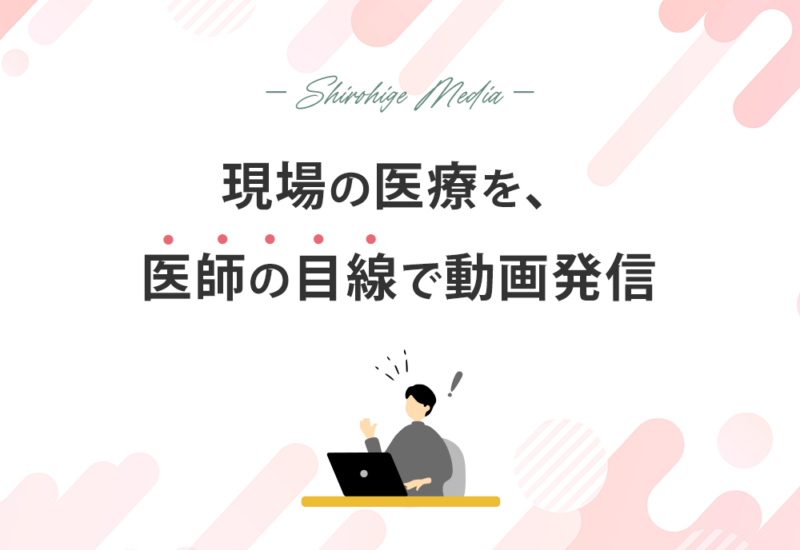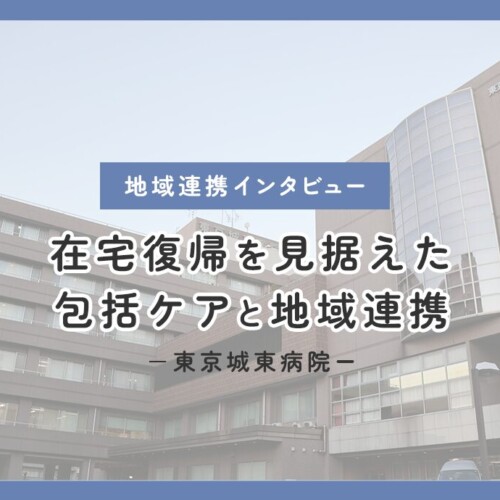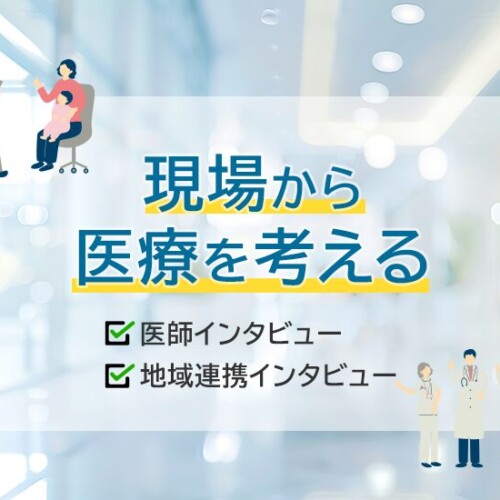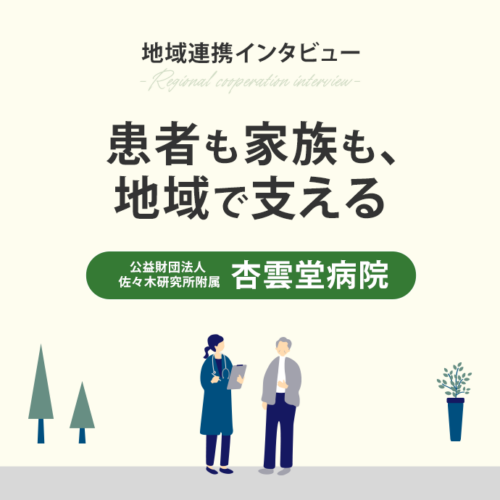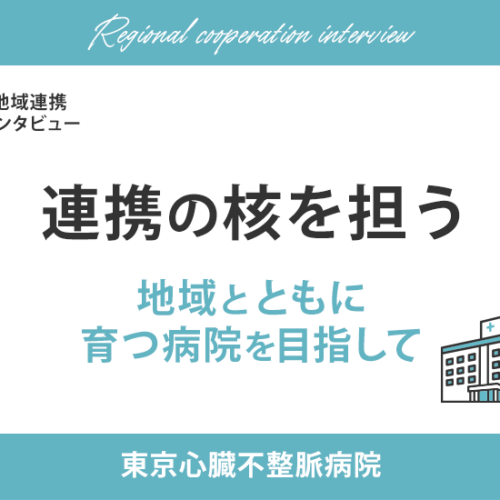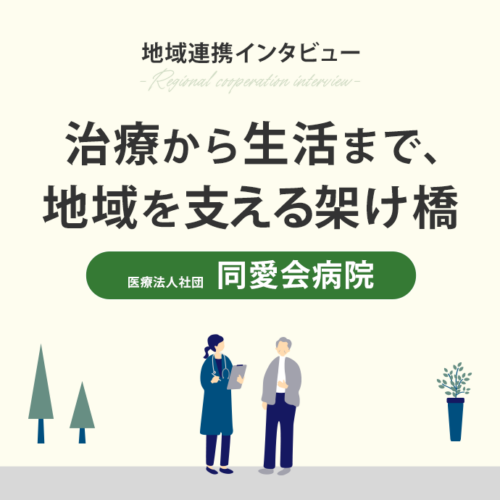地域とともに歩む医療をめざして
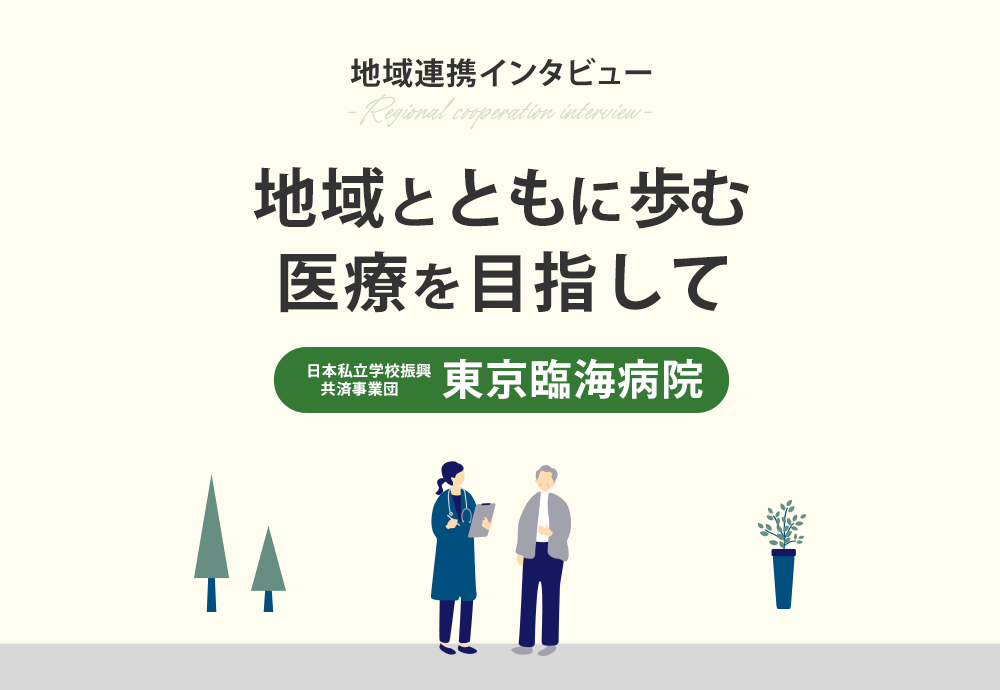
今回のインタビューでは、東京臨海病院 患者サポート室 地域医療連携・入退院支援センター 泉水 茜 様、地域医療連携・入退院支援センター 川口 千愛 様に、地域連携の取り組みについてお話を伺いました。
-地域連携を行う上で関わっている職種や役割について教えてください。
当院では「地域医療連携入退院支援センター」が中心となり、前方連携は地域医療連携室、後方連携は入退院支援センターとして動いています。前方連携は事務が5名、後方連携は看護師が7名、相談室にはソーシャルワーカーが5名在籍しています。入退院支援室の看護師と相談室のソーシャルワーカーが連携し、患者さんの入院前から退院後までのサポートを行っています。
-事務の方の具体的な業務内容はどのようなものですか?
事務は患者さんの紹介受診の予約対応、問い合わせ対応、急性期同士での転員調整や紹介医療機関との調整を行っています。また、カルテ共有システム「臨海ネット」の受付や登録作業、かかりつけ医が不在の患者さんへの対応、地域の医療機関からの紹介に対しての当院からの返書の発送や管理など、多岐に渡る連携業務を担当しています。

- 相談室との連携について教えてください。
相談室では、身寄りが誰もいない患者さんや生活上の課題が複雑な方、無保険の方など、地域の福祉制度を深く活用する必要があるケースをソーシャルワーカーが中心に対応しています。入退院支援室の看護師と連絡を取りながら、患者さんの状況に応じて担当を振り分けています。
- 医師との院内連携はどのように行っていますか?
治療方針がとても大事な部署なので、医師から患者さんの状況に関する電話連絡を受けたり、逆にリハビリスタッフから歩行能力の変化などの情報を医師に伝えるなど、必要な情報共有を行っています。電話連絡が中心ですが、患者対応や治療に関わる意思決定に関して連携を密にしています。

-外部連携ではどのような取り組みをしていますか?
外部連携では近隣の診療所や、他の高度急性期病院、訪問看護事業所などを訪問し、顔の見える関係づくりを大切にしています。電話だけでなく直接会うことで情報共有や相談がしやすくなるため、定期的に訪問を行っています。また、地域医療支援病院として年12回以上の医療従事者向け講演会を企画し、医師・看護師・薬剤師・放射線技師など地域の幅広い職種に参加してもらっています。コロナ禍以降基本的にはウェブ中心ですが、年に1回は必ず対面での情報交換会を開催しています。
-地域連携における今後の課題や展望はありますか?
江戸川区内で在宅医療と救急病院を結ぶネットワークがまだ整っていないため、地域医師会と連携し今後の関係構築を計画しています。地域からの急変時の要請にも迅速に対応できる体制を整えていきたいと考えています。また、病院として地域に積極的に働きかけ、医療関係者や住民への発信を強化することも今後の展望の一つです。

-病院としての地域連携の強化について
事務スタッフの育成は以前2名だったところを5名まで増員し、営業訪問や地域連携活動に参加できる体制を整えています。副院長や看護部長も同行し、現場での実践を通じて関係性を密にし、スタッフが適切に対応できるよう支援しています。顔の見える関係作りを重視し、地域医療機関との信頼関係を構築することが重要と考えています。