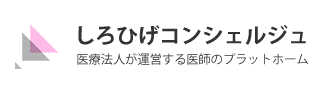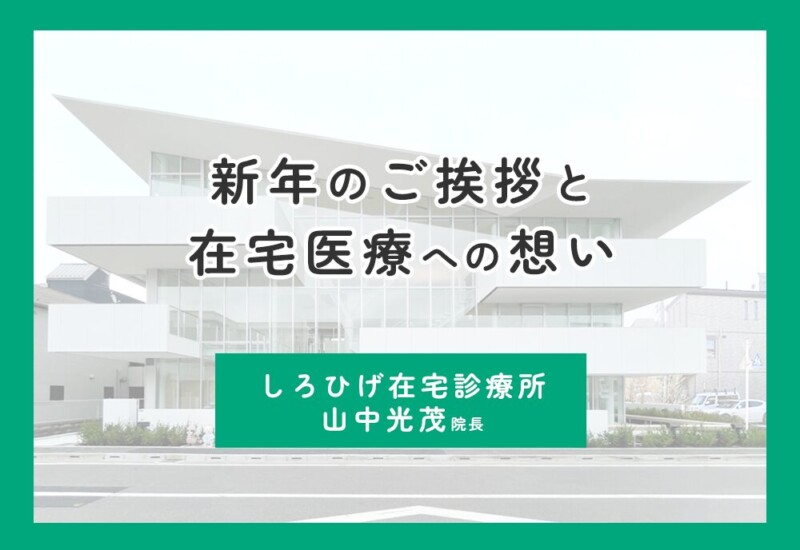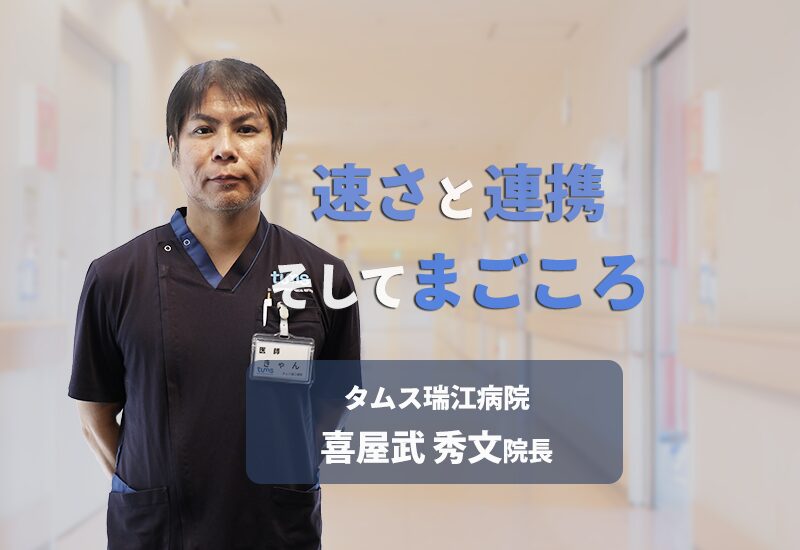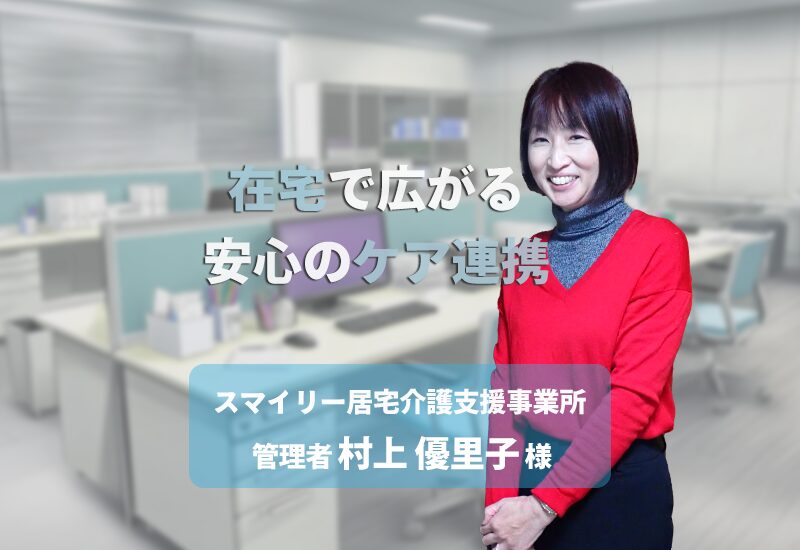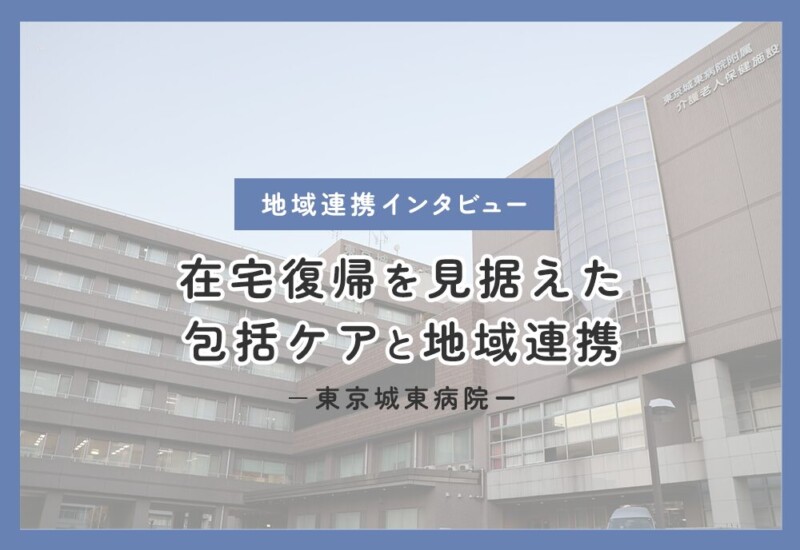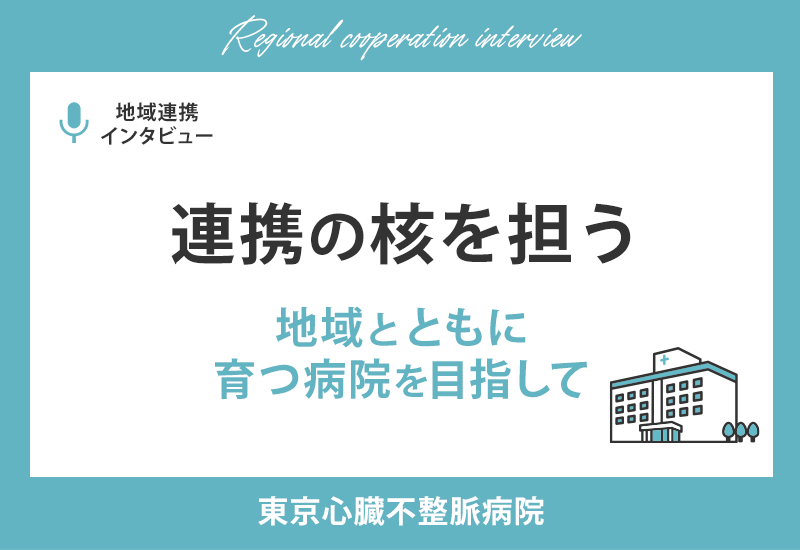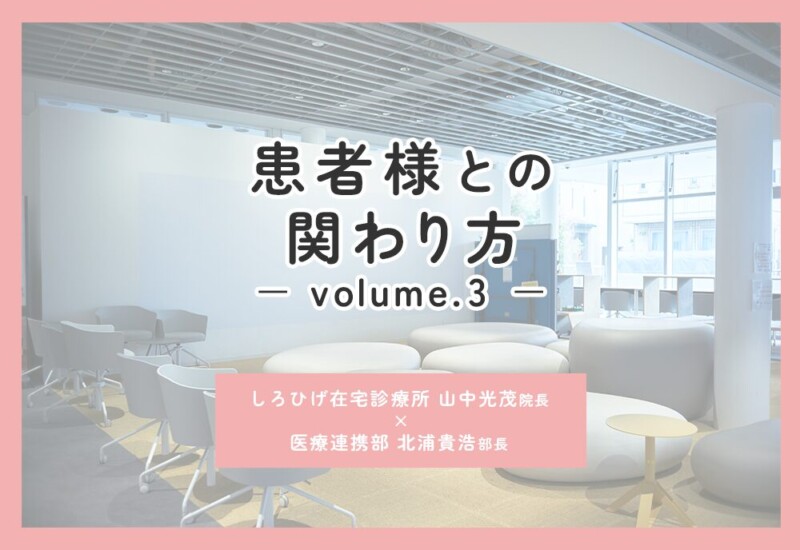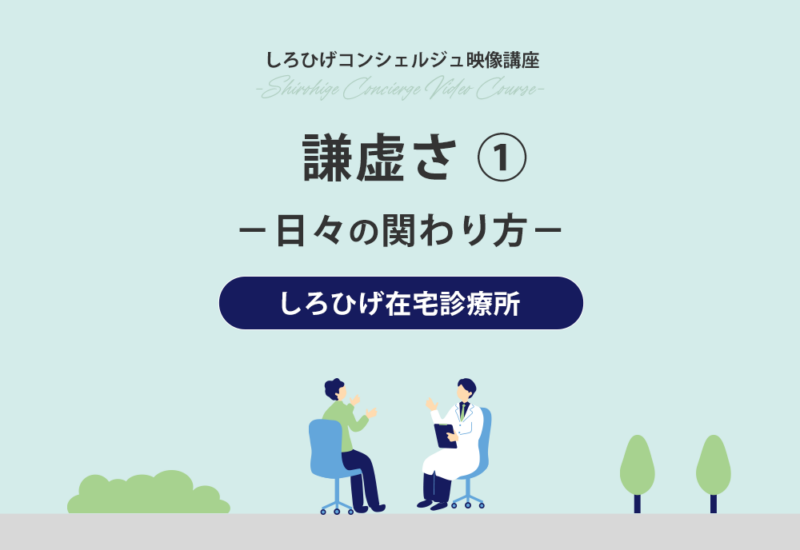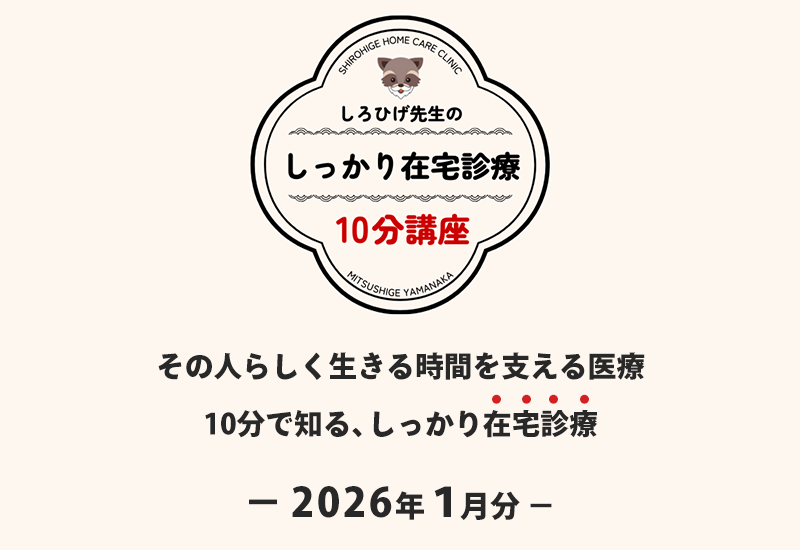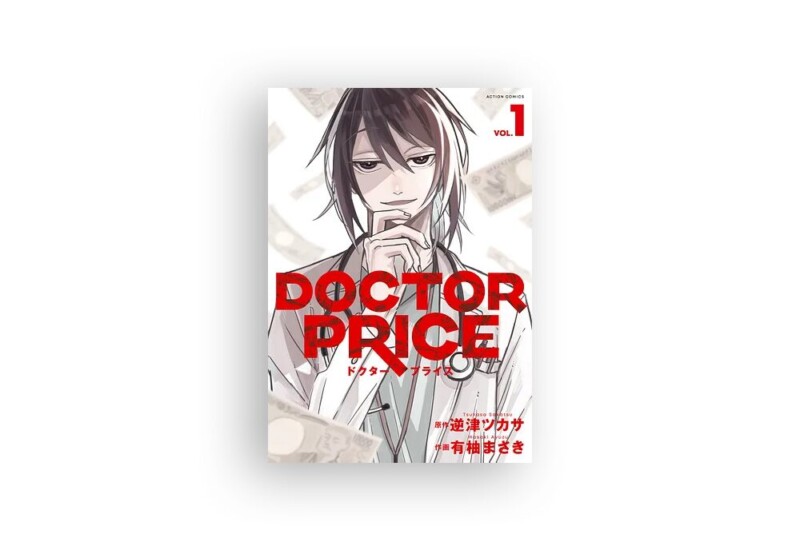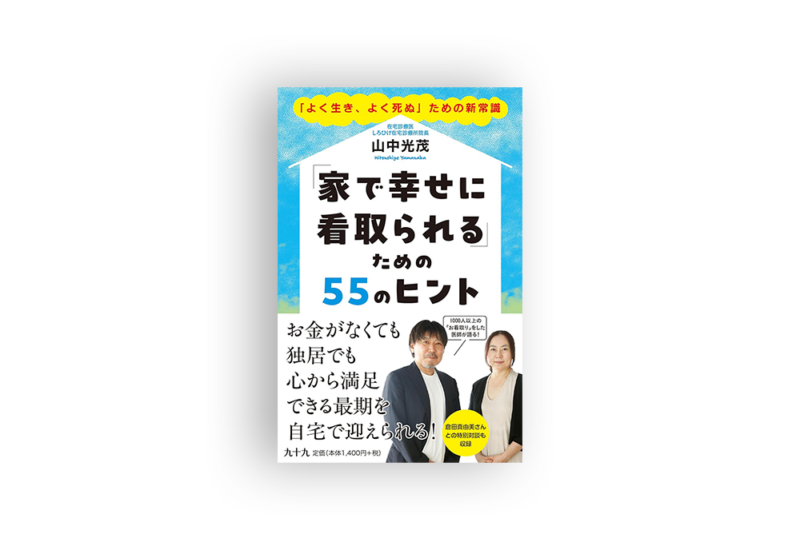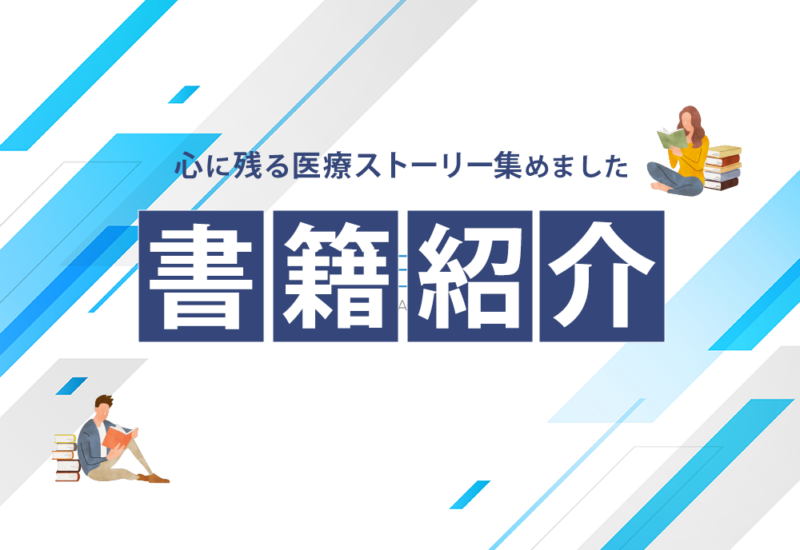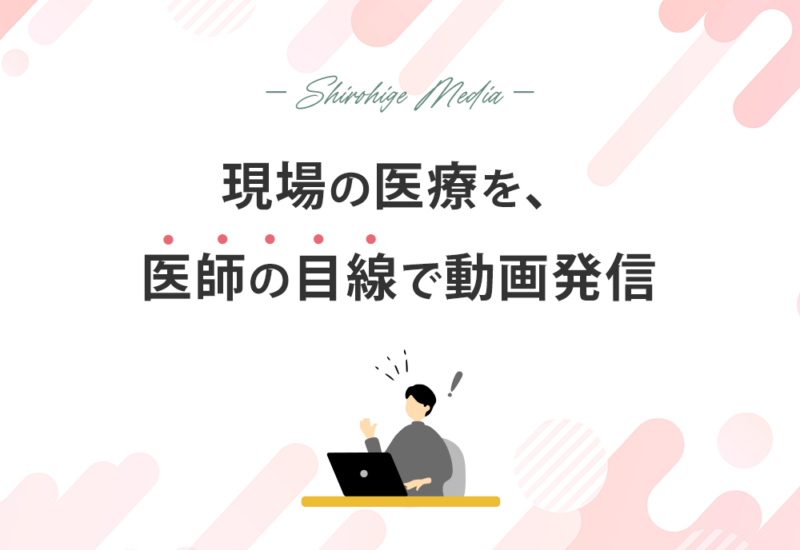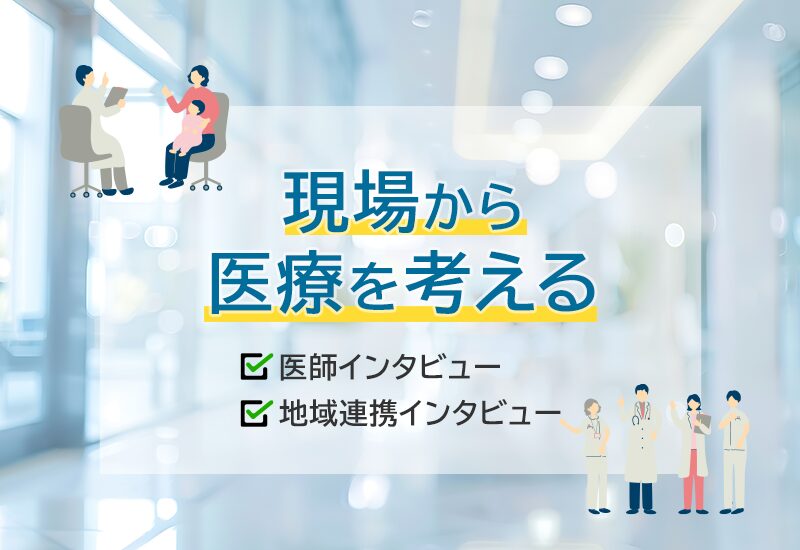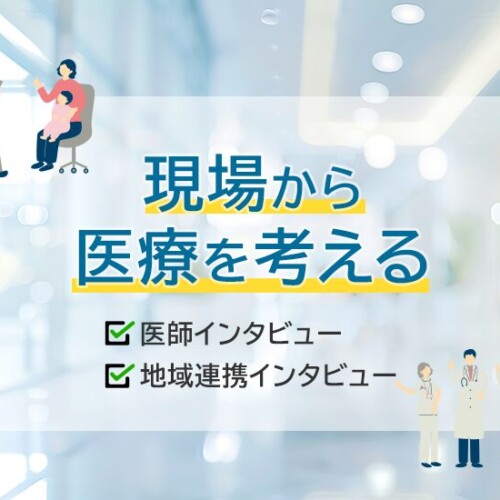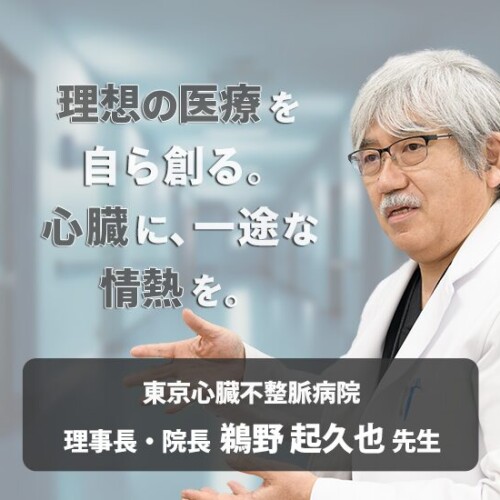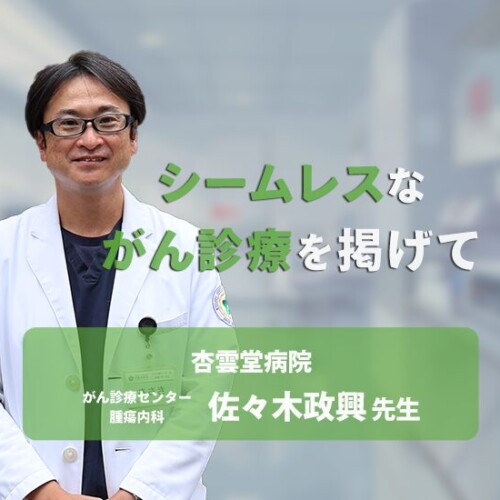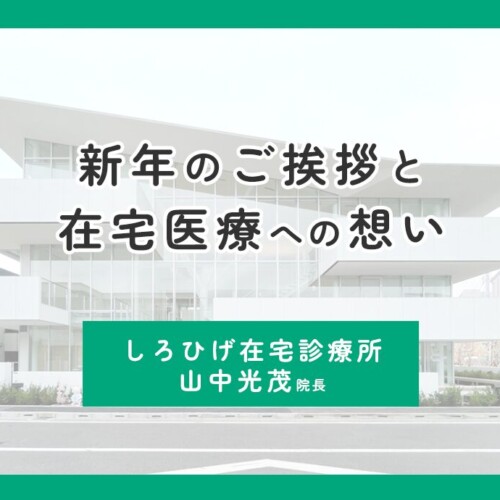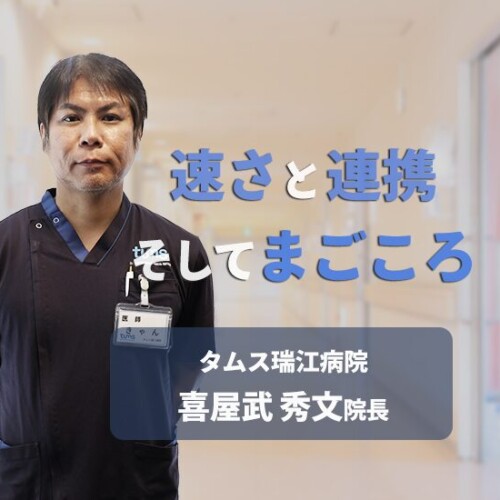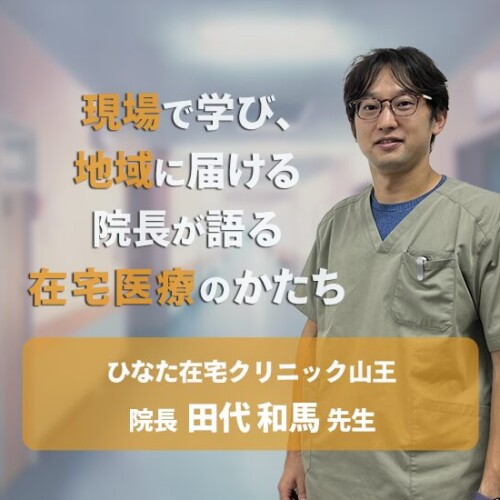医療をこえて、人生に寄り添う

今回、桜新町アーバンクリニック 院長でいらっしゃる遠矢 純一郎先生にご登場いただき、貴重なお話を伺いました。
-先生が在宅医療に関わるきっかけは何でしたか?
もともと私は呼吸器科が専門ですが、実は大学を卒業して医局に入ったときは、神経内科をやっていました。大学時代、第三内科というところに所属しており、そこは神経内科や血液内科、呼吸器内科など「他の科がやらない分野」を扱う科でした。研修医として担当した最初の患者さんはALSの方で、10年間大学病院に入院されていました。そこで「なぜ退院できないのか」を考えたとき、家での支援体制がないことに気づき、先輩と相談して大学病院初の在宅往診の仕組みを作り、患者さんを自宅に帰すことができました。振り返ってみると、最初の患者さんが、自宅での生活に戻すことの難しさを教えてくれたように思います。
- 研修医時代の経験で特に印象に残った患者さんについて教えてください。
40代の末期がんの患者さんが非常に印象的でした。その方は肺に転移のある進行がんで酸素吸入や緩和ケアが必要でしたが、「自宅に帰りたい」と強く希望されました。最初は無理だと考えていましたが、病院と調整し、酸素ボンベを積み込んで自宅に帰宅させました。ご自宅では10歳くらいの娘さんに味噌汁の作り方を教える場面があり、患者さんは「娘に自分の存在を残したい」という気持ちでその行動をしていたことがわかり、医療者として寄り添うことの大切さを深く実感しました。たとえ不治の病で命が限られた患者さんでも希望を持つことができること、そこに寄り添い、支援することも医療の役割であることを教えられました。
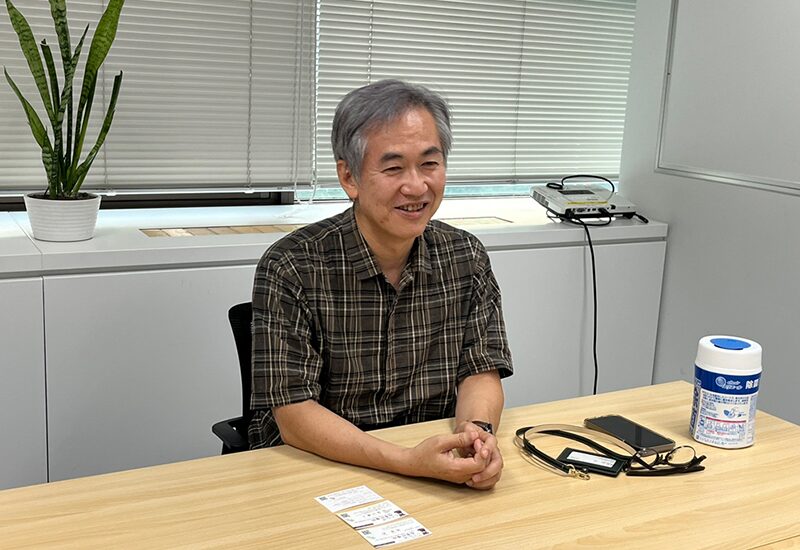
-在宅医療に移行する過程で、どのような経緯で現在の事業を始められたのですか?
先輩が訪問医療で開業することを聞き、手伝う形で関わり始めました。1998年頃から徐々に訪問診療を始め、患者さんの紹介が増える中で、医師と看護師のペア体制を構築していきました。スタッフたちが「こうしたい」「ああしたい」と希望することを実現していく中で、自然と訪問看護ステーションや認知症ケアセンターなど、事業が広がっていきました。私のトップダウンで広げたわけではなく、現場スタッフのアイディアややってみたいを叶える場をボトムアップ的にみんなで作った、という形です。
-現在の法人での多職種連携や地域との関わり方について教えてください。
私たちは訪問診療を中心に、外来や地域支援、介護サービスなども含めて患者さんを支えています。特に認知症在宅生活サポートセンターでは、本人の早期支援や進行時の困難支援、家族教育や啓蒙活動を行っています。また、地域食堂などのコミュニティ活動も展開しており、患者さんや地域住民が集う場を提供しています。在宅医療に取り組む中で、徐々に医療だけでは支えられないことがわかり、ケアとの連携や地域づくりにまで広がっていきました。
-認知症在宅生活サポートセンターの役割は何ですか?
認知症の方ができるだけ自宅で暮らせるよう支援することが中心です。具体的には、早期診断後の本人支援、進行後のBPSD(行動・心理症状)への対応、家族の支援や教育活動を行っています。本人や家族が安心して暮らせる環境を作ること、また地域社会全体で認知症に対する理解を深める啓蒙活動も行っています。こうした活動を通じて、認知症の方やその家族が生き生きと暮らせる社会づくりを目指しています。

-看護小規模多機能施設の役割と課題について教えてください。
以前、法人として有床診療所を持っていましたが、コスト面や利用状況から閉鎖しました。その代わり、看多機では看護師が常駐し医療的対応が可能な環境で、在宅患者が一時的に通う・泊まることができる多機能型施設として活用しています。まだ比較的新しいサービスということもあり、運営面、経営面では苦労が多いですが、利用されている方にはとても満足度が高いので、より良い運営についてさらにブラッシュアップしていくつもりです。
-法人として今後取り組みたいことはありますか?
医療に強い介護チームを作ることが大きな目標です。地域全体で患者さんの生活を支える仕組みを強化していきたいと考えています。また、認知症や終末期の患者さんができるだけ自宅で安心して暮らせるよう、施設・サービス・地域ネットワークのさらなる拡充も検討しています。