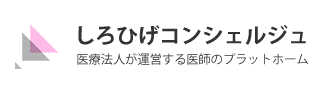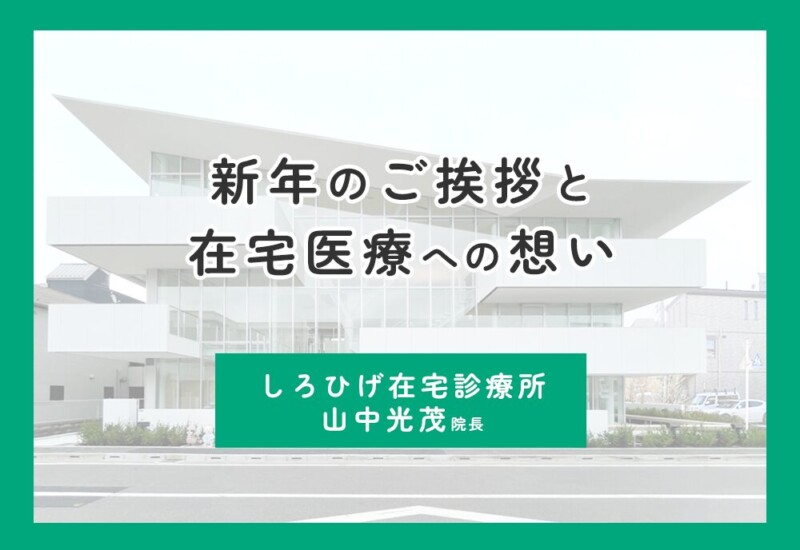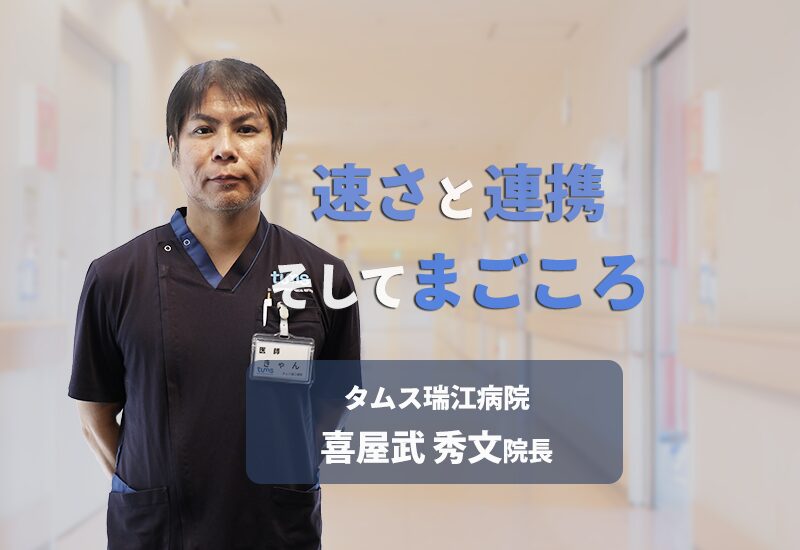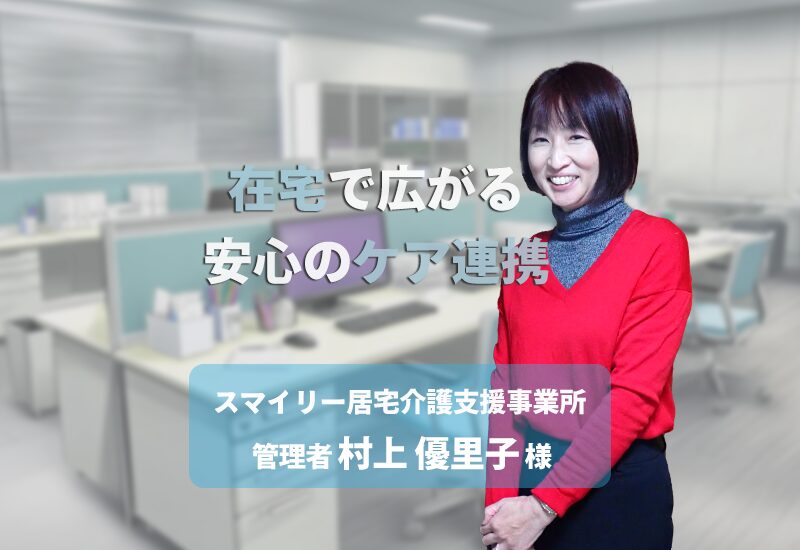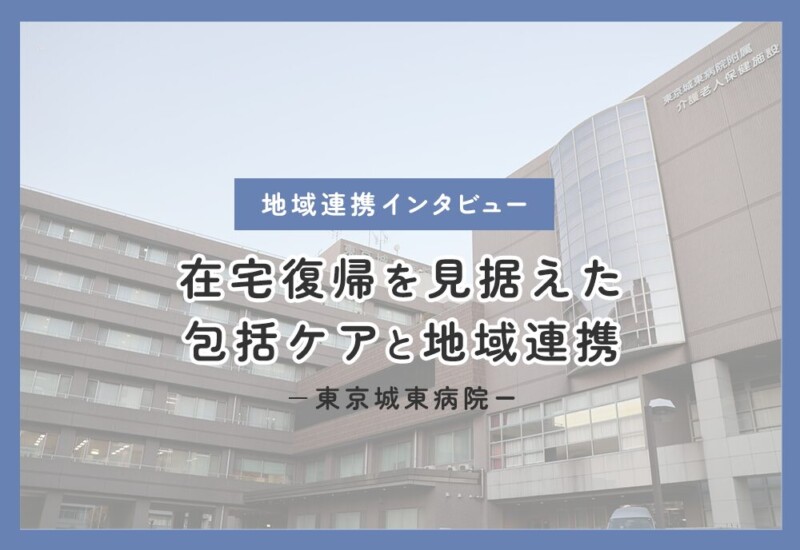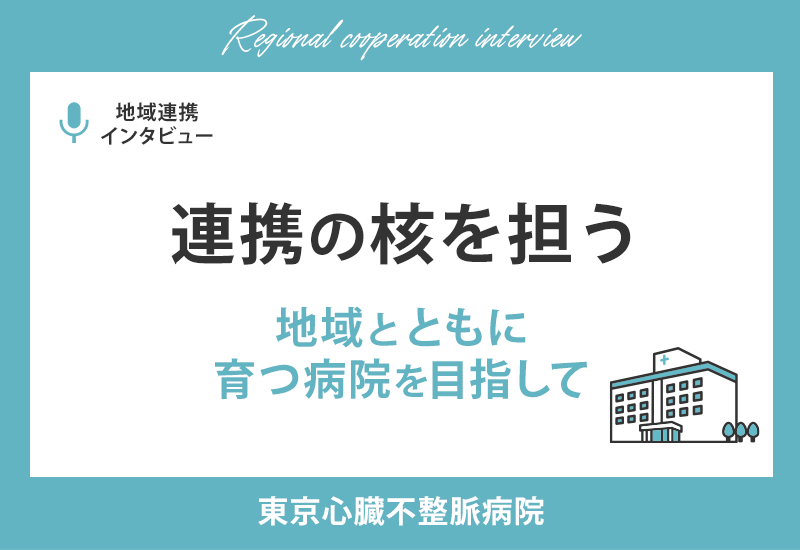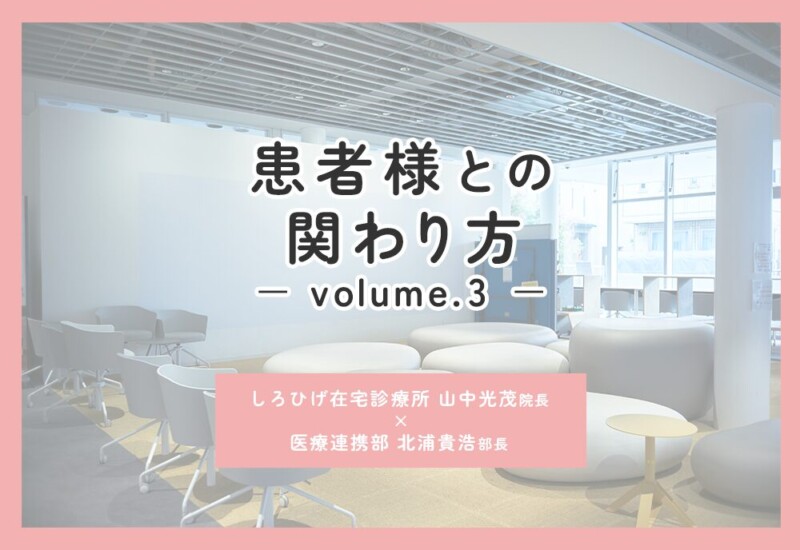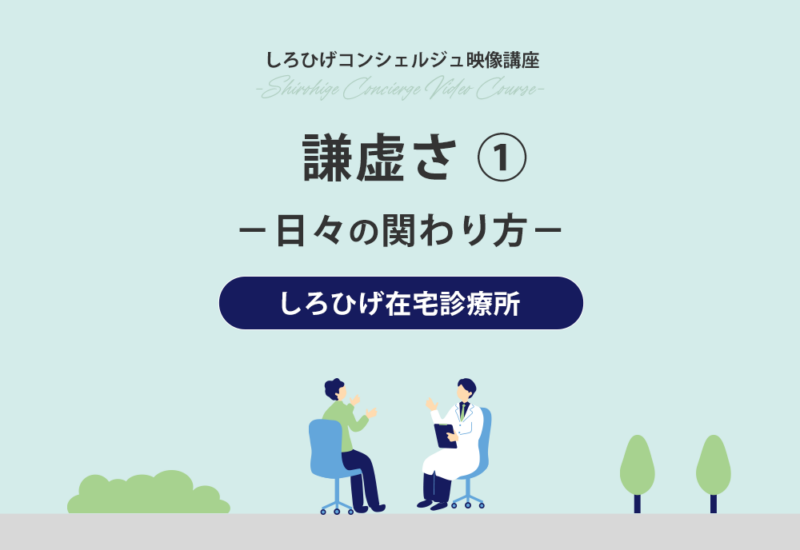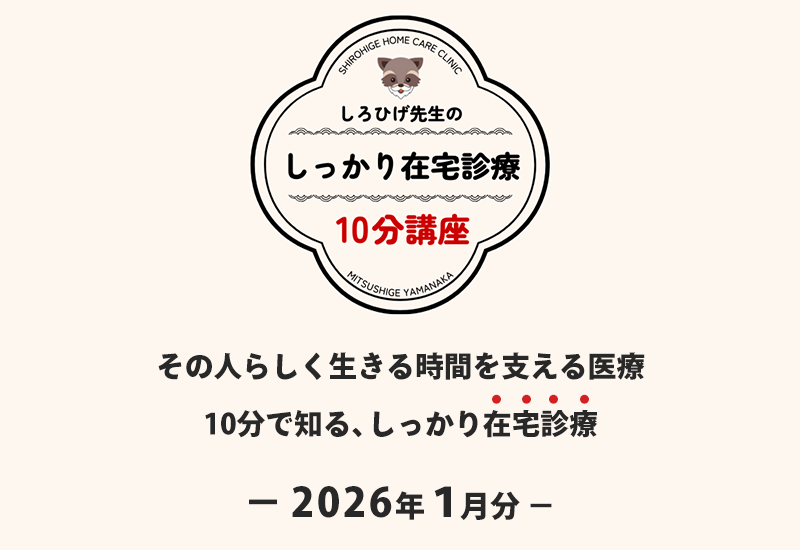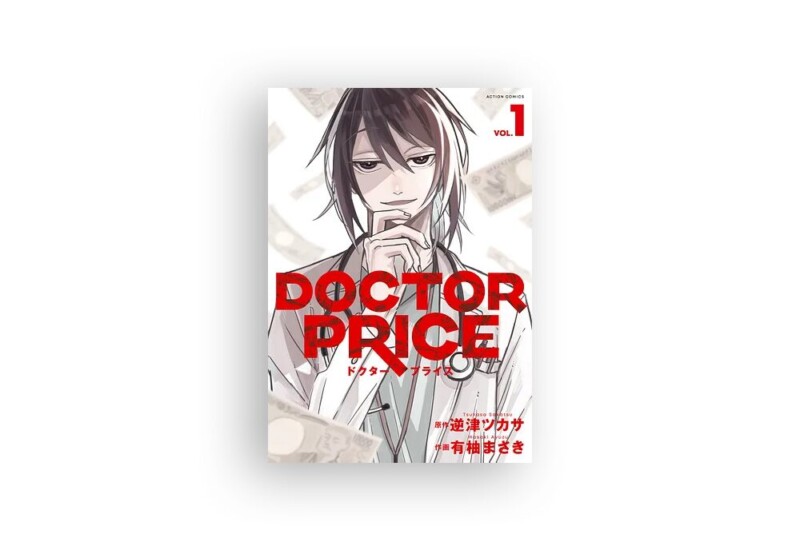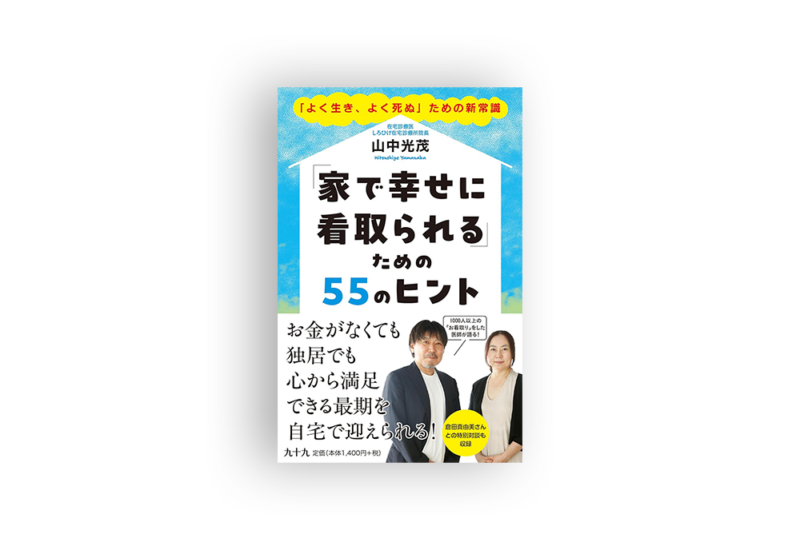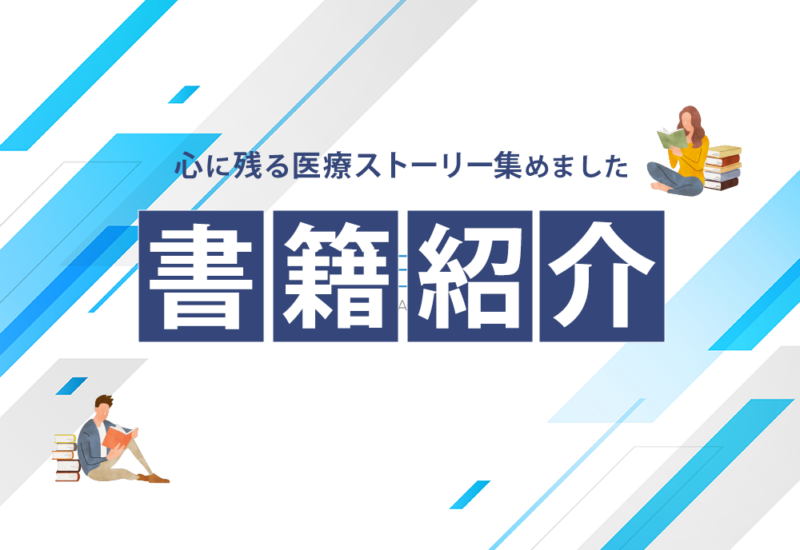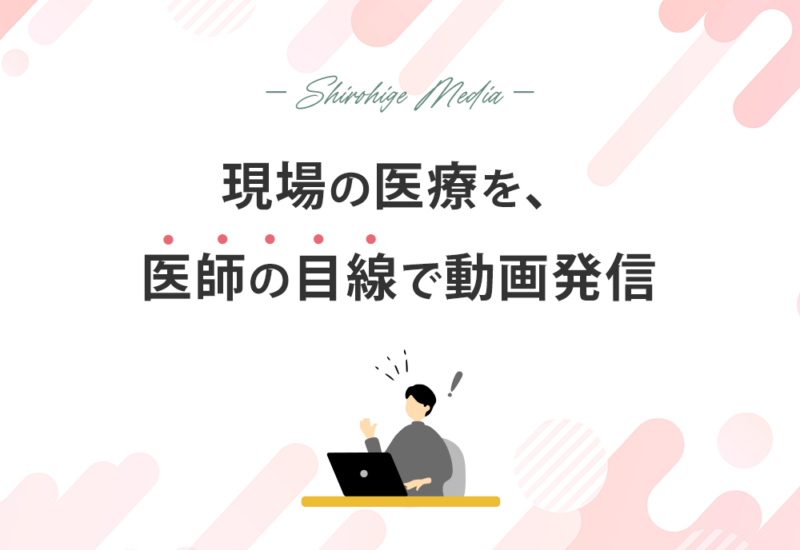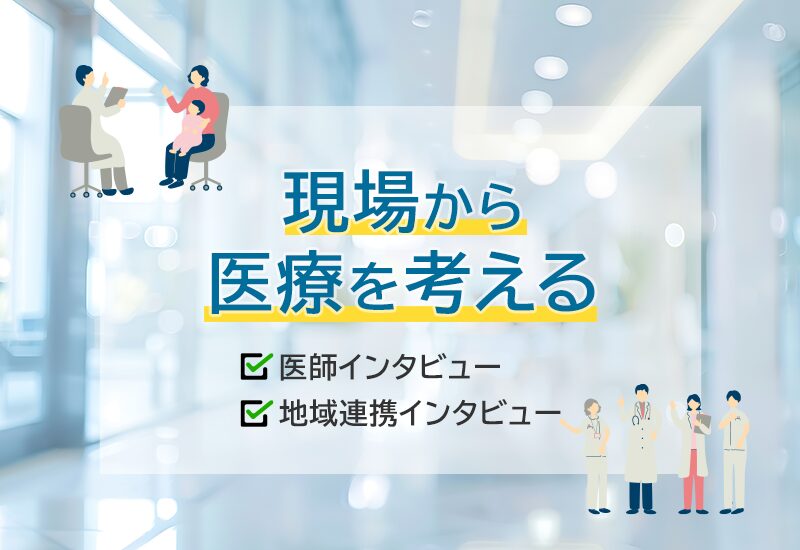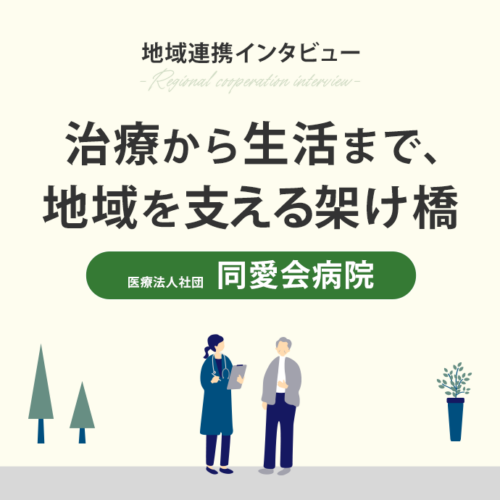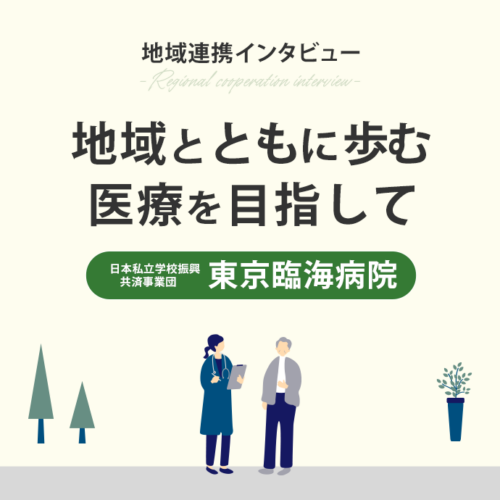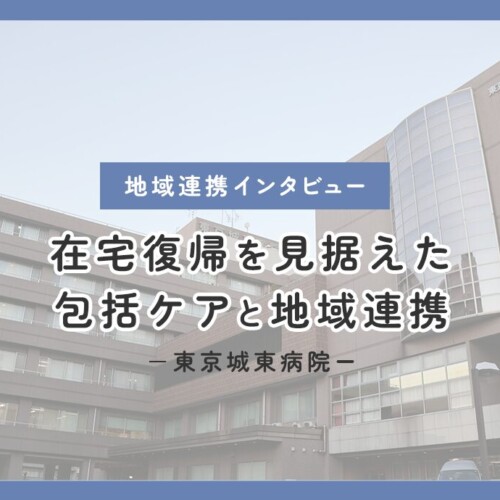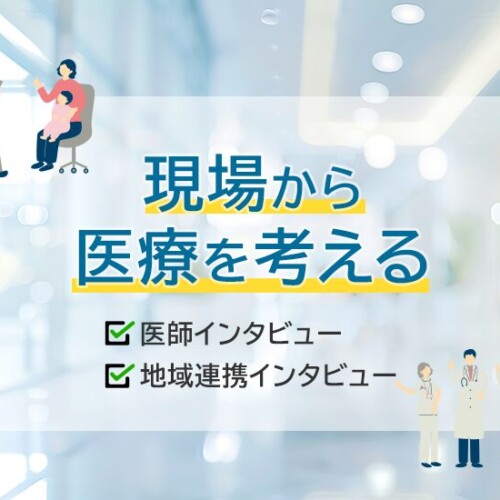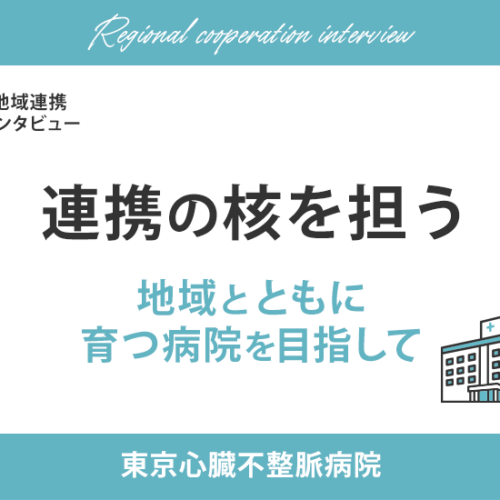患者も家族も、地域で支える杏雲堂病院
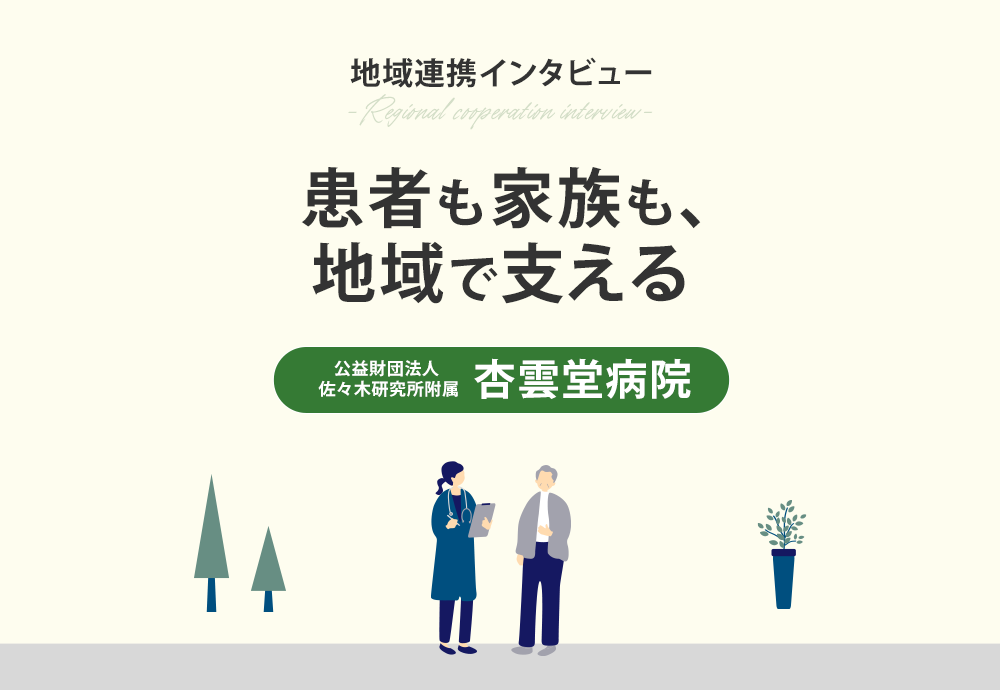
今回のインタビューでは、公益財団法人佐々木研究所附属 杏雲堂病院 患者サポート室 内野 寿則 様、副看護師部長 ・副患者サポート室長 梅内 恵子 様に、地域連携の取り組みについてお話を伺いました。
-杏雲堂病院の概要について教えてください。
1882年6月1日に設立された非常に長い歴史を持つ病院です。創立以来、地域に根差した医療を提供しており、今日まで地域住民の健康を守る役割を担い続けています。
現在の病床数は160床で、急性期病床80床、地域包括ケア病床40床、緩和ケア病床40床という構成になっています。救急指定は一次救急であり、地域住民が安心して受診できる「身近な救急病院」としての機能も果たしています。また、がん診療については診断から治療、そして緩和ケアまでを一貫して担うことが可能であり、患者さんが安心して治療の道筋を描けるような体制を整えています。さらに、近隣にある東京科学大学病院・日本大学病院等との連携も密に行っており、必要に応じて高度医療との橋渡しを行うことで、患者さんにとって切れ目のない医療提供を実現しています。
-地域連携における前方連携と後方連携の役割について教えてください。
地域連携は「前方連携」と「後方連携」に分かれており、それぞれに明確な役割があります。前方連携は、主に外来や入院の受け入れに関する調整を担当し、他院や施設からの入院相談を受け、適切に受け入れが可能かどうかを判断することが中心となります。
一方、後方連携は退院支援に重点を置き、患者さんが退院後に自宅や施設で円滑に生活を続けられるよう、環境調整や関係機関との連絡調整を行います。両者は「患者サポート室」という一つの組織の中で連携しており、センター長である医師のもと、看護師、事務職、ソーシャルワーカーなど多職種が役割を分担しながら協働しています。小規模病院ならではの強として、職種間のやり取りは主にPHSや電話を用いた直接的かつ迅速なコミュニケーションで行われており、患者さんやご家族の希望にスピーディーに対応できる点が特徴です。
-外部医療機関との連携はどのように行われていますか。
外部の医療機関との連携においては、電話とシステム(CARE BOOK:株式会社3Sunny社製)の両方を活用しています。例えば、東京科学大学病院など一部の病院とはCARE BOOKを用いて診療情報提供書を共有し、紹介から受け入れまでの流れをスムーズに行っています。
しかし、実際の現場では、緊急性の高いケースや患者の状態変化に即応する必要がある場面が多く、電話でのやり取りが依然として中心です。特に救急搬送や急な転院調整の際には、ドクター同士が直接電話でやり取りを行い、リアルタイムで正確な情報交換を行うことにより、適切かつ迅速な医療提供につなげています。システムの効率性と電話の即応性を状況に応じて使い分けることが、杏雲堂病院の現場連携の大きな特徴となっています。
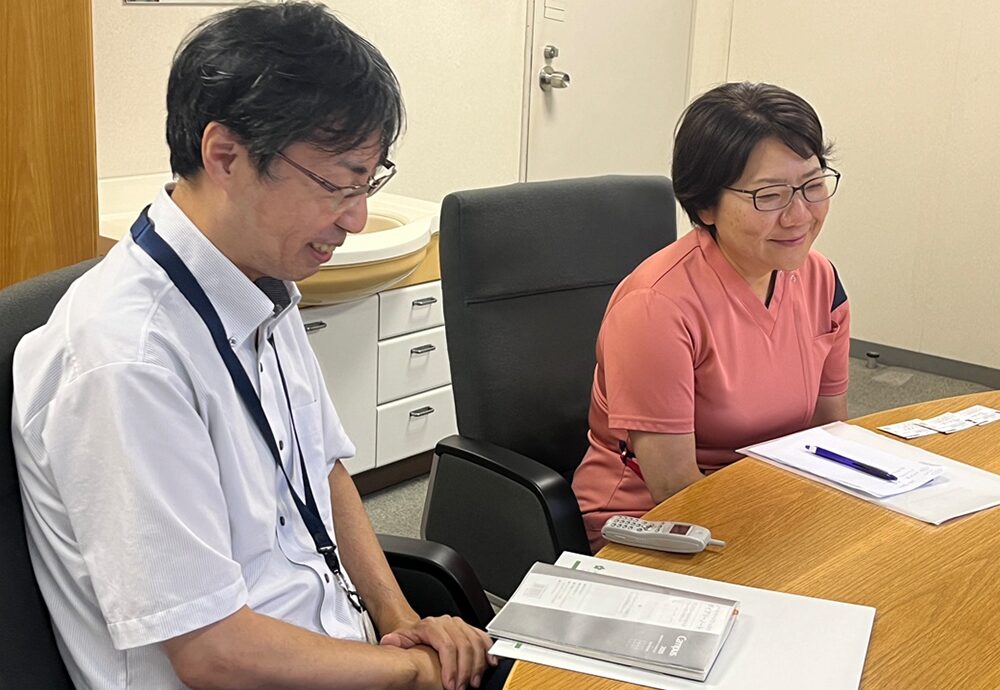
-医療機関以外の施設や介護事業所との連携について教えてください。
医療機関との連携に加えて、介護施設や地域の介護事業所との協力体制を強化しています。その一環として、毎月1回、施設スタッフと病院スタッフ(医師や看護師)が集まる情報共有会議を開催しています。この会議は、介護報酬上のメリットを施設側が得られるだけでなく、病院側にとっても将来的に入院が想定される利用者について事前に情報を得ることができる貴重な機会となっています。
また、訪問看護やケアマネジャーとの連携も重要視しており、年に3〜4回程度の合同勉強会を開催し、特にがん診療や緩和ケアに関する知識や実践を共有しています。こうした多職種間の連携を通じて、患者さんが施設や在宅で安心して療養生活を送れるよう支援している点が大きな特色です。
-在宅復帰や訪問診療とのつながりはどのようにされていますか。
在宅復帰を支援する際には、まず患者さんやご家族の希望を丁寧に確認することを重視しています。そのうえで、「バックベッド登録制度」を活用しています。これは、在宅療養中に体調が急変した場合や不安が高まった場合に、24時間365日いつでも杏雲堂病院が受け入れられる体制を整える仕組みです。
この制度により、患者さんやご家族は安心感を持って在宅療養に臨むことができます。また、訪問診療先の医療機関を選定する際には、これまでの連携実績の有無や連絡のスムーズさ、柔軟な対応力などを重視するとともに、ケアマネジャーや訪問看護師からの意見も参考にしています。こうした取り組みによって、病院と在宅医療の橋渡しが円滑に行われ、患者さんが希望する場所で療養を続けられるような体制を実現しています。
- 地域連携室の体制はどのようになっていますか。
地域連携室は前方と後方を合わせて約10名のスタッフで構成されており、前方は看護師2名と事務員5名、後方は看護師3名とソーシャルワーカー2名が在籍しています。特筆すべき点として、ベッドコントロールを事務職員が担っていることが挙げられます。
一般的には看護師が担当するケースが多い業務ですが、杏雲堂病院では今年4月から事務職が主導して行う体制を導入しました。これにより、看護師が患者ケアに専念できる時間が増え、全体として業務の効率化や役割分担の明確化につながっています。小規模病院ならではの柔軟な体制変更であり、各職種が互いの業務を理解し合いながら協力する姿勢が表れている取り組みです。
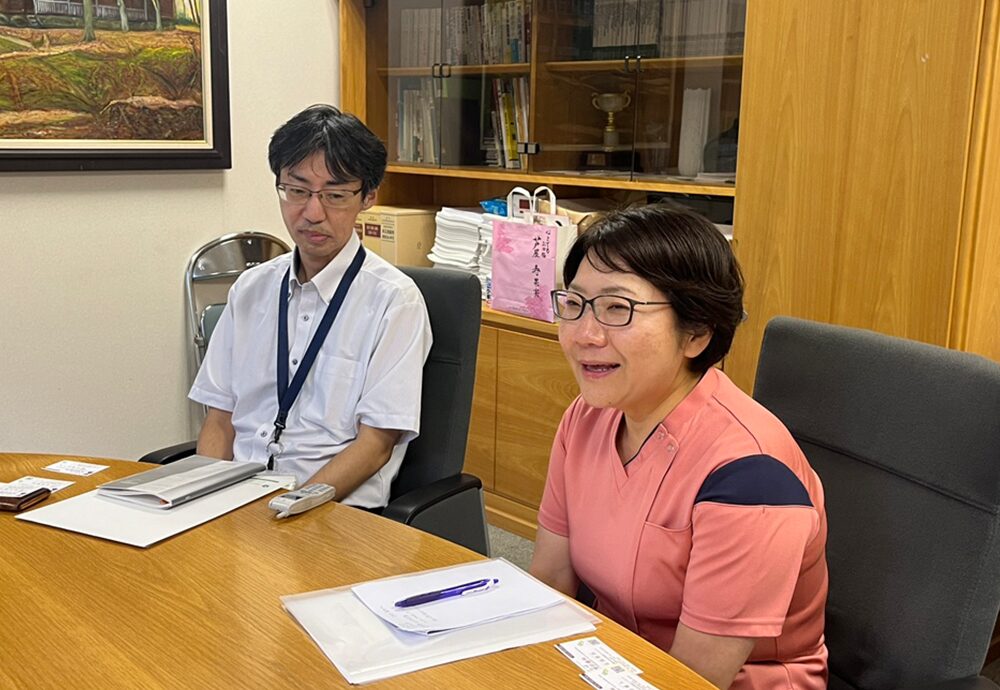
- 多職種連携やタスクシフトの取り組みについて教えてください。
医師の業務負担を軽減し、効率的な医療提供を行うために、タスクシフトやタスクシェアの取り組みを積極的に進めています。例えば、特定行為看護師の活用や、医師からの事前指示に基づいた看護師による対応などが挙げられます。ただし、実際の現場では医師の診察が終わらなければ対応が進まない業務も多く、十分なタスクシフトが実現できていない現状もあります。
職種ごとに専門性や見えている世界が異なるため、それぞれの強みをどう活かし、調整役がどのように機能するかが課題となっています。それでも、これらがうまく機能すれば、患者さんにとってよりタイムリーで効率的な医療が提供できるという大きな期待があり、今後の発展性を秘めた取り組みといえます。
- 地域に向けた独自の取り組みについて教えてください。
「あんずカフェ」という名称で、地域の医療・介護職を対象とした勉強会を開催しています。年に3〜4回程度行われるこの会では、特に緩和ケアをテーマに据え、病院のスタッフと地域の関係者が一堂に会して意見交換や情報共有を行います。
こうした活動は単なる知識の提供にとどまらず、顔の見える関係を築く場として機能しており、結果として地域全体の医療・介護の質の向上に貢献しています。病院という枠を越えて地域に開かれた取り組みを行うことで、杏雲堂病院は地域医療のハブとしての役割を担っており、信頼関係の構築にも大きく寄与しています。