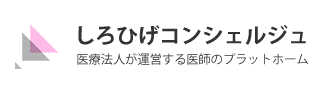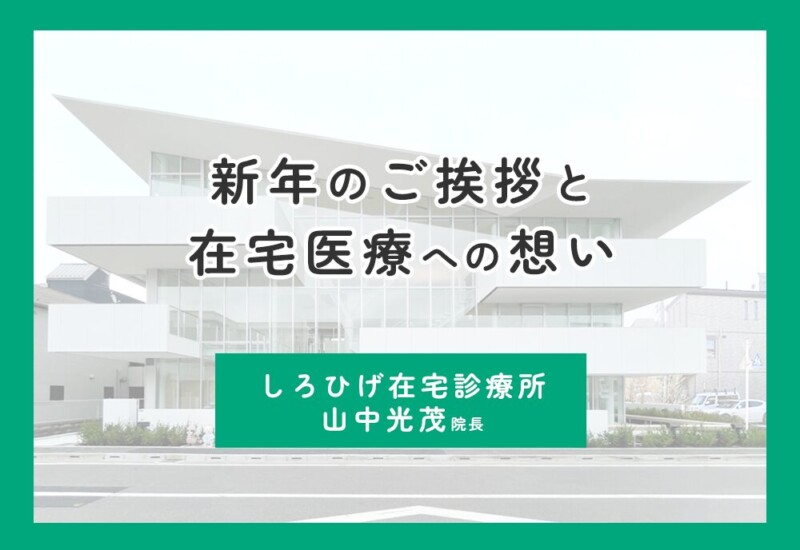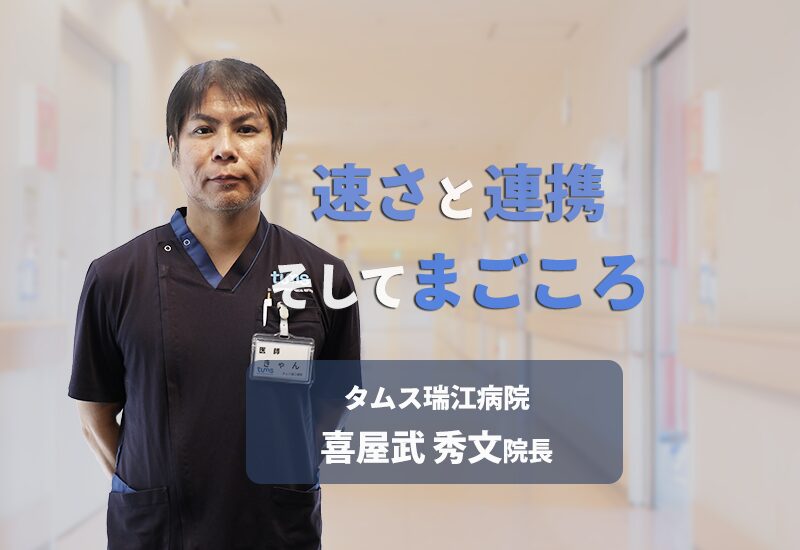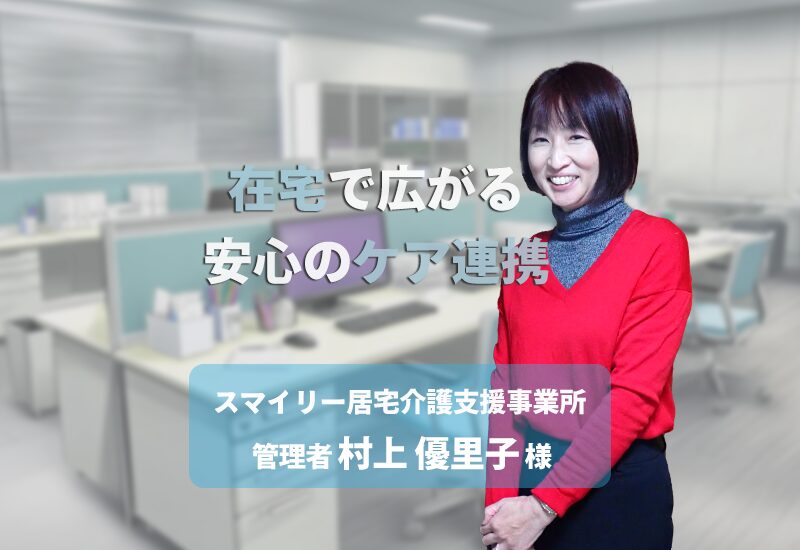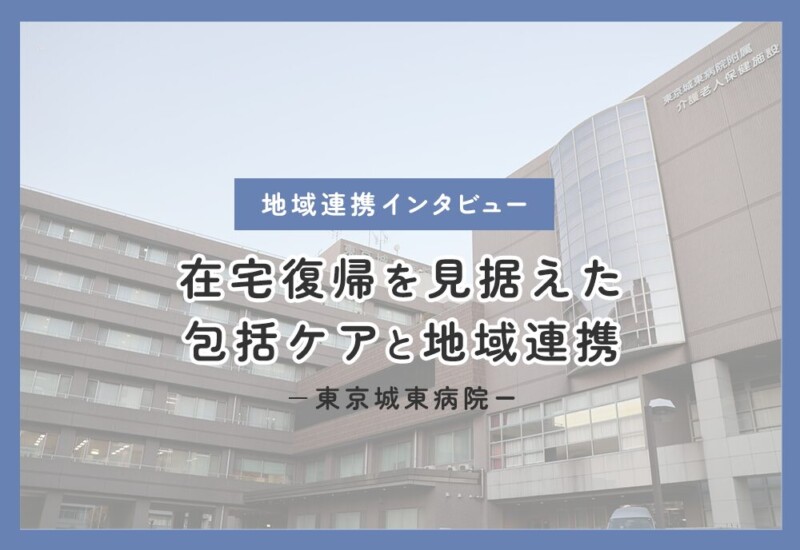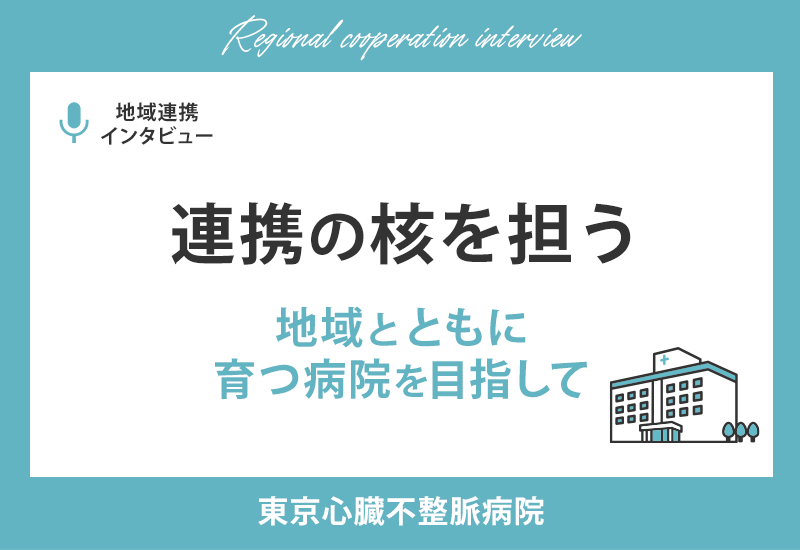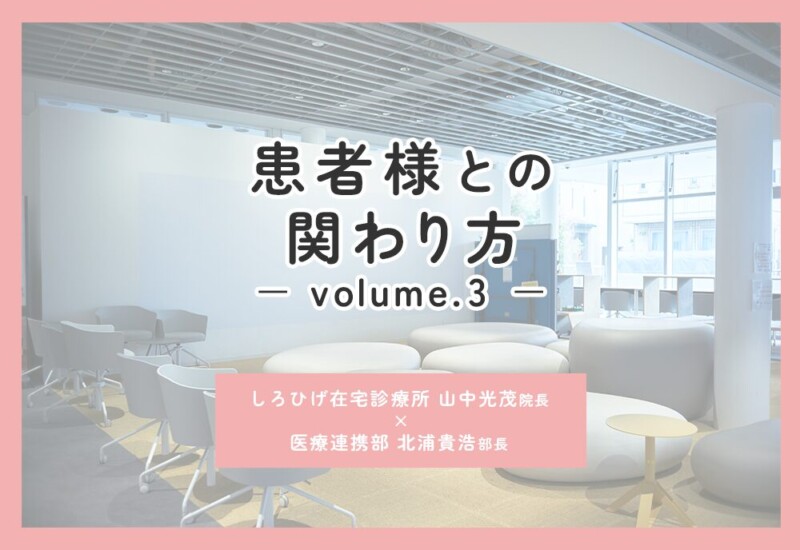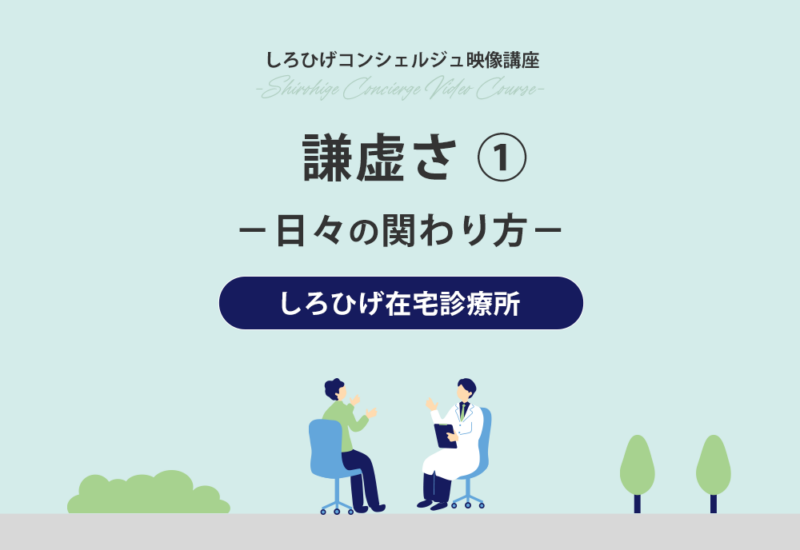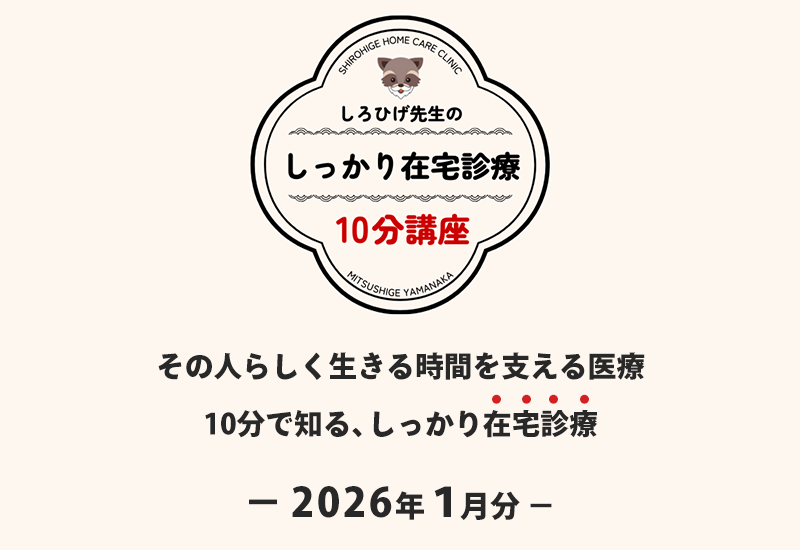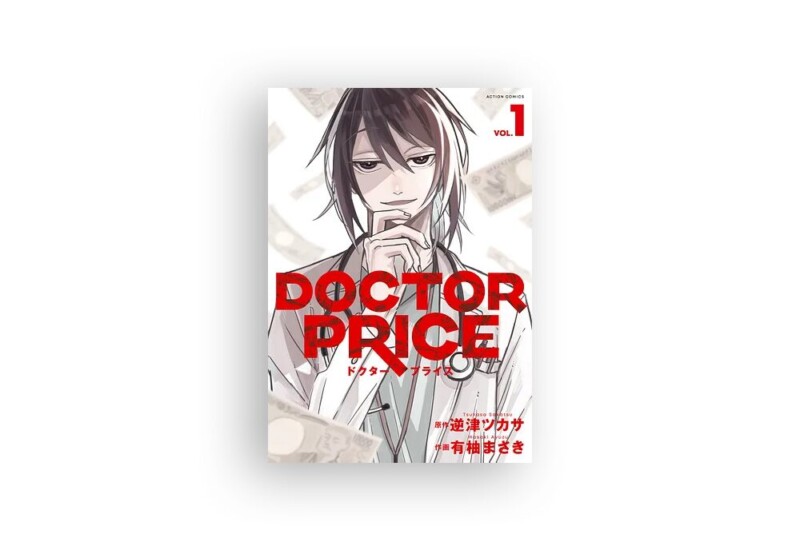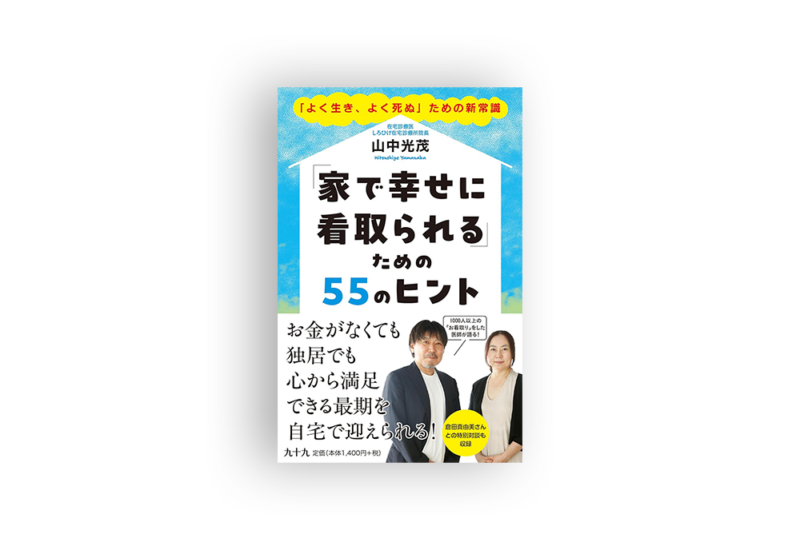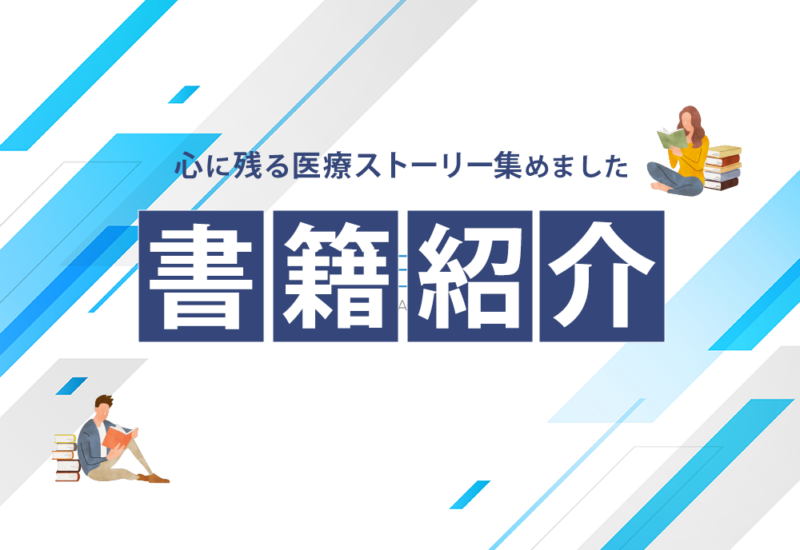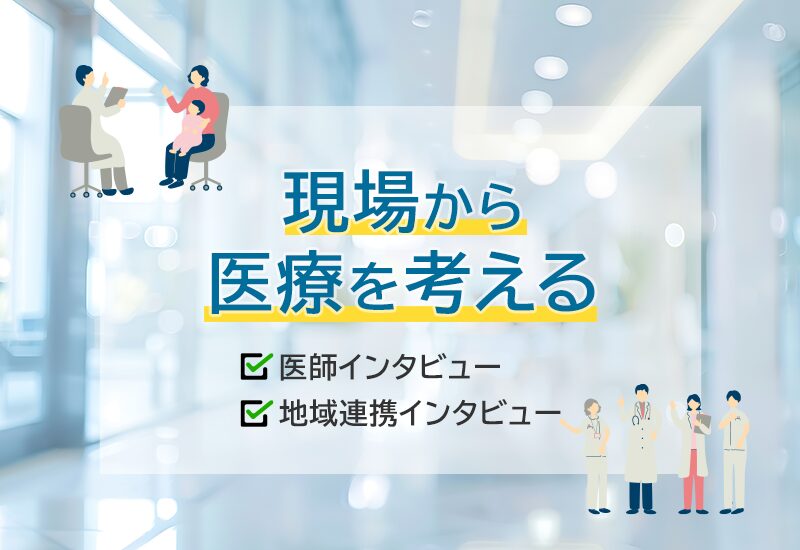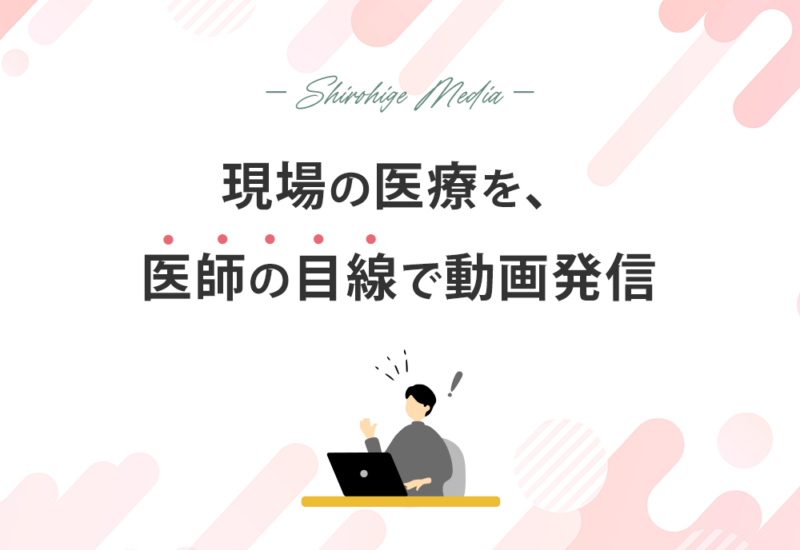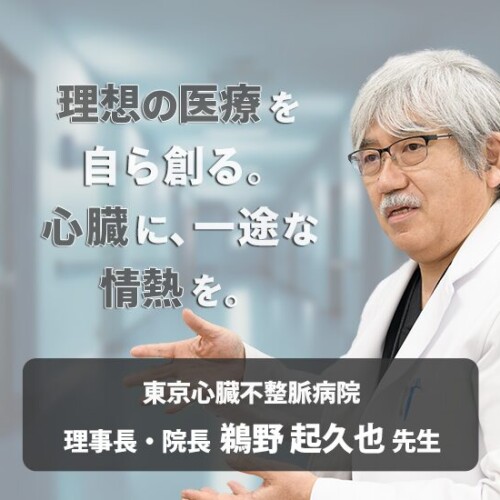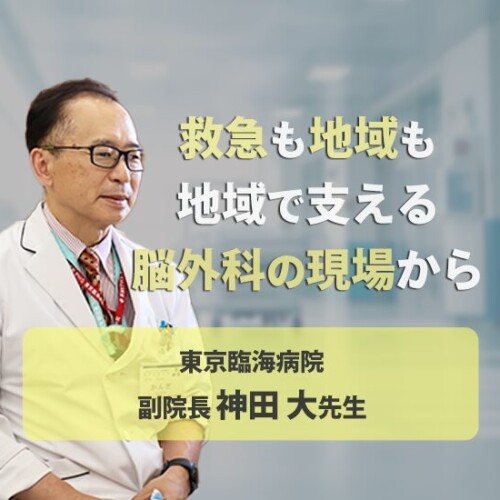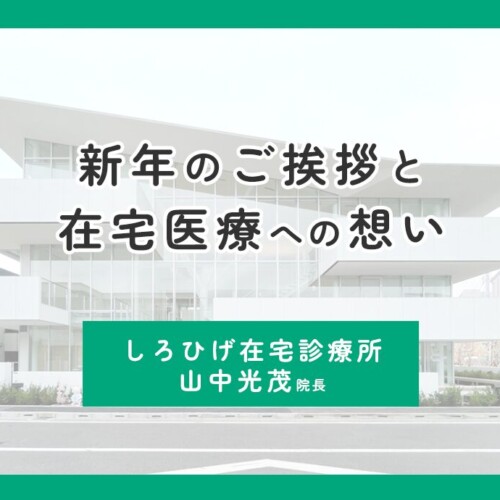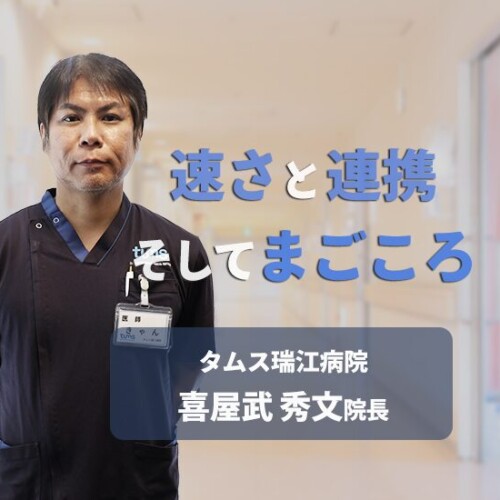暮らしとともにある医療を

今回、ファミリーケアクリニック吉祥寺 院長でいらっしゃる中西 貴大先生にご登場いただき、貴重なお話を伺いました。
-ファミリーケアクリニック吉祥寺を開設するまでのキャリアについてお聞かせください。
三重大学医学部を卒業後、神奈川県の湘南鎌倉総合病院で初期研修をしました。
兵庫県の出身なので幼少期に阪神・淡路大震災を経験し、高校生の時にはJR福知山線の列車事故があり、身近な人が亡くなるなかで「目の前で苦しむ人がいたときに手を差し伸べられる人でありたい」と考え医師を志しました。
そうした原点から、救急・災害医療に進みたい思いもあり、研修先を選びました。
初期研修後は練馬光が丘病院にて、救急・ICUでの入院から退院後の外来診療まで一気通貫で診る経験をしました。
その間に東京の神津島や沖縄の与那国島などの離島でも勤務しました。
2018年からは多摩総合医療センターに異動し、救急・集中治療に始まり、多くの方の最期を診る中で、緩和ケアの知識の必要性も感じ、福岡県の飯塚病院で緩和ケアの研修も受けました。
また学生時代から学生団体を設立し、東南アジアのラオスに診療所を作るなど海外での医療支援活動も行っており、初期研修中にはラオスでのNGO「ジャパンハート」の手術ミッションにも参加していました。
その後もNPO法人の理事として、ラオスやカンボジア、アフリカのタンザニアでも医療支援の活動を行っていましたが、新型コロナウイルスの流行が大きな転機となりました。
コロナ禍で海外での活動もままならなくなる中、都内の病院では多数の患者さんが運ばれ、時には5時間程度かけて東京の真反対から搬送されてくる方もいらっしゃり、地域医療の重要性を再実感しました。
また病院から自宅に帰り、住み慣れた家で最期を過ごしたいと考える患者さんも多く、そうした方が帰れずに病院で亡くなっていく現場を経験もする中で、地域でも患者さんを断らず、地域に根ざした医療を届けたいと考えクリニックを開設するに至りました。
- ファミリーケアクリニック吉祥寺の特徴や差別化ポイントについて教えてください。
患者さん一人ひとりの価値観や状況に合わせて「今」に最も合った医療を提供することを大切にしています。前職で救急・総合診療科に携わっていたこともあり、すべての医師が、幅広い診療に対応できるのが特徴です。
また専門性も兼ね備えたジェネラリストが多く、さまざまな診療科の専門医が在籍しています。例えば皮膚科では、院内で写真を共有しオンラインコンサルができる仕組みを整えており、どの先生でも常に相談できる体制となっています。
訪問診療未経験の先生には、経験豊富な医師に同行していただきながら在宅医療に慣れていただくケースもあります。また常に看護師を含めた経験豊富な診療コーディネーターが同行し診療がスムーズに行えるようサポートします。
その他、当院では終末期の患者さんも多くいらっしゃいます。2025年からは日本緩和医療学会の連携施設にもなっており、当院での勤務を通して、緩和医療学会の専門医も取得可能になりました。
上記のように地域の方々に安心していただける体制を構築し、「地域のお困りごとに迅速に応える医療チーム」として、医師だけでなくスタッフ全員で相互にサポートし合いながら、急な依頼等にも柔軟に対応しています。

-理念に掲げられている「ご自宅でも、質の高い医療で生活に安心を届ける」を実現するために、具体的にどのような取り組みをされていますか。
在宅医療では、診療所だけでなく、さまざまな地域の事業所と密な連携を取っていく必要があると考えています。その中で当然ながら医師としての医学面での専門性も求められていると考えています。
そのため、日常診療では毎日朝夕にカンファレンスを行い、困っているケースや治療方針をフラットに共有しています。加えて、月2回ほど各科の専門医に勉強会をお願いし、知識を更新しています。定例以外でも、フットケアを専門にしている皮膚科医を招いて陥入爪の処置に関して指導いただき、実際に診療同行をしてもらったり、骨粗鬆症の治療について整形外科医からオンラインレクチャーを受けたりと、外部の専門知見も積極的に取り入れています。
そして在宅では、医学だけでない面での課題もあり、そうしたケースでは「モヤッとカンファレンス」と称して困難事例や倫理面での困りごとなどを話し合う時間も設けています。
また地域との連携については、顔の見える関係になれるよう、定期的に講演会を行ったり、連携を深めるための交流会を行っています。またほぼすべての患者さんでオンラインツールを用いて診療の情報共有を行っているのが特徴です。
リアルタイムで共有し密な連携を取れていることで、状態が崩れる前に対応ができています。
-訪問栄養について、教えてください。
当院では管理栄養士が医師や看護師、あるいはリハビリで介入いただいている理学療法士や言語聴覚士、歯科医師と連携しながら、在宅での栄養管理を行っています。
具体的には、食欲の低下や嚥下機能の問題、糖尿病や心不全などの基礎疾患を踏まえた食事指導や栄養調整を行います。また食を通してのお困りごとに応えることを目指しており、訪問栄養として介入し管理栄養士が毎週顔を合わせお話することで、自宅でお一人暮らしの高齢者の方が抗不安薬をやめられたといった事例もありました。
患者さん本人だけでなく、ご家族やヘルパーなど多くの方を巻き込みながら、みなさんと一緒に日常的に取り組める工夫を考えています。
-医師として、日々の診療や業務において大切にしていることは何でしょうか。
最も意識しているのはその方の価値観に沿った判断・提案をすることです。
同じ年齢、性別、疾患の患者さんでも家族やこれまでの人生背景などは当然異なり、価値観もそれぞれです。
医師として医学的な正しさを知っていることは大前提として、その方が望む過ごし方をさまざまな角度から伺い、引き出し、それにあった選択肢をお伝えしたいと考えています。
在宅医療では、病気中心の生活ではなく、生活のなかでどう病気と付き合っていくのか、という視点も大切だと感じています。患者さん一人ひとりの生活や価値観を尊重し、医療的な判断だけでなく、その方らしい生活をどうサポートするか日々考えながら診療を行っています。

-院長として、また経営者として意識されていることや工夫についてお聞かせください。
自分一人で診られる患者さんの数には限界があり、一人ひとりが輝いて診療ができれば、より多くの人に私たちの医療を届けられると考えています。そのために、組織として安定した診療を続けるためには、医師だけでなく、看護師やコーディネーターなどスタッフ全員が働きやすい環境を整えることが欠かせません。
この1年でもスタッフの数は倍近くに増加しました。そうした環境の中でもクリニックが大切にしている理念を浸透させ、皆が同じように動けることを意識しています。
定期的に業務の見直しも行い、加えて地域活動等を通じて、地域の医療機関や介護事業所との連携を強化することで、患者さんにより良いサポートを提供できる体制を構築しています。
-今後のクリニックやご自身の活動に関して、目標や展望について教えてください。
当院のスタッフには、クリニックで勤務しながらも柔軟なキャリアを描いて欲しいと考えています。そのため個々のワークライフバランスや重視したいこと聞きながら、個人にあった働き方を提案しています。
そうした働きやすい環境を提供する中で、より多くの方にクリニックに関わっていただき、地域で暮らす方々が安心して生活できるよう、地域のお困りごとに応えていきたいと考えています。
また、大学時代を過ごした三重県にも定期的に伺っています。僻地医療も課題を抱えており、経営視点のある医師が増えることで異なる地域の医療にも貢献できると考えています。
そのため臨床能力に加えて、マクロの視点も持ち合わせた医師の育成にも力を入れていきたいと思っています。
そうした中で、当院の医療を、より多くの人に、より遠くの人にまで届けたいと考えています。