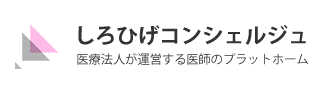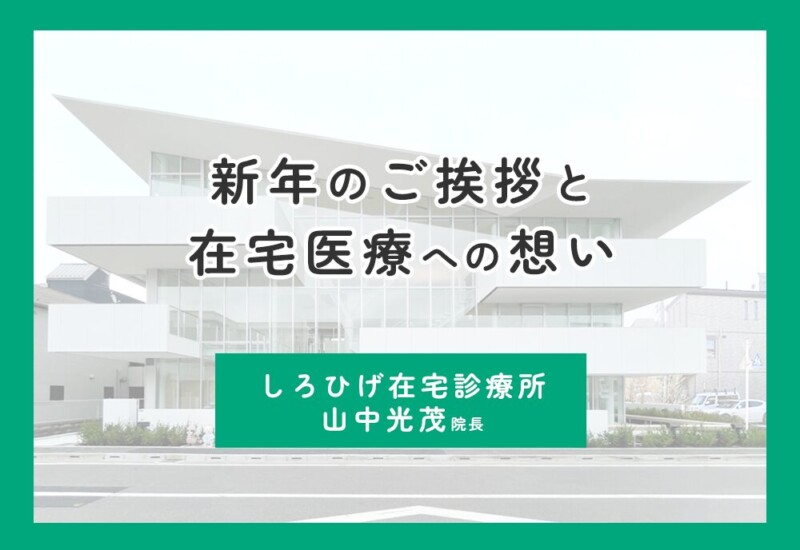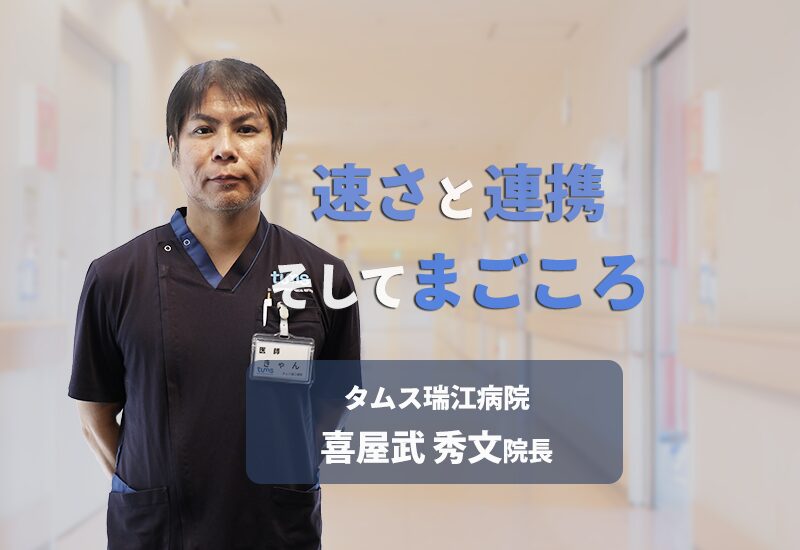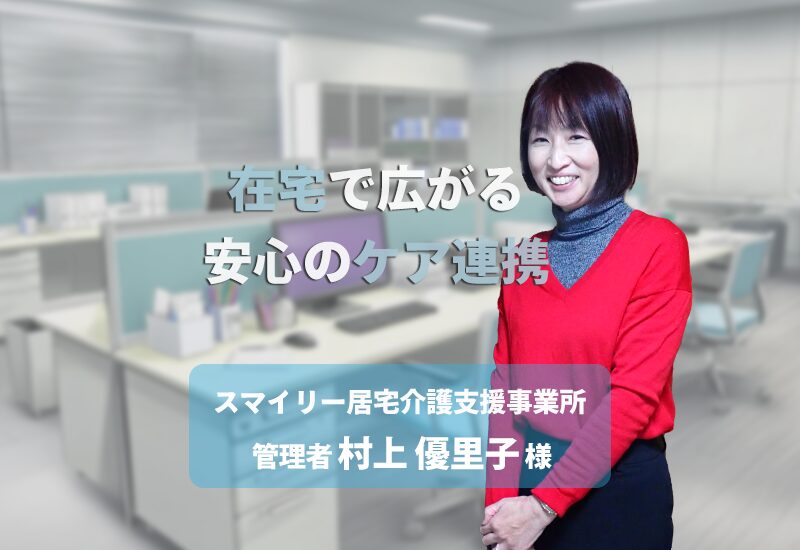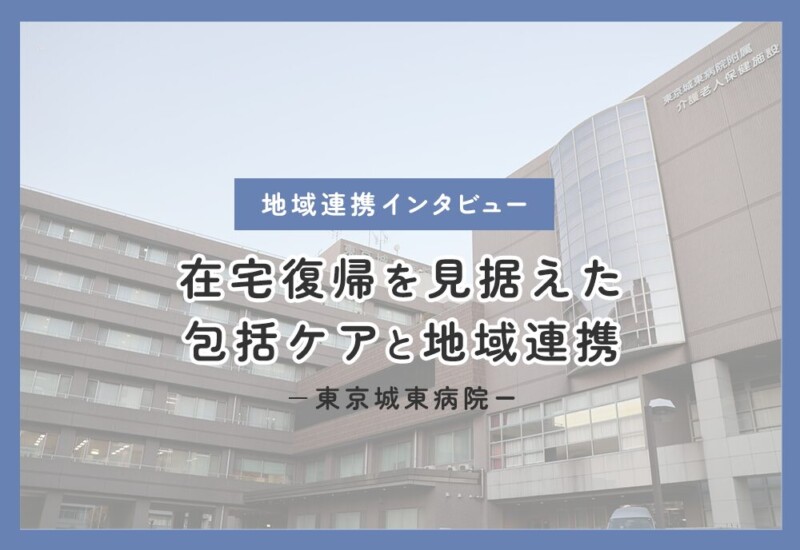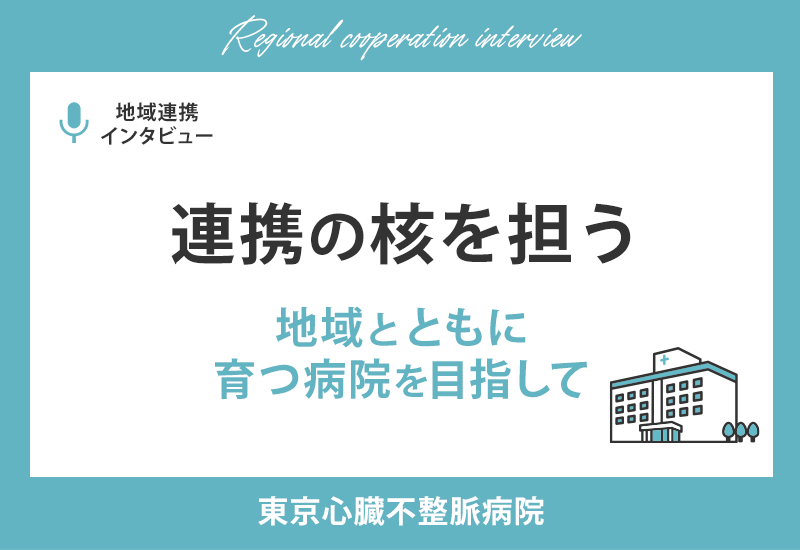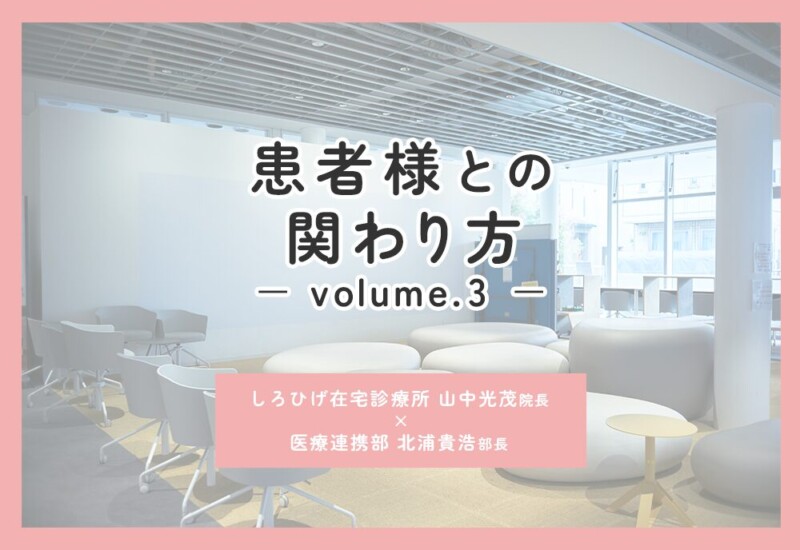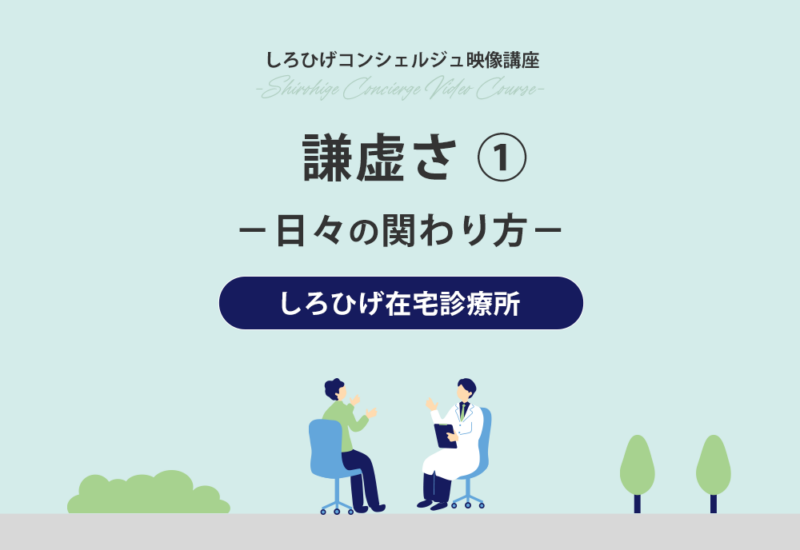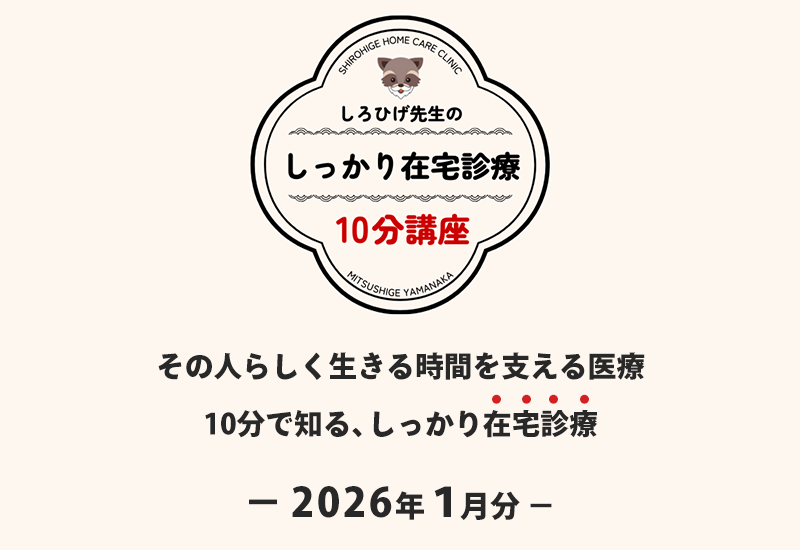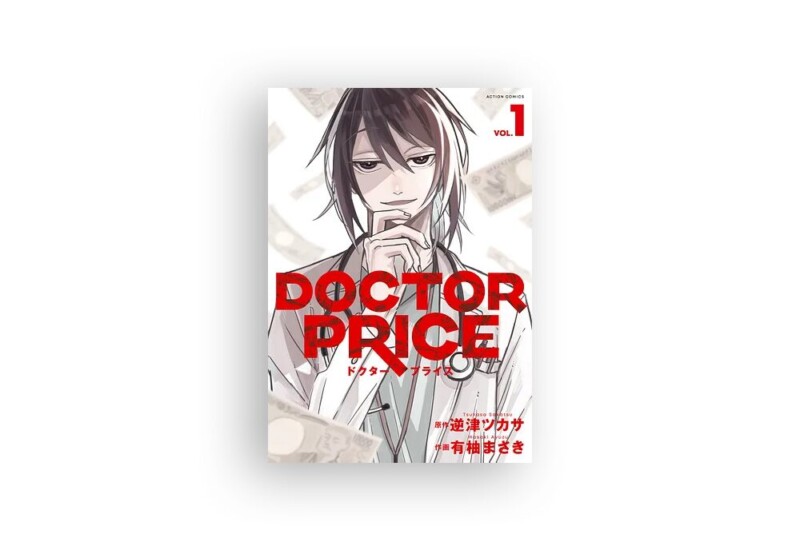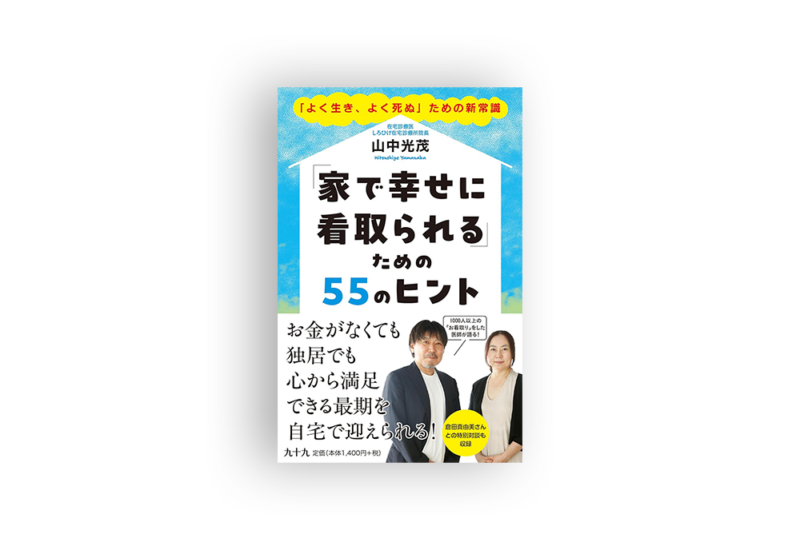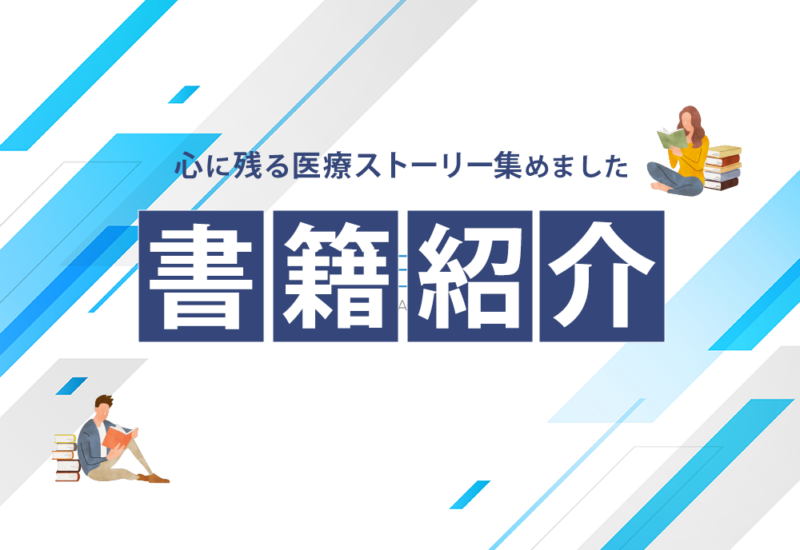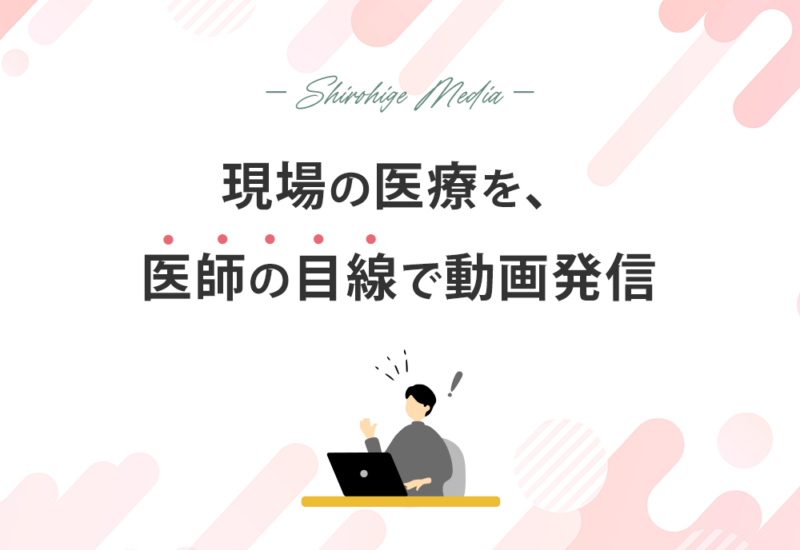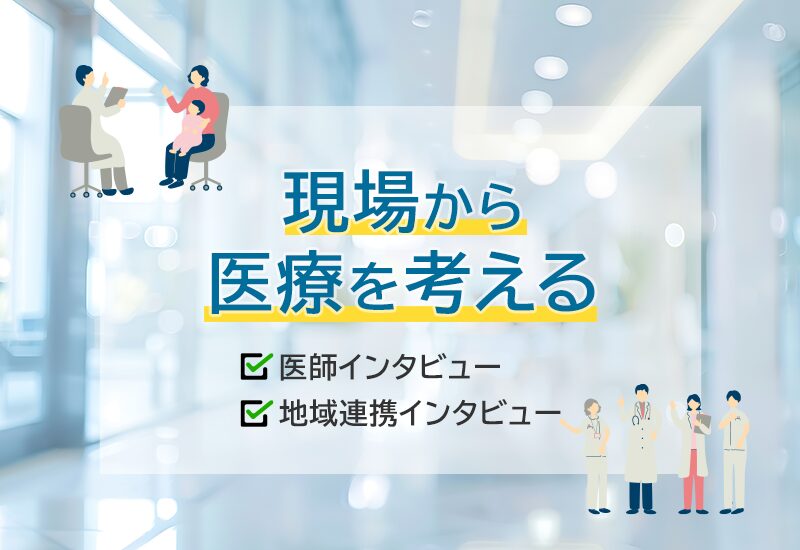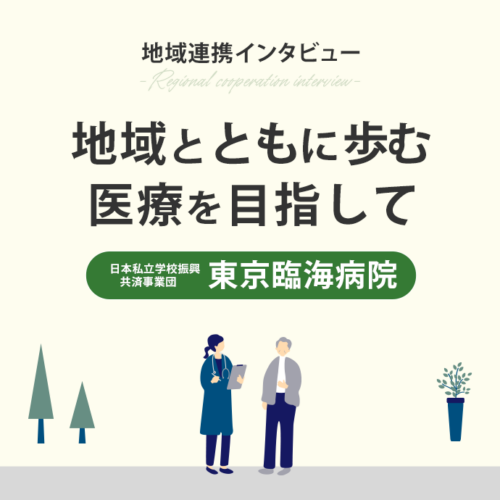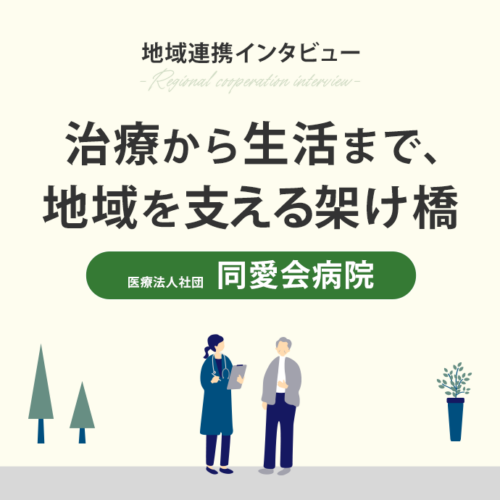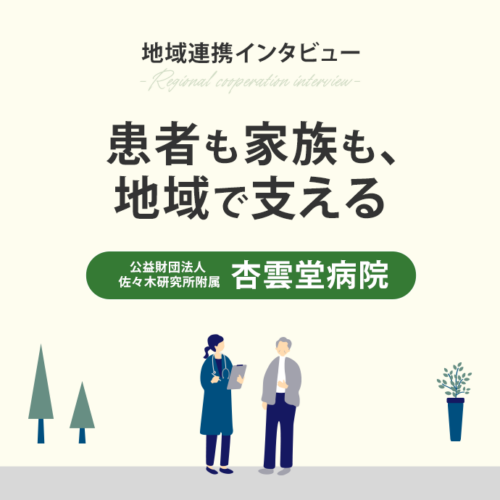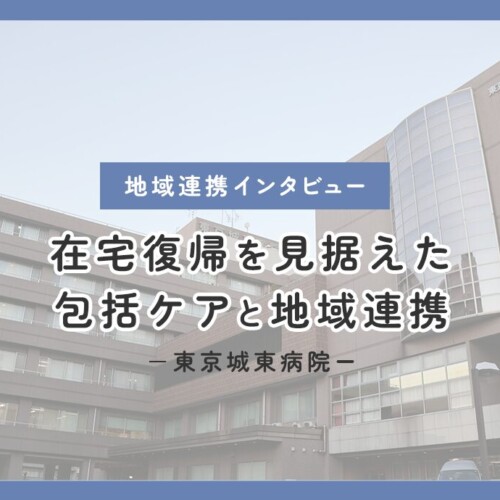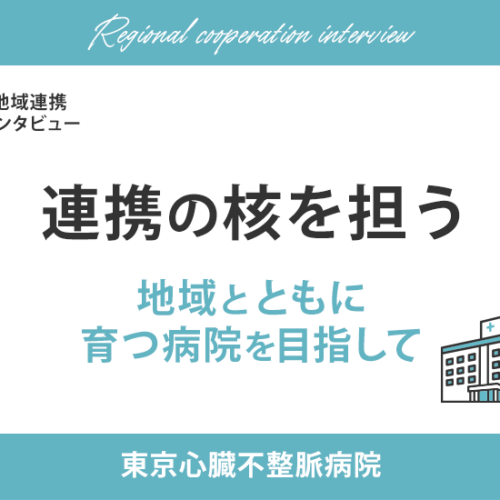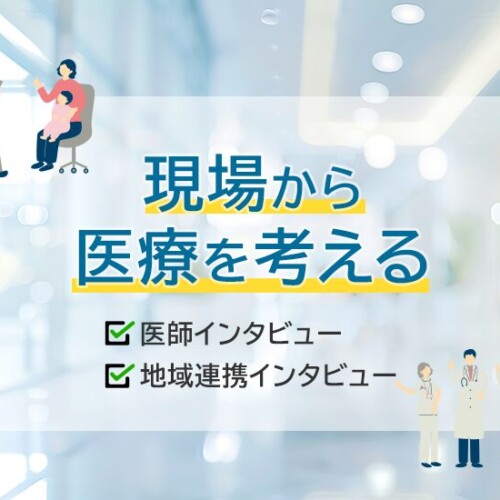患者も家族も、地域とともに安心できる医療

地域連携インタビュー(地域への影響・意識の変化)
医療法人社団城東桐和会 タムス浦安病院 院長代行 竹内 正人様に、地域連携の取り組みについてお話を伺いました。
- 地域連携において、病院設立当初から地域の意識に変化はありましたか。
地域の意識は、設立当初と比べると大きく変化したと感じます。特に、高次脳機能障害やリハビリテーションに対する理解が格段に広がったことが印象的です。設立当初は、急性期治療が終了した患者さんは、地域外の病院や遠方の施設に送られることが多く、患者さんやその家族は孤立感を抱きやすい状況でした。
回復期のリハビリを受けられる場所が限られていたため、病気や事故で生活が一変した方々が、地域社会とのつながりを失いやすいという課題がありました。しかし、浦安に回復期リハ病棟が設立されたことで、患者さんが住み慣れた地域でリハビリを受け、回復のプロセスを地域内で完結させられる体制が整いました。
医師や医療関係者の間でも、リハビリの意義に対する認識が深まったことが大きな変化です。単なる機能回復だけでなく、患者さんの生活の質や人生全体を支えるという包括的な考え方が浸透し始め、医療チーム全体で患者さんの社会復帰や生活の自立を視野に入れた支援が行われるようになりました。
これは、リハビリテーションの専門職だけでなく、医師や看護師、ケアマネジャー、地域の介護職、行政職までが一体となり、患者さん中心のケアを地域全体で支える文化が根付いてきたことを意味します。
さらに、地域の方々にとっても、「自分たちの町で回復できる」という安心感は非常に大きな意味を持っています。地域に医療資源があることは、家族や患者本人の精神的な支えとなり、治療やリハビリへの積極的な参加意欲にもつながります。
設立当初には想像できなかった、地域全体で患者さんを見守り支える意識が醸成されつつあることが、私たち医療従事者にとっても大きな励みとなっています。今後もこの流れをさらに強化し、医療・介護・行政・地域住民が一体となった地域包括ケアのモデルを作っていくことが重要だと考えています。

-地域のネットワークづくりや連携において意識していることは何でしょうか。
地域連携やネットワークづくりにおいて私が最も意識しているのは、「単に多職種を集めて話し合うだけではなく、課題を明確化し、その解決策まで導く責任を持つ」という点です。
多職種連携は時に盛り上がるだけで方向性を失い、結果的に実効性のない議論になってしまうことがあります。そのため、医学的な立場から課題を整理し、全体が同じ方向に向かえるように舵取りを行うことを重要視しています。
例えば、脳卒中や認知症の患者さんのケアでは、医療的観点だけでなく、介護・福祉・生活環境の視点も含めた課題抽出と優先順位付けを行うことで、チーム全員が具体的な行動に落とし込めるようにしています。
また、地域における医師会や大学病院との連携を活かし、市民向けの公開講座や啓発活動を継続して行っています。これにより、住民の方々が病気やリハビリに対する理解を深めるだけでなく、地域全体で「支える仕組み」が育まれると考えています。
病院の機能や専門知識を外部に開放し、医療従事者と住民、行政が一体となって課題に取り組むことで、単なる医療提供の枠を超えた地域包括ケアが実現できます。
さらに、医師としては、常に最新の知見を地域連携に反映させることを意識しています。
例えば、リハビリの新しい手法や認知症ケアのエビデンスを多職種と共有し、患者さんにとって最も効果的で生活に寄り添った支援を提供できるよう努めています。こうした取り組みを通して、地域全体で患者さんを支え、安心して暮らせる社会を作ることが、医療者としての使命だと感じています。