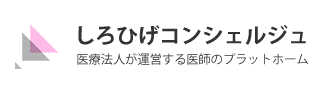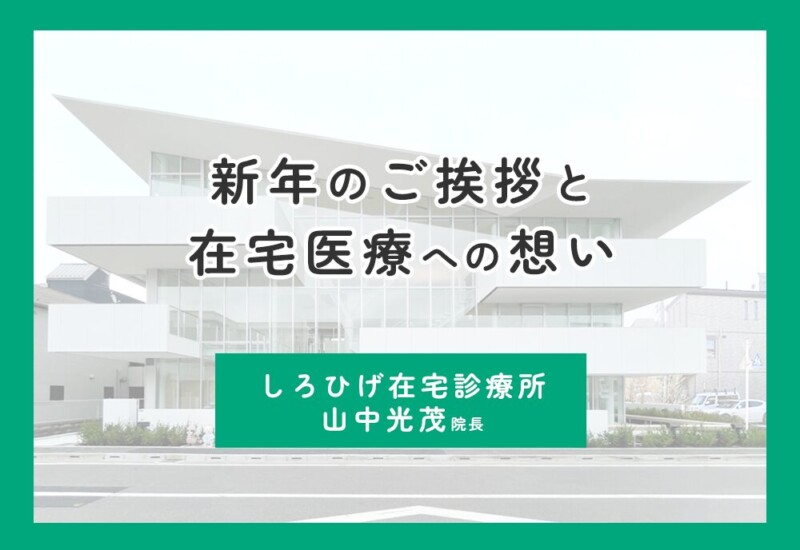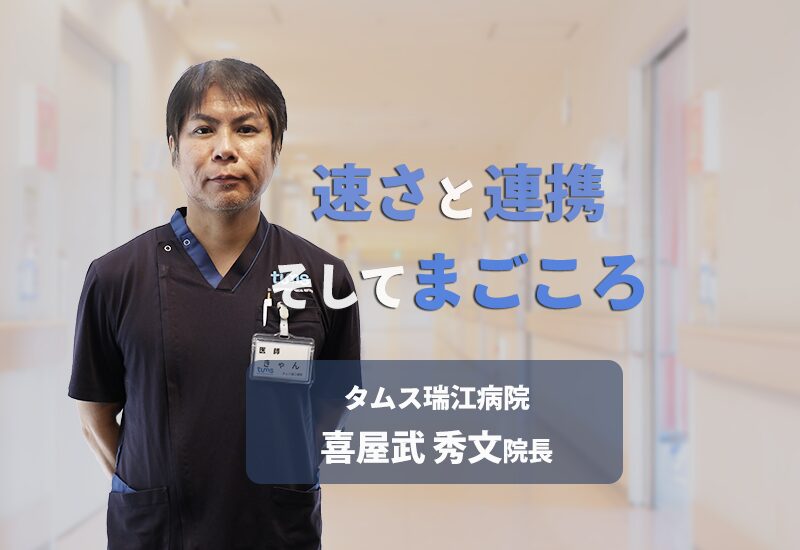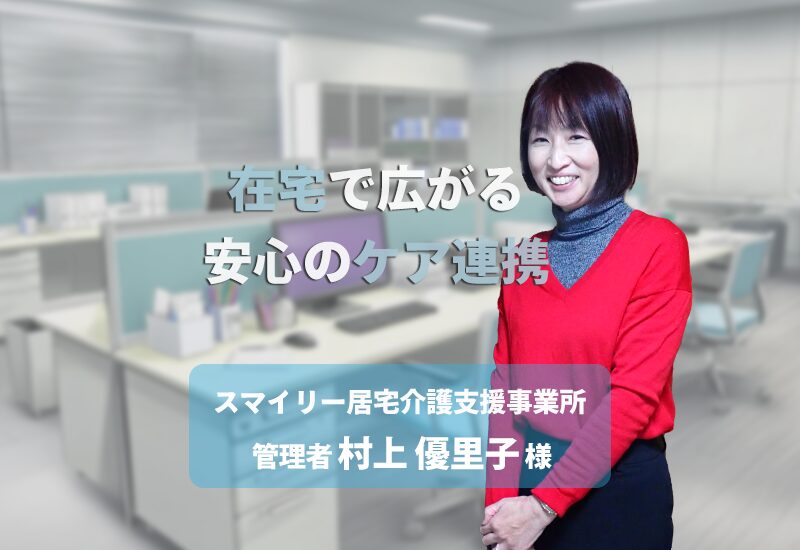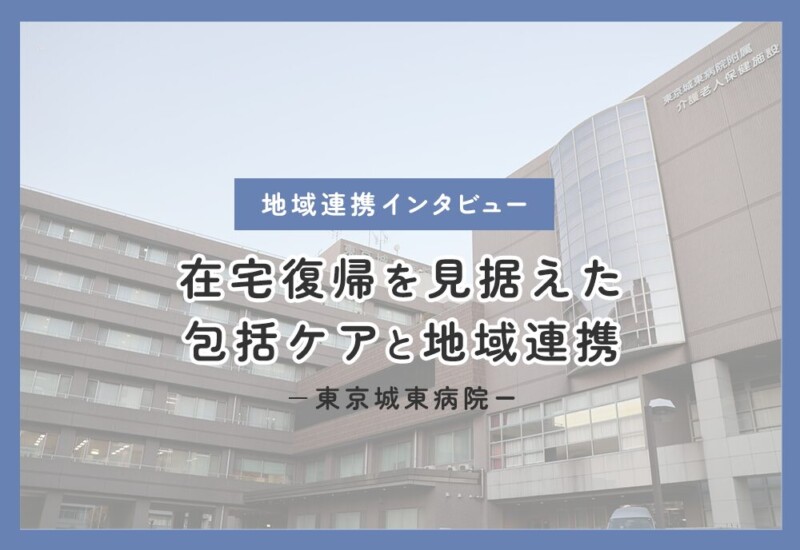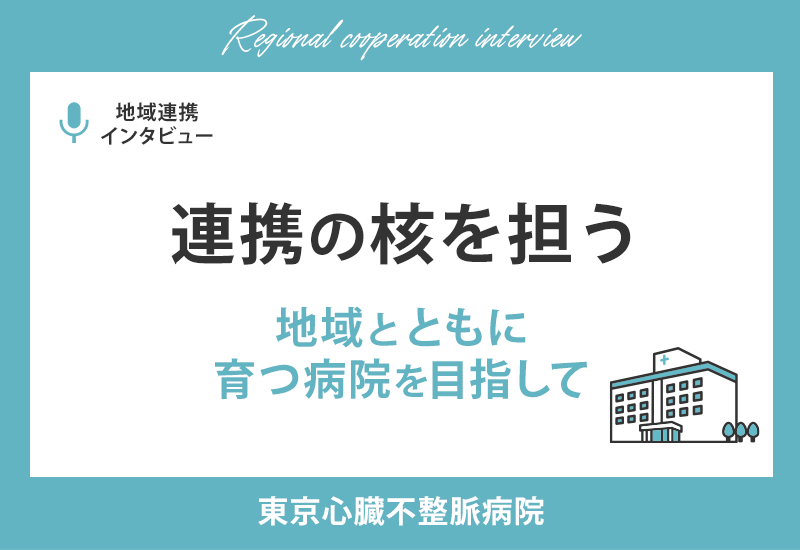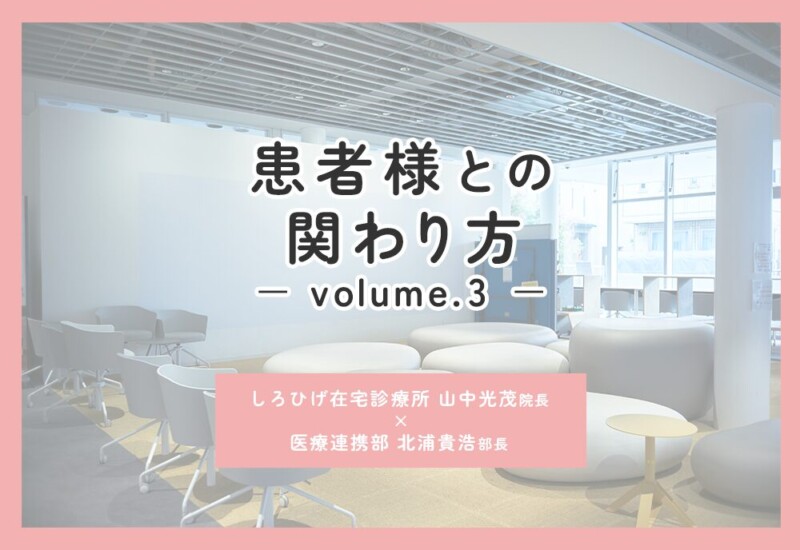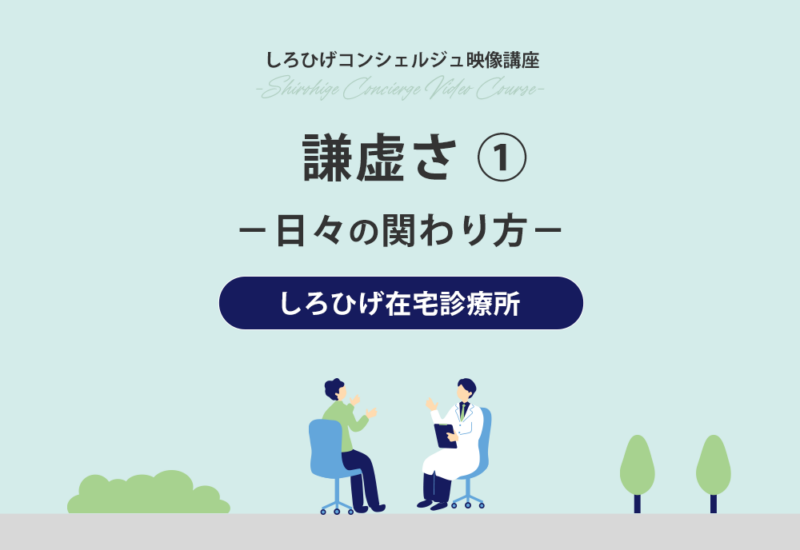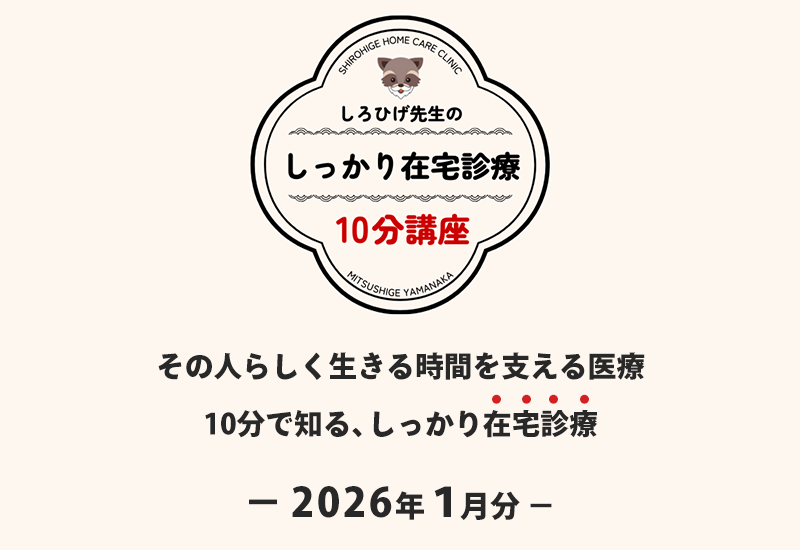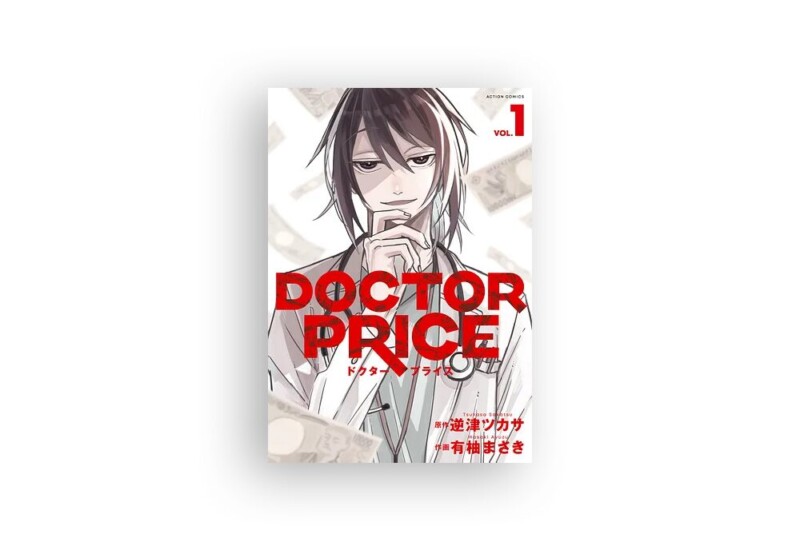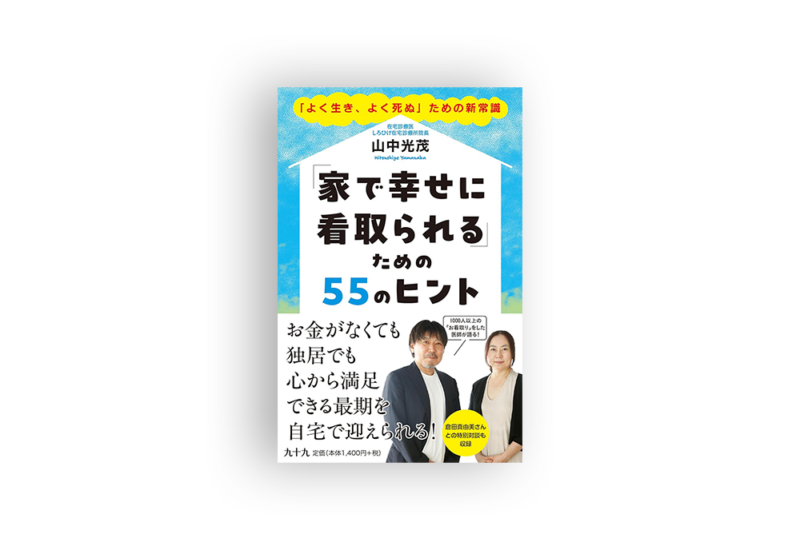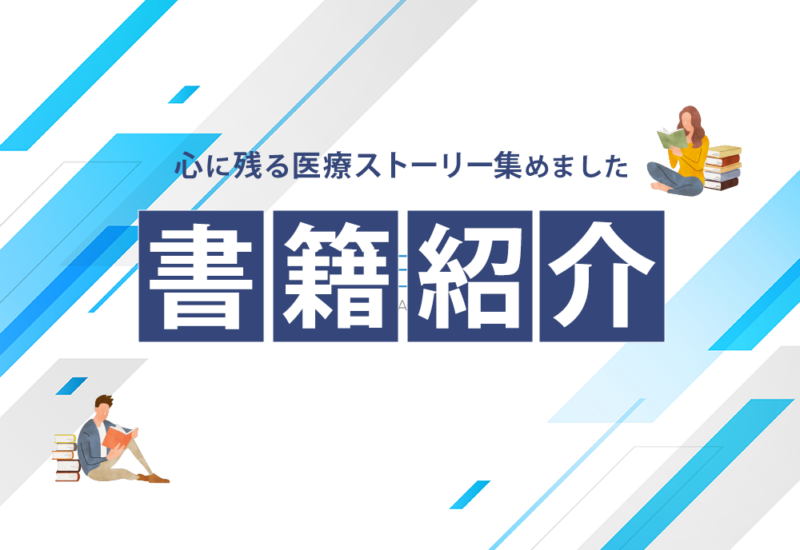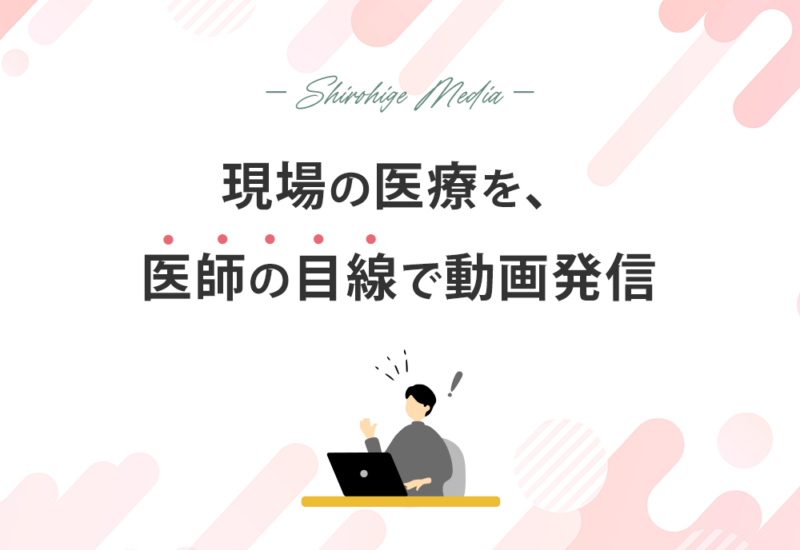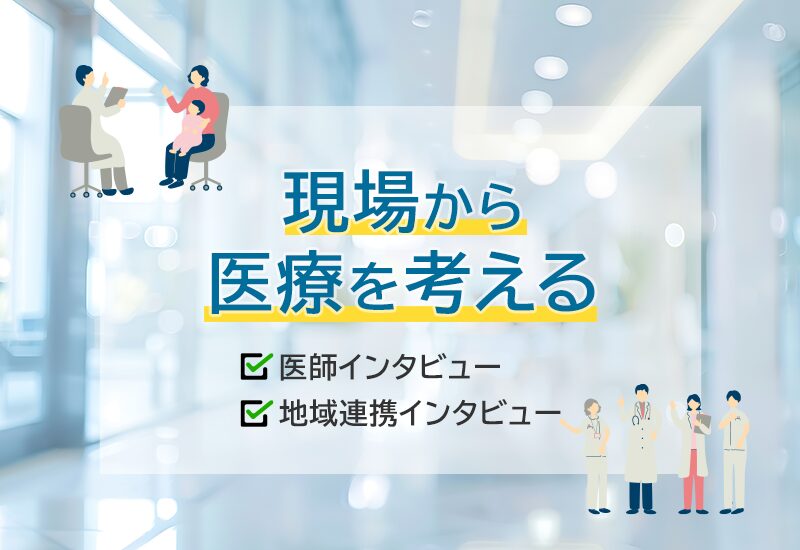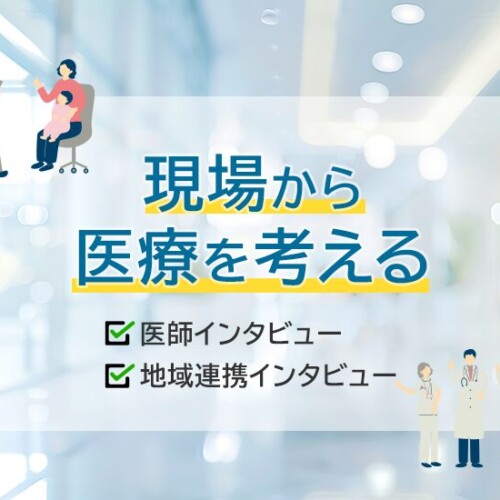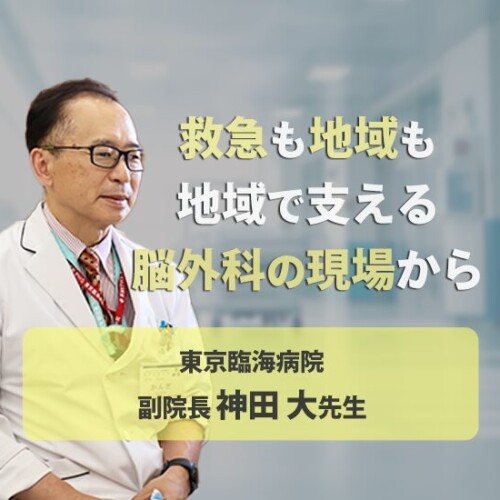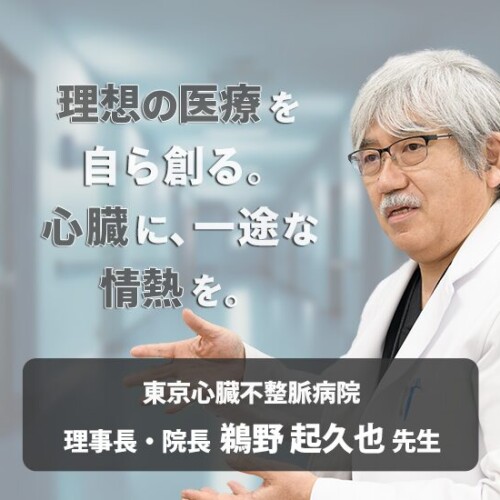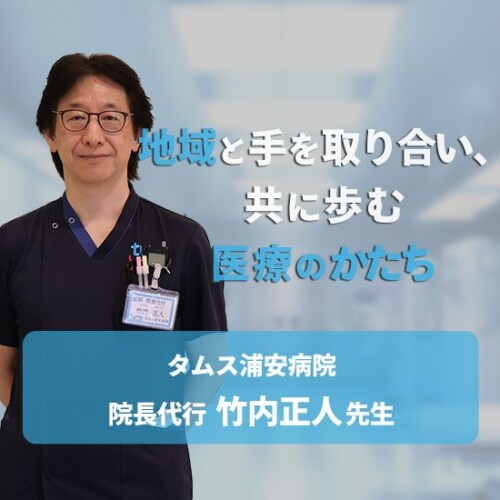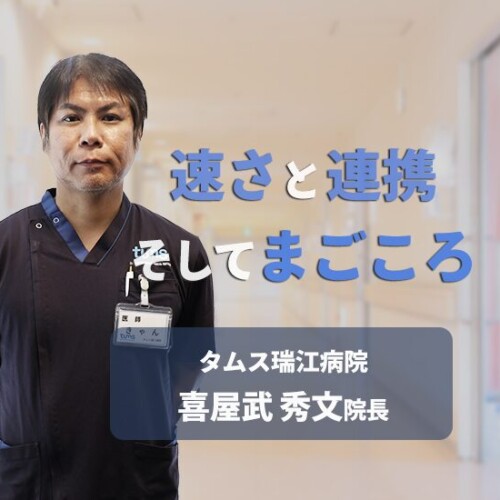「シームレスながん診療」を掲げて
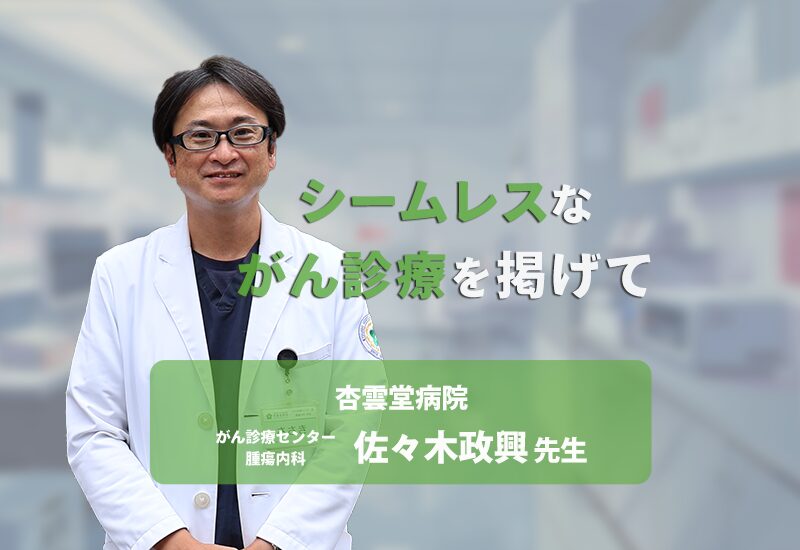
杏雲堂病院のがん診療センターでは、「シームレスながん診療」という理念のもと、患者一人ひとりに寄り添う包括的ながん医療を実践している。根治を目指す治療から緩和ケア、そして看取りまで、すべてを一つのチームで支える。
その中心で診療をリードするのが、がん診療センターを率いる腫瘍内科医の佐々木政興先生だ。
「治療の途切れをつくらないこと。それが最も大切だと思っています」と佐々木先生は語る。
多くの病院では、緩和ケアの段階に入ると転院を求められるケースが少なくない。しかしその過程で、患者にとっての“診療の流れ”が分断されることもあるという。
「当院では、がん治療から緩和ケア、看取りまでをシームレスにつなぎ、最後まで責任を持って診ていくことを大切にしています。完結できる体制こそが、当院の強みです」。
その理念を体現するかのように、同院では「患者と家族のさまざまな願いを支える緩和ケア」を重視している。
経済的・社会的背景もさまざまな患者を受け入れられるよう、緩和ケア病棟を拡大。地域の医療スタッフとも連携しながら、多様なニーズに応える体制を整えた。
「一人の患者さんの背景には、その人を支える家族や生活があります。そこにどう応えていけるかも、緩和ケアの大切な視点です」と佐々木先生は言う。
腫瘍内科としては、薬物療法を中心にがん診療センター併任の外科系診療科と密接に連携している。院内には「がん診療委員会」を設け、各診療科の治療方針を確認しながら、必要に応じて助言を行う体制も整備している。
対象疾患の中でも最も多いのは乳がんだが、希少疾患としては「胚細胞腫瘍」の加療にも注力しており、全国から若年患者が紹介され、他院で治療が難しいケースを引き受けることも少なくないという。
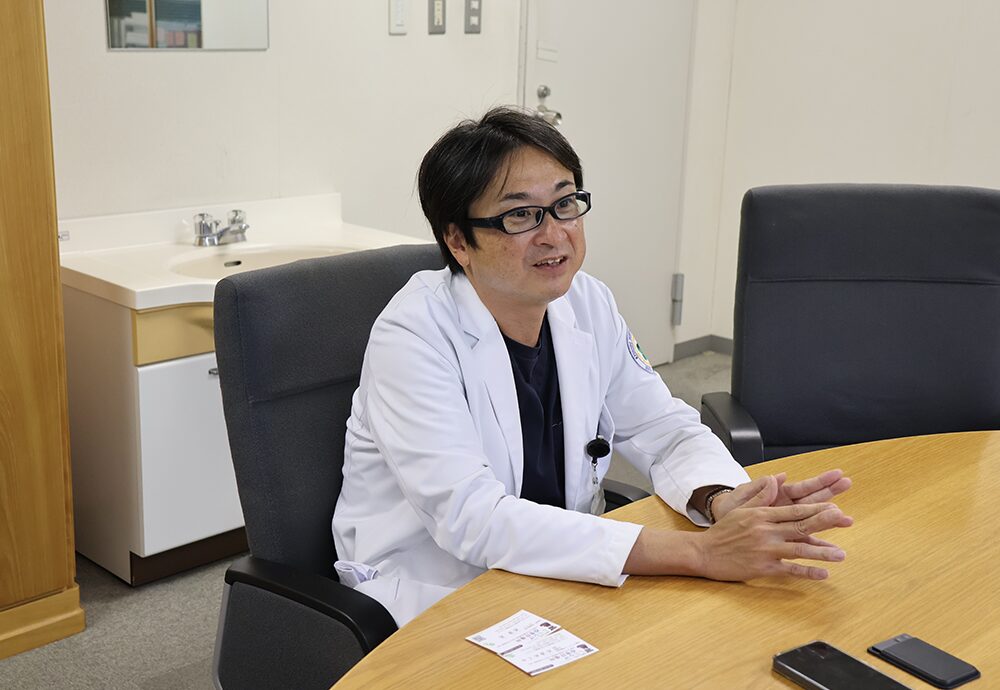
印象に残っている症例について尋ねると、佐々木先生は一人の患者を思い出す。
「当院の緩和ケアは“一方通行”ではありません。体調が回復すれば再び治療へ戻る“リバーシブル”な仕組みを大切にしています。ある患者さんは放射線治療後に体力が回復し、再び化学療法を行って趣味を楽しまれていました。余命数か月といわれていた方が、一年近く穏やかに過ごされたことがとても印象に残っています」。
患者や家族との関わりで何より重視しているのは「隠さないこと」。
「真実を伝えることは、時に患者さんにも医療者にもつらいことです。しかし、最初に目標を共有しなければ、後からズレが生じてしまいます。ですから最初にしっかりとお話しし、主治医として支え続ける覚悟で向き合っています」。
医療の進歩については、抗がん剤から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤へと進化した現状を語る。
「治療法の進歩により、副作用の種類も変化しました。今は複数の診療科が協力しなければ対応できないケースも多く、単一科では完結しない医療になっています」。
また、遺伝子検査やバイオマーカーの活用も広がっており、「治療中にも積極的に遺伝子情報を調べ、方針を柔軟に変えていく時代です。同じがんでも個別化医療の流れはさらに加速していくでしょう」と展望を語る。
チーム医療については、常勤3名・非常勤1名の腫瘍内科/緩和ケア医に加え、多職種カンファレンスを定期開催。看護師、薬剤師、リハビリスタッフなどが一体となり、外来や化学療法室で得た情報を迅速に共有している。
「患者さんやご家族が何を求めているのかを丁寧に探ることを大切にしています。医療者が良かれと思うことと、患者さんが望むことは必ずしも一致しません。だからこそ、多職種の視点で支えることが大切です」。
今後のがん医療について、佐々木先生は「暮らしと両立するがん治療」が大きなテーマになると語る。
「身体的な副作用だけでなく、経済的・時間的な負担も“有害事象”として捉える時代です。生活や仕事との両立、つまり社会的な視点を持つ医療がますます重要になると感じています」。
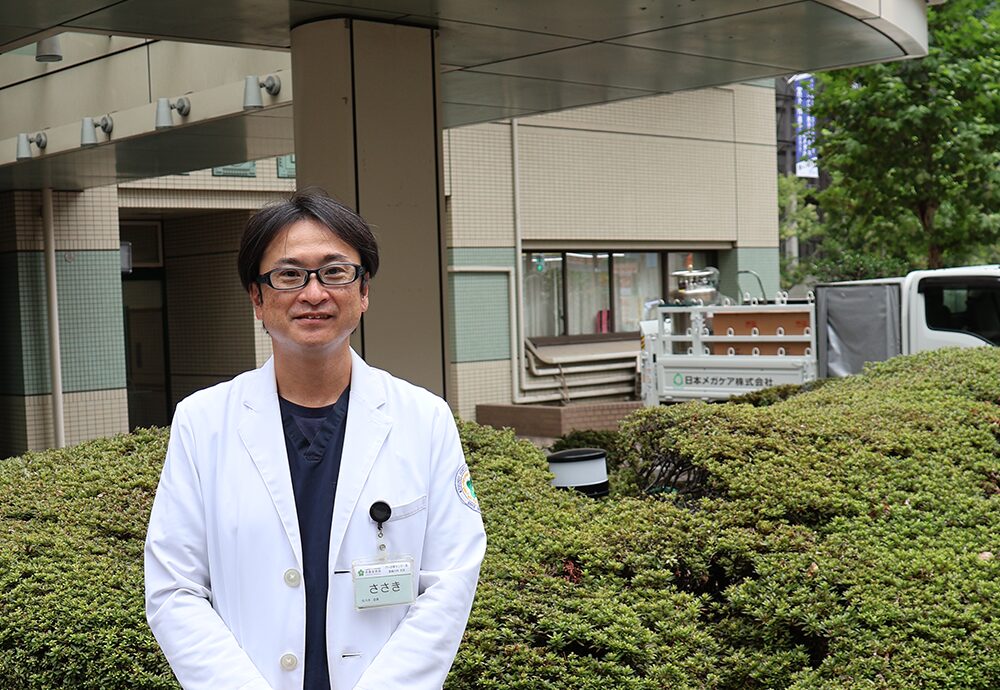
最後に、地域包括ケアの中での病院の役割について尋ねた。
「大きな病院に囲まれた地域の中で、患者さんを“家に帰すまで”を整えることが当院の役割だと思っています。病院は地域の“避難場所”のような存在であるべきです。在宅や介護施設と一体的に連携し、教育活動やカンファレンスを通じて、地域が補い合う仕組みをつくりたい」。
シームレスに患者を支える体制と、地域との連携を両輪に進化を続ける杏雲堂病院。
佐々木先生の言葉には、医療の先にある「人の生活」を見据えた温かな哲学があった。